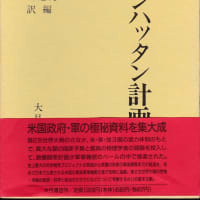▲小田部雄次 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』 2001年6月 恒文社 定価1800円+税
小田部雄次 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』 2001年 恒文社
ミカドと女官 幕末と明治維新の動きを読み解くには、倒幕の連盟の動向や、明治維新の前後の国際環境、幕末の江戸幕府の人的資源・ネットワークの考察も大切なのだが、一方、幕府権力は王権のもつ正統性という伝統資産を甘く見ていたのか、倒幕勢力の軍事的解体が困難とみると、倒幕運動の根源を絶つ資源として公武合体論を促す動きが立ち上がる。転変する急激な倒幕主体の内容変化を読み解き、その問題を見ていくのには、王権・権威筋の公家・皇族の人的資源や、ネットワークの組織を考えることも大切だ。
幕末に至る少し前までは、皇室周辺のことは、「せいぜい伝統芸能・儀式でもやらせておけ」程度の幕府権力の認識から、急転して、幕府権力側の「権威の欠如」認識が重要な、力点となっていく。
これはまた、皇室および公家勢力にとっても同じ。「権力と権威をめぐる相克」がある。 明治維新後、この難題を解決するとして、「明治華族制」が創造される。参議・元勲・元老たちが暗躍していく。これを宮廷側からみるとどうなるか。ミカドと宮廷組織・皇族輩出のシステム・女官の問題が出てくる。これらの問題に一貫して探りを入れてきたのが、小田部雄次のようだ。多くの著作を送り出しているのだが、まずは『ミカドと女官』から、はじめてみよう。
・
・
バーガミニが、『天皇の陰謀』 を米国で出版したとき、当初は大ベストセラーとなったのだが、その後、再版しようとした時に、日本大使であったライシャワーなどを含むジャパン・ハンドラーたちが、バーガミニの『天皇の陰謀』抹殺に動く。再出版のための出版社にまで多額の買収資金を送られ、出版を拒絶され、研究者としての道を絶たれたと言う。
バーガミニが『天皇の陰謀』を出版する際、1年ほど研究のため京都・ほかに滞在し、元公家・華族たちとも接触し、「ここだけの話」、「名前を伏せての話」 の重要な話を聴き遺している。
この聴取内容の一部が、生かされ、膨大な近代史料の解読とともに『天皇の陰謀』の論の主要論点となる。
秦郁彦もバーガミニに資料提供しているのだが、その後、『天皇の陰謀』を読むに至って、激しい攻撃を自分の著書で書いている。しかし、秦郁彦の批判は
「偽書」を使って書いているので、「偽書」であるという論点が主要なものである。バーガミニの中味に深入りしない。
『シオンの議定書』と同様に偽書と言うばかりで、細部にわたった批判の記述しない。おそらく、やぶへびになるからだろう。完全無視するのが、得策と判断したのだろう。
・
・
間もなく、明治維新から150年である。明治維新からこれだけの時間が経過したにもかかわらず、「帝国・戦争国家」「パクス・ブリタニカからパクス・アメリカーナ」の明白な支配から、一歩も踏み出さない・動けないでいる「属国日本」
バーガミニ 『天皇の陰謀』 と 鬼塚英昭 『日本の本当の黒幕』 の二著を微細にわたり読むため、前提となる準備作業も出てきた。
幕末から明治維新、そして陰謀渦巻く昭和のアジア・太平洋戦争、戦後占領処理に至るまで、皇室・宮廷・宮内制度・華族制と深い関係があるという仮説だ。もちろん天皇の果たした政治的主体性の意義も問われる。
立憲君主制の創成 → 軍閥の暗躍・一人一殺テロ横行 → 議会制の萎縮・有名無実化 → 戦争 → 敗戦交渉 → 戦後象徴天皇・民主独立国家
という国定教科書のような、これまでの日本近代化通説を真っ向から異論を提起しているのが、バーガミニ 『天皇の陰謀』 と 鬼塚英昭 『日本の本当の黒幕』 と思われる。
上の二著を読みながら、二人が論の典拠としている様々な資料(皇室周辺の日記類)の入手が足りないと痛感される。そしてそれとともに必要となってきたのが、明治から昭和前半期の皇室・宮廷・宮内制度・華族制のことだ。
この問題で、有力な情報を提供する研究の蓄積があると見えるのが、小田部雄次。

▲ 小田部雄次 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』
▼ 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』 目次

▲▼ 『ミカドと女官』 目次

▲ 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』 目次
「大正10年(1921)の春、、牧野と「二位の局」(柳原愛子)が鎌倉で話し合った問題、・・・・女官は伯爵以下の家に限るという「古代よりの慣例」があるので、公侯爵家より選ぶことはできないということであった。」
「これは皇太子裕仁の登場により、新しい「奥」を組織するための女官選出に関する課題であった。」
「しかし、そもそも「公侯伯子男」という五爵位の制度は近代になって創設されたものであり。「古代よりの慣例」というのは奇異な感じがする。おそらくは最上流の公家からは女官を選ばなかったということなのだろう。」
「女官および後宮の歴史的変遷を大まかに見れば、律令以前、律令による制度化、律令制度崩壊による変質、近代における再編というように区分することができる。」
「藤原摂関家の繁栄により確立した女官の身分制度が、基本的には近代の女官制度を支える「古代よりの慣例」ということになろう。そして摂関政治が崩壊し、武家の時代になっても、女官の身分制度の型式的な大枠は摂関時代のものが踏襲されたのである。」
「江戸幕末期の女官についていえば、高級女官の最上位にある典侍には、「羽林家・名家の中で上の部」の子女がなり。「摂家・清華・大臣家の姫君」は典侍にならないという(下橋敬長 『幕末の宮廷』。)」
「おそらくはこの「摂家・清華・大臣家の姫君」が、愛子のいう女官にはならない「公侯爵家の子女」にあたり、これらの姫君は「后妃」になるのであって、女官にはならないという意味なのであろう。」
「典侍にはならない「摂家・清華・大臣家」の摂家とは、摂政関白になる家柄であり、近衛、九条、二条、一条、鷹司の五摂家であった。」
「清華は摂家に次ぎ、「三公とは太政官の最高峰の太政大臣、左大臣、右大臣、内大臣の総称である。久我、三条、西園寺、徳大寺、花山院、大飯炊御門、菊亭、広幡、醍醐の九清華であった。」
「大臣家は中院、正親町三条、三条西の三家であり、「大納言に任ぜられて大将を兼ねず、内大臣に任ぜらるるを以て先途といたします」といわれた家柄であった。摂家や清華より次位にあるが、「ともあれ大臣になれる家」といわれた。」
「一方典侍に上がる羽林家は、摂家、清華、大臣家より下位にあたり、大納言、中納言、参議にまで昇進でき、近衛中・少将を兼ねた家柄である。四辻、中山、飛鳥井、冷泉、六条、四条、山科などがあった。『幕末の宮廷』)。」
そして、典侍の下位に掌侍(ないし)、命婦(みょうぶ)、女嬬(にょじゅ)と続くのが、幕末から近代にかけての基本的な女官の序列であり、掌侍以下にはより下位の家柄の子女がなったわけである。」・・・・・・・・
「こうした身分意識は、近代においても、「奥」の外、たとえば、近衛文麿や西園寺公望など政界で活躍する上流貴族たちの間においても意識され維持されていたのであった。」
「近衛は華族とは清華のことと断じて、近代の新興貴族を軽蔑していた。西園寺は元老でありながら、青年の近衛に対しても摂家であるが故に強い敬意を表していたのであった。」
「摂家の近衛や、清華の西園寺からすれば、東条英機や吉田茂などは一介の臣民に過ぎず、単なる実務官僚でしかなかった。国際社会の第一線で活躍した上層の政界人においてすら、こうした旧来の身分意識が強く残っていたのである。外部との接触の少ない「奥」においては、より頑迷固陋なものがあった。」
「いずれにせよ、後宮は近代の華族制度の前提となる旧来の身分制度に拘泥し、それを維持し、諸判断の基準にしてきたのである。そうした、「奥」の独自の身分秩序の中に愛子は起居し、「古代よりの慣例」を聞き伝え、肌で知っていた。(柳原)愛子はこうした慣例を、宮内大臣に就任したばかりの牧野(信顕)に伝えたのであった。」
小田部雄次 『ミカドと女官 菊のカーテンの向こう側』 (28頁~31頁)
上の記述は、大正天皇が病の中、宮内大臣になった牧野伸顕が、宮中のことや、後に昭和天皇になる裕仁の后妃選定に関わる前段の記述の部分である。
大正の終わり頃、宮内大臣となった人物ほか、宮中の要、天皇やその側近に会うには、この「宮内大臣」を通さなければ、会うことも叶わなかったはずであるが、この宮中奥深くに、あるいは宮中そのものに、やがて軍国主義に突き進む日本の闇、「伏魔殿」があった。 謎が解かれるべき、「伏魔殿」が眼の前の、「そこ」にあった。
灯台もと暗し!なのだね!
つづく