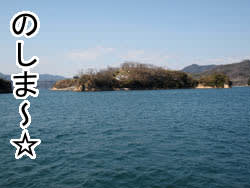神様は、台所が大好きです。
だから昔は、
どこの家の台所にも、
神様がいらっしゃいました。
台所という場所は
いわば、家一軒一軒に存在する、
小さな神社のようなものなのです。
『神様ごはん』の冒頭の文章です。「なるほど~。そうだよね」と、一気に読み上げた私は、翌日の日曜日に早速、台所や冷蔵庫の掃除・片付けをカミさんとおこないました。著者は、他に、料理に“神道”の意識を活用していることも感銘を受けました。
「料理、食事のチカラはスゴイ!」ということは、以前から認識していました。それは、10数年前に観た、映画「ガイアシンフォニー(地球交響曲)第二番」の佐藤初女さんのエピソードによるものです。初女さんは、“おむすび”、“食”で人に生きる力を与えることができるという実践を行われていました。感動した私は、何度も「ガイアシンフォニー」の自主上映会を開催しましたし、東北旅行の際には、初女さんの活動拠点である弘前の「森のイスキア」にも寄らせていただきました。初女さんは、ご不在でしたが・・・
 (2005年9月)
(2005年9月)
また、福岡で初女さんの「おむすび講習会」があったときも、ご縁あって参加することができ、初女さん直伝のおむすびの作り方を学びました。

(過去記事で使用した画像。末っ子ヤマトくんも幼いなぁ。懐かしいですね)
そんなことから、“食”に対して、意識して生活してきましたが、今回の「神様ごはん」で、あらためて感謝と思いを強くしました。
早速、「神様ごはん」著者が薦める味噌と醤油を調達しました。塩は、従来から使っている「キパワーソルト」。「神様ごはん」でも、この塩を薦めていました!ちょうど、カミさんが、1ヶ月前に、ぬか漬けを始めていましたし、米は、信州・安曇野の友人夫妻が作っているコシヒカリを愛用していますし、素材はバッチリ!!! 我が家の家計でできる範囲でね☆
高校生になったヤマトくんのお弁当にも、“塩おむすび”を入れてあげるよう、カミさんにお願いしました~。私も早起きして、たまには握るか(笑)
お米を洗って炊くのは、私の役割でしたが、味噌汁も時々作ることにしましたし、包丁も私が砥石で研ぐことにします。
食生活が、さらにワクワクしていきます☆