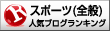7月のマジック教室は、マジックを披露する時のサーストンの三原則の解説から始まりました。①あらかじめマジックのストーリーを話さないこと。②同じマジックをその場で何度もやらないこと。③タネあかしをしないこと。
引き続き、マジックの楽しみ方の研修をしました。①「観察」見て楽しむ。謎を見つける楽しさ。②「習得」習って楽しむ。教わって、やってみて自分の体で感じる楽しさ。③「発表」試して楽しむ。人前で演技をして驚かせる楽しさ。④「創造」創って楽しむ。新しいマジックを考える楽しさ。
実習は、「類は友を呼ぶ」です。紙の表と裏に縦4列、横4列16分割された中には、友、男、女、良、悪などの文字が印刷されています。自分の思うように線に沿って自由に折り曲げていき、最後にハサミで回りをカットしていく16枚の用紙ができる。友を上にして一枚づつ捲っていくと16枚のすべてが「友」となっている作品。
発表は、ストローマジック、数字当てマジック、3本ロープが参加者から披露されました。最後に3枚カードを使用して真ん中のカードを引いてみると全く別のカードが出てきてビックリする作品を学びました。
(7月18日記)
引き続き、マジックの楽しみ方の研修をしました。①「観察」見て楽しむ。謎を見つける楽しさ。②「習得」習って楽しむ。教わって、やってみて自分の体で感じる楽しさ。③「発表」試して楽しむ。人前で演技をして驚かせる楽しさ。④「創造」創って楽しむ。新しいマジックを考える楽しさ。
実習は、「類は友を呼ぶ」です。紙の表と裏に縦4列、横4列16分割された中には、友、男、女、良、悪などの文字が印刷されています。自分の思うように線に沿って自由に折り曲げていき、最後にハサミで回りをカットしていく16枚の用紙ができる。友を上にして一枚づつ捲っていくと16枚のすべてが「友」となっている作品。
発表は、ストローマジック、数字当てマジック、3本ロープが参加者から披露されました。最後に3枚カードを使用して真ん中のカードを引いてみると全く別のカードが出てきてビックリする作品を学びました。
(7月18日記)