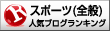駒形「どぜう」
◆200余年の歴史
「駒形どぜう」の創業は1801年。徳川11代将軍、家斉公の時代です。初代越後屋助七は武蔵国(現埼玉県北葛飾郡)の出身で、18歳の時に江戸に出て奉公した後、浅草駒形にめし屋を開きました。
当時から駒形は浅草寺にお参りする参詣ルートのメインストリートであり、また翌年の3月18日から浅草寺のご開帳が行われたこともあって、店は大勢のお客様で繁盛したと言います。
初代が始めたどぜう鍋・どぜう汁に加え、二代目助七がくじら鍋を売り出すなど、商売はその後も順調に続きました。嘉永元年(1848年)に出された当時のグルメガイド『江戸名物酒飯手引草』には、当店の名が記されております。
やがて時代は明治・大正・昭和と移り変わり、関東大震災、第二次世界大戦では店の全焼という被害を受けます。しかし多くのお客様のご支援と先代の努力もあって、江戸の味と建物は現在の六代目へと引き継がれております。
◆のれんの由来
仮名遣いでは「どじょう」。もともとは「どぢやう」もしくは「どじやう」と書くのが正しい表記です。それを「どぜう」としたのは初代越後屋助七の発案です。
文化3年(1806年)の江戸の大火によって店が類焼した際に、「どぢやう」の四文字では縁起が悪いと当時の有名な看板書き「撞木屋仙吉」に頼み込み、奇数文字の「どぜう」と書いてもらったのです。これが評判を呼んで店は繁盛。
江戸末期には他の店も真似て、看板を「どぜう」に書き換えたといいます。
200余年の歴史を刻む、店の大事なのれんです。
サイボクハム(埼玉県日高市)の温泉館「花鳥風月」に行きました。
先ず、和風レストラン「花鳥風月」で食事をしました。ハムやソーセージが付け出しで出ておりました。
ゆっくりと食事をした後は、天然温泉です。地下2000メートルから湧き出る温泉は温まりの湯、美肌の湯として人気があり、露天風呂もあります。
サイボクは自社ブランド豚肉のほか、隣接する工場で作られたハムやウインナーなどを直販しています。多くの人が買い物をしています。また新鮮野菜直売所「楽農ひろば」、屋内のバーベキューレストランなどゆっくりと一日楽しめる場所です。ひょうたん池の庭園もきれいです。
カフェテリアのソフトクリームがとても美味しいです。
「ヨシカミ」の洋食メニュー
浅草に行くと老舗洋食レストラン「ヨシカミ」で食事をすることが多くあります。
大正から昭和にかけて、日本一の娯楽の中心地として繁栄を際わめた東京浅草の中心、六区興行街の一つ裏通りに、昭和26年(1951年)12月末、オープンカウンター式の店として誕生。
“うますぎて申訳けないス!”との看板については、コックのマークと共に昭和35年(1960年)頃より、一つは「下町の酒落」として、今一つは調理人の「ここまで口に出したからにはそれなりの料理を」という戒めとしてキャッチフレーズに採用したとのこと。どのメニューも美味しい食べられます。
芸能人の俳優、女優、演芸人も来店しており、店内には多くのスターたちの色紙が飾られてあります。竹早高校の先輩である俳優の緒形拳さんの色紙もありました。
この日は、3人で入り、ビーフシチュー、ハンバーグ、ポークソティーを注文して、ライス、ポタージュスープ、生野菜サラダのセットとしました。皆で「美味しいね」と何回も繰り返して言葉が出てきます。美味しい料理を堪能しました。
洋風かき揚げ(松栄亭)
神田淡路町2丁目に洋食レストラン「松栄亭」があります。創業は明治40年(1907年)。
夏目漱石も通ったことのある松栄亭の看板メニューが「洋風かき揚げ」です。当時、漱石が何か美味しいものをと注文したところ、冷蔵庫の中に残った食材で作ったのが洋風かき揚げでした。
今も看板メニューの一つとして載っておりましたので、ランチに入ったときに注文をしてみました。
天麩羅のかき揚げは食べたことがありますが、洋風のかき揚げは初めてでした。
ナイフとフォークで切り分けていき食べますが、満腹感を味わいました。
お菓子のかりんとうなどを製造しているところです。
毎月第一金曜・土曜日には会社の敷地内で蔵出し販売の大売り出しをしています。多くの人が買い求めて来場しております。
製造販売をしているかりんとうが安価で買うことができる特別な日です。
かりんとうの好きな人には安く求めることができるので喜ばれています。
かりんとう以外にも和菓子やせんべいなどもたくさん置いてありますのでお菓子好きな人は多く買ってしまうようです。
午後からはその日に造られたかりんとうの販売もありますので、それを求めてくる人も多いようです。
甘党好きな人には安価で買うことができる蔵出し品を喜んで求めておりました。


東京カリントの蔵出し販売会 山積みされているかりんとう
天保元年創業「いせ源」
神田須田町1丁目界隈は、戦災を免れた数多くの建物の飲食店が現存しております。東京都選定歴史建造物に指定されております5店舗を紹介します。
①「いせ源本館」 創業天保元年(1830年)というから190年の歴史があります。都内唯一のあんこう料理専門店。江戸末期から続く秘伝の割り下でつくるあんこう鍋が絶品です。
②「神田まつや」 創業明治17年(1884年)の老舗江戸前蕎麦店。高度なそば打ち技術、香り、味、喉ごし、甘くて濃いめんつゆとお店の人のハイクオリティーなところが人気のあるところです。
③「ぼたん」 創業明治30年(1897年)の老舗鳥すきやき料理店。
④「竹邑(むら)」 創業昭和5年(1935年)木造入母屋造り3階建て。粟ぜんざい、揚げまんじゅうの伝統の甘味が楽しめる。この竹邑をこよなく贔屓にしていた池波正太郎は「むかしの東京の汁粉屋、その中で汁粉の味も店の人たちの応対もしっとりと落ちついている」と記述している。
⑤「藪蕎麦」 明治13年(1880年)創業。蕎麦御三家の一つ、老舗として暖簾を守り続けている。しかし平成25年(2013年))失火により焼失した。翌年の平成26年(2014年)に再建し鉄骨平屋建として再開した。そのために歴史建造物の指定は除かれた。
この近辺は散策して、食事をするには良い場所です。
はつ花のそばは、そば粉と地卵、そして自然薯だけで打った独自製法で仕上げています。はつ花の自然薯そばは茹で上げたそばの水分を十分に取り除き、乾いた状態で食べる独特な風味が特色です。
山かけそばを注文しました。温かいそばに自然薯の山かけをのせた逸品です。温かいつゆと、ふんわりとろとろの自然薯山かけとの相性は絶品でとても美味しかったです。
天丼と細切りざる饂飩御膳
東京ガーデンテラス紀尾井町3F にある「ささ樹」でランチをしました。
とても落ち着いた和食のレストランです。
カウンター席でゆっくりと食事ができました。
この日は天丼と細切りざる饂飩御膳を注文しました。
とても美味しかったです。
「五目焼そば」(赤坂四川飯店)
平河町の全国旅館会館6階の赤坂四川飯店でランチをしました。
ここのオーナーは陳建一氏であります。初めて日本に四川料理を広めた故陳建民(四川料理の神様)の長男です。
麻婆豆腐は陳建民氏が創作したもので愛好者が多いです。麻婆豆腐を注文している人が多いですが、自分は五目焼そばを頼みました。とても量が多くて食べ応えがあります。そして美味しかったです。
ここの赤坂四川飯店は、午前11時30分のオープン時間とともにすぐに満席になりますし、ランチ時は席が空くのを待っている人が多くおります。
それだけリピーターも多く来店客もたくさん来るお店です。
お店の前には順番を待っている人が多くおりました。店前にあるタッチパネルで人数と席を選ぶと順番待ちの番号票が出てきます。この日は15分ほどで入ることが出来て板長の前のカウンター席に着席。
梅特ランチ寿司を注文。まずサラダと茶碗蒸しがでてくる。握られた寿司はまず4貫と玉子焼きが並ばれておかれました。味噌汁も一緒に出てきます。トロマグロなどがとても美味しく食べることが出来ました。板長は食べる状況を見ながら、次の4貫とウニ、いくらなどの巻き物が3つ出されました。そして最後はデザートがでます。
群林堂の「豆大福」
やっぱり、音羽にある群林堂の「豆大福」は美味しいです。
いつも行列して順番を待っています。豆大福は一人15個までと制限されています。手作りで豆がたくさん入っていて中の餡と相性がいいです。
群林堂の向かい側には講談社のビルがあります。講談社を訪れる作家たちも群林堂の「豆大福」を土産に購入していく人が多いとのことです。
店内は背中合わせにカウンター席が14席。ほとんど切れ目なく来店客が食しています。人気メニューはカツカレーです。男性で注文する人はほとんどが大盛りカツカレーをリクエストしております。
カツカレーライスはとんかつと野菜サラダが乗っており、その上からカレーが盛られております。その色が黒色に近いようなものでビックリしますが、とても美味しく頂きました。
神保町界隈には、美味しい料理店が沢山ありますので、お店選びも絞り切れない時もあります。キッチン南海には旧店舗の時も行きました。新しく開店したお店も何回か行っております。このお店は常連客が多く、食べ終わった後、客は皆さん「ごちそうさまでした!」と言っております。厨房で料理を創っている人もホールスタッフも「有難うございます!」と言って応えております。