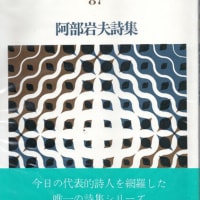クリークは小さくて、つたうるしの多い藪だらけの、勾配の急な峡谷から流れ出していたのだが、わたしはこのクリークの感じと水の動きが気に入って、流れに沿って少しのぼってみることにした。
それに名前もいいじゃないか。
トム・マーティン・クリーク。
人の名に因んでクリークに命名することはいいことだ。そういう川の流れに沿って行ってみるのは楽しいじゃないか。特徴は? クリークは何を知っているか? 如何なる自己形成を行ったか? そういうことを見るのだ。
リチャード・ブローティガン『アメリカの鱒釣り』 [1]
「ストーリーの如何というより、ただ、あのモンタナの川の色彩情景の鮮烈さと、いまは既にこの日本でも大衆化してしまっている(らしい)フライフィッシングの「キャスティング」の見事さには、かつて息子たちとともに目を見張ったものでした。」という言葉を添えて、古い友人がDVDを送ってきた。
モンタナとフライフィッシングという言葉から、「モンタナの風に吹かれて」という小説があったような気がして納戸の中の本棚を探したが見つからない。リチャード・ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』と『東京モンタナ急行』 [2] という2冊の本のタイトルと、やはりレッドフォードが監督した『モンタナの風に抱かれて』という映画のタイトルがごっちゃになっていたらしい。
【あらすじ】
モンタナ州ミズーラ。老いてなおブラッドフット川でフライ・ロッドを振るうノーマン・マクリーン(Arnold Richardson)の青年時代(1920年頃)の回顧として物語は描かれる。
長老派教会の牧師(Tom Skerritt)と敬虔な妻(Brenda Blethyn)の長男として生まれたノーマン(Craig Sheffer)にはポールという弟(Brad Pitt)がいる。厳格な家庭で、父は兄弟に教育を授けるだけでなくフライフィッシングも熱心に教える。「信仰と釣りは同じ」という環境で二人は成長する。
長じて、ノーマンは東部のダートマス大学で学業に専念するが、新聞記者としてモンタナに残ったポールは釣りの腕を磨いていく。
6年後、学業を終え、帰郷したノーマンはポールと釣りをするが、腕の差は歴然としていた。喧嘩で警察に留置されたポールを引き取りに行って、彼が留置場の常連であることや賭博場にも出入りする生活を送っていることを知る。
ダンスパーティーでジェシー・バーンズ(Emily Lloid)と知り合う。ジェシーの兄ニール(Stephen Shellen)とのトラブルなどがあるが、シカゴ大学から教授採用の通知が届いた日、ジェシーに求愛する。職も恋愛も順調なノーランはポールと一緒に祝杯をあげるが、ポールに誘われた賭博場「ロロ」で説得を試みるがポールは翌朝の釣りの約束だけしてロロに残る。
翌日の釣りで父とノーマンの見ている前でポールは巨大な鱒をヒットし、激流に流されながら取りこむ。二人はポールの姿に「完成された釣り」を認める。そして、これがポールの釣りの最後となって、ある日、彼は賭博の諍いから殴り殺され、路上に棄てられているのだった。
後年、最後の教会での説教で、父は手から逃げて行ってしまう者への愛を語る。それはポールへの尽きない愛の証だったのだとノーマンは回顧する。
この映画は釣りを通じて語られた家族の人生の話かもしれないが、釣りなしには成立しえない家族もあるのだという主張のようでもある。いや、美しい故郷の川の景色と静かな家族愛で綴られた一人の老人の回顧をレッドフォードが愛おしんでいるのか。
何よりもフィッシングである。それは幼い兄弟にメトロノームを使って父が教えるキャスティングの練習から始まる。1拍目:ラインを振り上げる(後方へ飛ばす)、2拍目:休止(ラインが後方に伸びきるのを待つ)、3拍目:ラインを前方に降り出す、4拍目:ラインが前方に伸びて着水する。4拍子のリズムがキャスティングの基本で、4拍目で着水させずに1拍目に戻って繰り返すシャドウ・キャスティングを繰り返しながらラインの長さ、方向を調整する。1拍の長さはラインの長さに依存する。画面では、子どもたちのシャドウ・キャスティングにはメトロノームのリズムはわずかに早すぎるようだった(そのような些細なことが気になるのは、それ以外の釣りのシーンが完璧だったからなのだけれども)。
父の厳しい作文指導から解放されたノーマンがロッドと魚籠をもって飛び出すとポール(7,8才くらい)もロッドを握って後を追いかける。1番目の釣りのシーンである。ポールの1投目、背後の木の枝にフライが引っ掛かる。たぶん外す役であろうノーマンが微妙に嫌な表情を見せる。そう、人の釣りというのはこんなふうに始まるのだ。広い野原のシャドウ・キャスティングと豊かな自然を流れる谷の違いをきつく印象づけられるのだ。釣りは、自然が見せる最初の拒否を乗り越えることから始まる。自然がいつも人間を歓迎してくれるなどというロマンチシズムは、おそらく都会人の幻想の中でしか育たない。
朝食のパンにサーディンを挟むかどうかで二人は人生でたった1度だけの兄弟喧嘩をする。そんな少年期を脱する頃、父と三人で行ったのが2度目の釣りのシーンである。ポールがシャドウ・キャスティングをしながら川を渡る後姿の美しさに彼の釣りの才能が暗示される。サイド・キャスティングするラインは川面すれすれに往復する。そのラインの流れのあまりの美しさに、これは釣り名人のスタントマンがブラッド・ピットの代わりをつとめているのではないかと疑ったほどのものである。もう1点、釣りに秀でる人間の特徴が描かれる。このシーンばかりではなく、ポールはいつもポイントを求めて離れていってしまう。ポイントの選定に厳しいのだ。この1シーンだけで、この映画が釣りに関しては超1級たりえているのだ。
ポールはすでに兄を越える腕になっているのだが、同サイズのレインボー・トラウトが1尾ずつ。二人のところに戻った父が魚籠から取り出したのは黒点が消えかかって赤褐色に輝くレインボーで、スティールヘッド(海から遠いモンタナではたぶんそんなことはないだろうが)と呼びたくなるような大物だった。三人のキャリアと腕を一瞬にして語るために、この3尾のトラウトが写るシーンがある。これは「腕とその釣果」についての常識的な想像力を示しているにすぎないが、じつはこの映画の主題である釣りを語るための繊細な仕掛けなのだ。
ダートマスでの6年の学業を終えてモンタナに帰ったノーマンは、ふたたびポールと川に行く。ノーマンが仕掛けを準備している間に、ポールは2尾立て続けにヒットし、二人の腕の差は歴然とし、あげくの果てにポールはノーマンにポイントのアドバイスを始める。ノーマンも石裏でヒットするが、自分の釣りよりも、大石のうえでシャドウ・キャスティングをするポールの姿に見入ってしまう。ノーマンは、キャリアはあるが普通の凡庸なフィッシャーマンで、ポールは釣りについては天才に近いことが、このあたりで明らかになってくる。どうあがいても、もう敵わないのだ。これが3回目の釣りのシーン。
4回目の釣りのシーン。ダンス・パーティーで知り合ったジェシー・バーンズの家族にジェシーの兄ニールと釣りの約束をさせられたノーマンはポールを誘う。朝からへべれけのニールは酒場の女連れで釣り場にやって来る。そんな二人を河原に残して兄弟は釣りをする。小さなレインボーを1尾キャッチして河原で寝そべっているノーマンに近寄って来たポールを見て「20匹も釣ったか」と声をかけると、ポールはニヤッと笑って魚籠を開けてみせる。魚籠はからっぽ。このシーンもまた、この映画の釣りのリアリティを保証している。そういうものなのだ、釣りは。名人に釣れなくて素人同然の釣り人にかかる、ということが起きることを自覚的な釣り人ならよく知っている。
「ニールはどうした」と聞くポールに、ノーマンは答える。
「奴は、釣りもモンタナも僕も嫌いなのさ」
ここには原初的な人間の観察と峻別がある。その人間の「人生の中でなすこと」と「生きる場所としての自然への態度」と「人間関係」。この3点でその人間のほとんどを描くことができるのではないか。ニールはモンタナを出てハリウッドで暮らし、モンタナの自然には関心がなく、故郷でも酒場の女を口説くことに夢中になっている。
最後の釣りは喜びとともにやってくる。
シカゴ大学から教授(instructor of English literature、正しくは専任講師)採用の手紙を受けとったノーマンはジェシーに求愛する。恋愛の成就をポールに打ち明け、二人で飲み明かそうとするがポールはノーマンを賭博場に誘う。ポールを咎めて家に帰るノーマンにポールは翌日の釣りを約束させる。
翌朝、家族揃った朝食の席で、ノーマンは教授採用のことを告げると、ポールは “real professor !”と叫び、家族は皆それを祝福する。そして父子3人は母親に見送られてブラックフット川へ出かける。
これが5回目で、そして最後の釣りのシーンとなる。クライマックスである。
川に着くと、父は「上流へ行く」と言い、ポールは対岸に渡っていく。ノーマンは降り立った河原の付近に位置取る。川と魚をどのように知っているか、キャリアと技量がそれぞれの釣り場選定に反映しているというのが、釣りという視点から見た受け取り方である。
しかし、父もポールもノーマンに場所を譲ったというのがもう一つの主題「家族への愛」に沿った解釈である。とくに、ポールが敢えて流れを横切ってノーマンの対岸に入るというのは、ポイント選定のためというよりはノーマンに場所を譲って、なおノーマンの近くで釣りをしたいという気持ちの現われと見るのが正しいだろう。
幼かった頃、兄の後を追っていた時分の「兄を慕う気持ち」が川面を漂っているようなシーンである。そう、私は受けとった。
ノーマンが河原を歩いて行くと首筋に虫が止まる。それはハッチ(羽化)したばかりのカワゲラの成虫である。その日その時刻にトラウトがどんなエサを補食しているのかを知ることは、フライフィッシングにとって決定的な要素である。たいていの場合、初めにキャッチしたトラウトの胃から捕食物を採取して調べるのが欠かせない手順の一つになっている。ノーマンは偶然に最適のフライ選択の情報を手にし、次々にヒットさせる。
対岸のポールのフライには何の反応もなく、苛立つポールは水を蹴るしぐさを見せる。兄を祝福し、譲る気づかいを見せていたポールも一人の釣り人に還元していくのだ。そして、我慢できずにどんなフライを使っているのか、兄に尋ね、「バンヤン」という名のフライを譲ってもらう。このあたりも釣り人の心の機微を捉えている。
東部から帰ったばかりの時、ポールのアドバイスにむっとするノーマンだが、ここではポールが意地を棄ててフライを譲ってもらう。釣り人の心はいつも「何としても釣りたい」という気持ちと「技量を持つ身のプライド」を両立させるべく激しく揺動しているのである。
ノーマンが場所換えで河岸の林を移動すると、木の下で読書をしている父が誇らしげに自慢の息子を見つめる。まったく釣れていないもう一人の息子ポールは、意を決して激流の対岸の大石脇の深みを狙おうとし、胸のポケットから煙草をとりだして帽子に入れる。
釣り人は、ヒットする魚のサイズとファイト、キャッチするまでのプロセスを想像する。その想像の正しさの程度こそが、キャリアに裏打ちされた技量の程度なのである。煙草を帽子に入れるのは、流れの激しい渓流でのヤマメ釣りやアユ釣りで、日本の釣り人もしばしば行なう動作である。その些細な動作の描写こそ、釣りを知悉する人々によって制作された良質な映画であることの証左である、と釣り好きの私は信ずるのである。
ついでに言えば、何度かフライを投入するポイントが写されるが、すべてが明らかにヒットを予感させるポイントなのもさすがと思わせる。餌の流れと集餌点、マス類の定位する川底の様子、そこから出てきて就餌するポイントを見きわめてフライを投入し、流すのである。その条件によって、ただ一点を狙い打ちするときも、フライを流して集餌ラインを狙う場合もある。
ポールの狙い通りに、対岸の深みから超大物が飛び出す。急流に流されながらのファイトは激しく、せっかくの煙草も帽子ごと流されてしまう。このシーン、一緒に見ていた妻は「ここで死ぬのね」と言い、私は「この程度の流れで死ぬようでは釣りの物語は完成しない」と、これは胸中で。
駆けつけた父と兄の前に、70cmを超えると思われるトラウトをぶら下げてポールが川から上がってくる。そのシーンの会話とノーマンの独白……
父「すごい魚だ」
ノーマン「信じられない」
その瞬間、僕ははっきりと感じた
完成されたものの美しさを
父「お前はすばらしい釣り人だ」
ポール「あと3年で魚の考え方が読める」
ノーマン「写真を」
そこはブラッドフット川の川辺ではなく――
弟は芸術品のように――
この世を超えた空間に立っていた
そして、川辺での3人の語らい。美しい夕焼けに輝くブラッドフット川の岸辺での愛し合う家族のひとときだが、ノーマンの独白はこう続く。
だが同時に僕は感じていた
人の世は芸術ではなく――
永遠の命をもたぬことを
ノーマンの予感したように、ポールは賭博の諍いで殺され、路地に棄てられる。常々、父が「ポールのフライフィッシングは美しい」と讃えていたそのキャスティングを生みだしていた右手を砕かれて。
それから何年か後、老いた父の牧師としての最後の説教を聞く妻、ノーマンとジェシー夫妻、そして二人の孫。説教に仮託してポールへの愛を語るシーンが回顧の物語の終わりである。
モンタナの自然の中で生きる家族にとって釣りは「趣味」ではない。しかし、人生そのものでもない。幼い兄弟が川べりで将来のことを語り合うシーンで、ポールがフライフィッシャーマンになると言い、ノーマンはそんな職業はないと答える。
モンタナで人生に向き合うための真摯な手段、人生に不可欠な手段としてフライフィッシングがある。それがなければ人生は完成しない。しかし、それがあれば人生が完成するとは保証されてはいない。いわば、人生に潜む不可能性を、ポールのフライフィッシングとその死は表象している。
多くの釣り人は、釣りを人生だ、と思いなすことはある。そしてまた、多くは思いなすだけで人生にすることはしない。いや、そういう不可能性を誰も引き受けようとはしない。「趣味」と規定して、ある地点から引き返すのである。それも「釣り」である。 〈クリークは何を知っているか? 如何なる自己形成を行ったか? そういうことを見るのだ。〉
青年よ汝よりさきに死をえらび婚姻色の一ぴきの鮎
塚本邦雄 [3]
渓谷はかなしかりけりこれからを流れるようなひとりとなろう
福島泰樹 [4]
死というものは、水だとか樹木だとかの、さりげない
姿勢のどこかに、ごく美しく仕舞われているものだとぼ
くはおもった。
ぼくはこのことを知りはじめてから、水や樹木と親し
むために、ひとりで魚を釣りにでかけた。ぼくはぼくの
影を終日水に写した。
伊藤桂一「一章」部分 [5]
さて、映画のクレジット・タイトルは、次の文で終わる。
No fish were killed or injured during the making of A RIVER RUNS THROUGH IT. The producers would like to point out that, although the Macleans kept their catch as was common earlier in this century, enlightened fishermen today endorse a “catch and release” policy to assume that this priceless resource swims free to fight another day. Good fishing
[1] リチャード・ブローティガン(藤木和子訳)『アメリカの鱒釣り』(晶文社、1975年) p. 37。
[2] リチャード・ブローティガン(藤木和子訳)『東京モンタナ急行』(晶文社、19年)。
[3] 『現代詩文庫501 塚本邦雄歌集』(思潮社 2007年)p.60。
[4] 福島泰樹「歌集 エチカ・一九六九年以降」『福島泰樹全歌集 第1巻』(河出書房新社 1999年)p. 98。
[5] 『日本現代詩文庫6 新編・伊藤桂一詩集』(土曜美術社出版販売 1999年)p. 13。