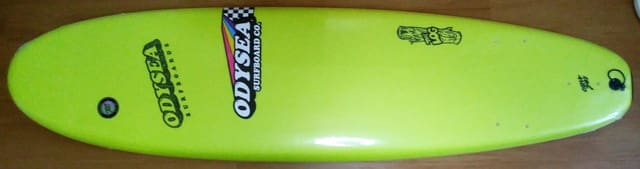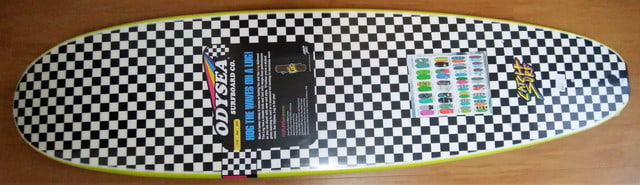日にちが経ってしまったけど、8月4日、東京トラック事業健康保険組合にて開催された労働基準協会ベーシックセミナー「非正規労働者の処遇に関する規制から保険制度まで~その基礎知識のすべてと今後~」、講師は法曹界の元キムタク、現三谷幸喜こと、岡崎教行弁護士。
事前に「外人女性とおつきあいしたら英語はうまくなると思いますか?」って質問してもいいですかと尋ねたら、きっぱりと断られたが、気を取り直して、お勉強の記録。
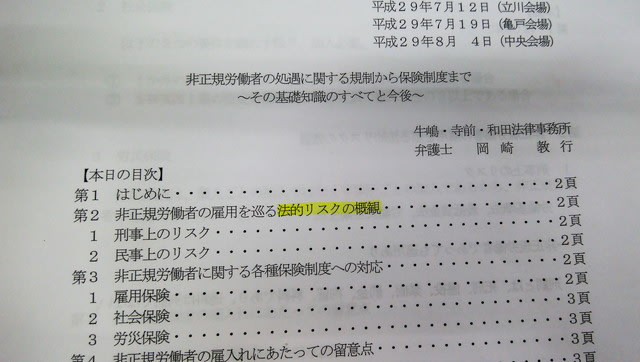
第4 非正規労働者の雇い入れに当たっての留意点
①募集にあたっての労働条件の明示気味 ←「文書で」なくてもよい
②労働契約締結時の労働条件の明示義務 ←「退職に関する事項」について、契約社員なのに「定年制 有」と記載してるケースが目に付くが、そもそも定年制の概念がない ←雇い止めが難しくなる(間違った期待を持たす)
パートタイム労働者についての特則 ←「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項」を見落としがち
③募集時と労働契約締結時とで労働条件が異なる場合の契約締結前の明示義務(H30.1.1施行)当初の明示と、❶異なる、❷範囲内で特定、❸明示していなかった、ものを明示
④パートタイム労働者に対する雇い入れの時の説明義務 ←説明
⑤雇い入れ時の健康診断
常時使用される労働者:期間の定めのない労働契約により使用されるもののほか、期間の定めがある労働契約により使用されるものであっても、1年以上使用されることが予定されている者も含まれる。 ←見落としがち
パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者は、健康診断を実施する必要がある。4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については健康診断を行うのが望ましい。
⑥就業規則の作成義務
・適用対象 ←10人未満でも作成しておいた方が良い ←就業規則がない場合、使用者と労働者の間には労働契約書しかない ←懲戒処分の根拠がない ←根拠のない懲戒処分は無効 ←紛争時(有事)の時に必要性がわかる ←遅い!
・従業員代表からの意見聴取 ←適用者の過半数でない ←従業員代表の選出手続きをしっかりやっていないところが多い
・試用期間を設けるか否か、例えば1年契約において最初の3か月を試用期間とするといった場合 ←よくあるが… ←入れるべきでない ←有期の場合、期の途中では解雇になる ←適正を見極めたいのなら最初の契約を3か月にすれば良い
第5 非正規労働者の処遇にあたっての留意点
〇育児休業・介護休業付与義務 ←10月1日以降改正有り ←就業規則の変更に留意
〇所定労働時間外労働に対する賃金の支払い ←割増しを払う必要ない ←しかし就業規則に「所定労働時間を超えて労働する場合、割増しを払う」となっている場合 ←支払う必要がある
〇無期転換ルール 法律上なにもしなければ今の労働条件と同じ ←しかしそのままだと「定年の定め」がない ←就業規則の変更は必要
第6 非正規労働者の雇い止めにあたっての留意点
〇解雇理由証明書 ←超重要! ←請求があった場合、そこに書く理由がその後の裁判などで大きな影響
(例 解雇理由が10個ある ⇒ 証明に2つしか書いていない ⇒ 裁判で10の理由を主張 ⇒ 後付けと判断される ⇒ とほほ
〇雇い止めをするにあたっての留意点 中小企業←証拠がない(注意の証拠) ←改善のための指導・教育(「彼に足りないのは何か」といった指導) ←思いが通じなかった時に「武器」になる ←退職勧奨する ←応じなかったら解雇(雇い止め) ※この流れの時間がない場合は1回だけ契約更新する(注意喚起した上で)
ところで…
法定労働時間外労働に対する地銀の支払いに関して、時間外労働が1か月60時間を超えた場合、60時間を超えた部分については割増率が50%になるが、現状は、中小企業については、適用されないことになっている。
これについて、岡崎先生は「平成31年4月1日から適用されることが決まっている」と説明されたが、そのことが盛り込まれた法律案は審議もされずに廃案となった。
時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金を盛り込んだ法律案とともに、次の臨時国会で法案提出される予定となっており、現在のところ、まだ決まっていない。
岡崎先生に指摘したら「ブログに書いといてよ」って言われたので、「岡崎さん、ちゃんと、ブログに書いといたよ」。