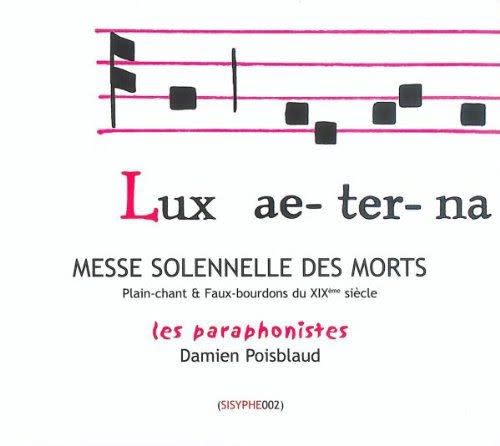随分前に、音楽雑誌(「レコード芸術」だったと思います)で
「好きな作曲家ランキング」みたいなものをやってました。
(この手のものは今でもよくやってるのかな?)
もう10年以上も前の"データ"ですが、
ブルックナーを好きと答えた人の9割が男性、との結果でした。
クラシックファンの"男女比"は半々くらいだとしても、
「あの指揮者がああだこうだ」とマニアックに語るのは
おそらく男性の方が多いのでは、と思います。
ですから、この手のアンケートに答えた"母集団"も
男性の割合がもともと多いと思いますが、それにしても9割とは・・・。
色々な名曲解説本にも書かれていることですが、
ブルックナーの作品は、他の作品と一線を画する「不思議な曲」だと思います。
前回も書きましたが、私自身は熱狂的なブルックナー信者ではありません。
それでも"演奏の好み"や"版"へのこだわりは多少あります。
(例えば交響曲第3番は初稿が好き、とか・・)
でも、「ブルックナーのどこがいいの?」と尋ねられても、
ブルックナーの交響曲の魅力を言葉で伝えることができません。
「同じような曲ばかり・・」とか「長くて退屈だ・・」という批判的な"感想"に対しても、
「その気持ちもわかる」と思ってしまうのです。
誰かに"魅力"を教えてもらうのではなく、自分で"魅力"を発見しない限り、
ブルックナーを好きにはならないのではないか、
と感じています。
だからこそ、その"魅力"を発見した人は、ブルックナーにのめり込み、
やがて「信者」へとなっていくのではないでしょうか。
一口にクラシックファンといっても、様々なジャンル、膨大な作品がありますので、
どの曲も多かれ少なかれ同じだとは思います。
でも、ほかの(好きな)曲ならば、その"魅力"を熱く語れるのに
ブルックナーだけは「自分で(その魅力を)掴み取るのだ!」
と言いたくなってしまいます。
本当に「不思議な曲」だと思います。
「好きな作曲家ランキング」みたいなものをやってました。
(この手のものは今でもよくやってるのかな?)
もう10年以上も前の"データ"ですが、
ブルックナーを好きと答えた人の9割が男性、との結果でした。
クラシックファンの"男女比"は半々くらいだとしても、
「あの指揮者がああだこうだ」とマニアックに語るのは
おそらく男性の方が多いのでは、と思います。
ですから、この手のアンケートに答えた"母集団"も
男性の割合がもともと多いと思いますが、それにしても9割とは・・・。
色々な名曲解説本にも書かれていることですが、
ブルックナーの作品は、他の作品と一線を画する「不思議な曲」だと思います。
前回も書きましたが、私自身は熱狂的なブルックナー信者ではありません。
それでも"演奏の好み"や"版"へのこだわりは多少あります。
(例えば交響曲第3番は初稿が好き、とか・・)
でも、「ブルックナーのどこがいいの?」と尋ねられても、
ブルックナーの交響曲の魅力を言葉で伝えることができません。
「同じような曲ばかり・・」とか「長くて退屈だ・・」という批判的な"感想"に対しても、
「その気持ちもわかる」と思ってしまうのです。
誰かに"魅力"を教えてもらうのではなく、自分で"魅力"を発見しない限り、
ブルックナーを好きにはならないのではないか、
と感じています。
だからこそ、その"魅力"を発見した人は、ブルックナーにのめり込み、
やがて「信者」へとなっていくのではないでしょうか。
一口にクラシックファンといっても、様々なジャンル、膨大な作品がありますので、
どの曲も多かれ少なかれ同じだとは思います。
でも、ほかの(好きな)曲ならば、その"魅力"を熱く語れるのに
ブルックナーだけは「自分で(その魅力を)掴み取るのだ!」
と言いたくなってしまいます。
本当に「不思議な曲」だと思います。