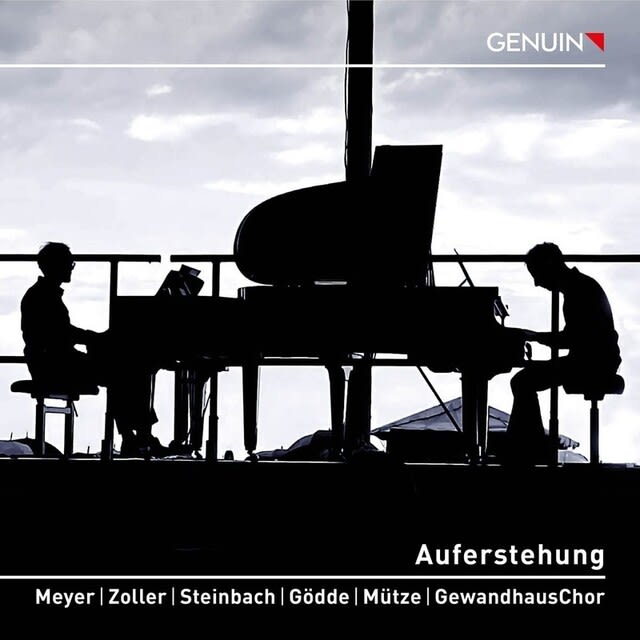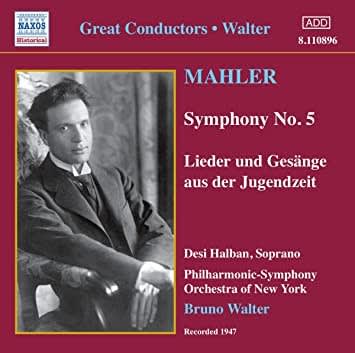ノルウェーのピアニスト、ヨアキム・カールが弾く『神的なもの ~ピアノ作品集~』
というCDを聴きました。

収録されている曲は以下の通りです。
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』
リスト:2つの伝説より第1曲『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『来たれ、異教徒の救い主よ』
メシアン:『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より第5曲『御子に注ぐ御子のまなざし』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ』
リスト:2つの伝説より第2曲『波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『来たり給え、創造主なる聖霊よ』
メシアン:『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より第14曲『天使たちのまなざし』
フランク:前奏曲、コラールとフーガ
ノルウェー、ロフォーテン諸島のスタムスンド教会で録音されています。
コラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』は
塚谷水無子さんの「ブゾーニ編:ゴルトベルク変奏曲」の解説によれば
「ヨーロッパの人々に最も愛されている」コラール前奏曲だそうです。
私もとても好きな曲です。
アンドレイ・タルコフスキーの映画「惑星ソラリス」で流れるのがこの曲ですが
未来?を描いたSF映画の冒頭にバッハを用いた段階でこの映画の"評価"は決まった気がします。
『目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ』は曲名は知らなくても
一度はどこかで耳にしたことのある有名な曲ですね。
リストは「超絶技巧練習曲」や「タンホイザー序曲」(ピアノ版編曲)など
派手で煌びやかな印象が強いのですが、1861年にローマに移住して以降
キリスト教に題材を求めた作品が増えていきます。
どちらも二人の聖人(フランチェスコ)にまつわる逸話を基にした曲ですが
『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』は小鳥たちの囀りを描写するトレモロが印象的で
神秘的で静かな風景です。
『波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ』は荒れ狂う海をマントを広げて渡る力強い情景が描かれ
壮大なクライマックスを迎えます。
オリヴィエ・メシアンは神学者でもあったそうで、やはりキリスト教的な主題の作品も多いです。
パリのサントトリニテ教会で60年にわたりオルガン奏者を務めました。
『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』は2時間を超える大作で"音楽語法"もかなり複雑です。
第1曲「神のまなざし」に登場する<神の主題>
第2曲「星のまなざし」に登場する<星と十字架の主題>などが他の楽曲にも現れます。
殆ど現代音楽のような曲ですが「共感覚」の持ち主で一音一音に異なる「色」を感じるメシアンには
違う情景が見えていたのかもしれません。
メシアンの曲といえば、以前に聖イグナチオ教会(カトリック麹町教会)で
「キリストの昇天」の第3楽章「キリストの栄光を自らのものとした魂の歓喜の高まり」を
聴いたことがあります。
コンサートが終わった後のアンコール?だったのですが
突如として鳴り響いたパイプオルガンに度肝を抜かれました。
教会のステンドグラスは、聖書の物語を分かりやすく伝える意味もありますが
教会で歌われる、演奏される音楽もまた同様です。
教会のパイプオルガンで聴くメシアンは特別なものでした。
普段はこのような「企画物」はあまり聴かない(手に取らない)のですが
バッハのコラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』で始まり
フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』で幕を閉じるという構成に惹かれてしまいました。
他の曲はどれも「標題音楽」ですが、フランクのみ「絶対音楽」です。
にもかわらず「神的なもの」と題するCDの最後に(バッハ、リスト、メシアンを経て)フランクを選ぶとは。
『前奏曲、コラールとフーガ』については
以前にも書きましたがホルヘ・ボレットの演奏が私にとっての究極の1枚です。
そのボレットには及ばないまでも、ヨアキム・カールの演奏も余計な飾りを排した
静かで美しい、この「神的なもの」の最後を飾るに相応しい響きです。
因みに本CDの原題はラテン語の「numinosum」で「神々しい」というような意味です。
心理学者ユングの自伝「思い出・夢・思想」に出てくる言葉からインスピレーションを受けて
選曲したそうです。
というCDを聴きました。

収録されている曲は以下の通りです。
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』
リスト:2つの伝説より第1曲『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『来たれ、異教徒の救い主よ』
メシアン:『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より第5曲『御子に注ぐ御子のまなざし』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ』
リスト:2つの伝説より第2曲『波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ』
バッハ/ブゾーニ編:コラール前奏曲『来たり給え、創造主なる聖霊よ』
メシアン:『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より第14曲『天使たちのまなざし』
フランク:前奏曲、コラールとフーガ
ノルウェー、ロフォーテン諸島のスタムスンド教会で録音されています。
コラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』は
塚谷水無子さんの「ブゾーニ編:ゴルトベルク変奏曲」の解説によれば
「ヨーロッパの人々に最も愛されている」コラール前奏曲だそうです。
私もとても好きな曲です。
アンドレイ・タルコフスキーの映画「惑星ソラリス」で流れるのがこの曲ですが
未来?を描いたSF映画の冒頭にバッハを用いた段階でこの映画の"評価"は決まった気がします。
『目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ』は曲名は知らなくても
一度はどこかで耳にしたことのある有名な曲ですね。
リストは「超絶技巧練習曲」や「タンホイザー序曲」(ピアノ版編曲)など
派手で煌びやかな印象が強いのですが、1861年にローマに移住して以降
キリスト教に題材を求めた作品が増えていきます。
どちらも二人の聖人(フランチェスコ)にまつわる逸話を基にした曲ですが
『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』は小鳥たちの囀りを描写するトレモロが印象的で
神秘的で静かな風景です。
『波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ』は荒れ狂う海をマントを広げて渡る力強い情景が描かれ
壮大なクライマックスを迎えます。
オリヴィエ・メシアンは神学者でもあったそうで、やはりキリスト教的な主題の作品も多いです。
パリのサントトリニテ教会で60年にわたりオルガン奏者を務めました。
『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』は2時間を超える大作で"音楽語法"もかなり複雑です。
第1曲「神のまなざし」に登場する<神の主題>
第2曲「星のまなざし」に登場する<星と十字架の主題>などが他の楽曲にも現れます。
殆ど現代音楽のような曲ですが「共感覚」の持ち主で一音一音に異なる「色」を感じるメシアンには
違う情景が見えていたのかもしれません。
メシアンの曲といえば、以前に聖イグナチオ教会(カトリック麹町教会)で
「キリストの昇天」の第3楽章「キリストの栄光を自らのものとした魂の歓喜の高まり」を
聴いたことがあります。
コンサートが終わった後のアンコール?だったのですが
突如として鳴り響いたパイプオルガンに度肝を抜かれました。
教会のステンドグラスは、聖書の物語を分かりやすく伝える意味もありますが
教会で歌われる、演奏される音楽もまた同様です。
教会のパイプオルガンで聴くメシアンは特別なものでした。
普段はこのような「企画物」はあまり聴かない(手に取らない)のですが
バッハのコラール前奏曲『われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ』で始まり
フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』で幕を閉じるという構成に惹かれてしまいました。
他の曲はどれも「標題音楽」ですが、フランクのみ「絶対音楽」です。
にもかわらず「神的なもの」と題するCDの最後に(バッハ、リスト、メシアンを経て)フランクを選ぶとは。
『前奏曲、コラールとフーガ』については
以前にも書きましたがホルヘ・ボレットの演奏が私にとっての究極の1枚です。
そのボレットには及ばないまでも、ヨアキム・カールの演奏も余計な飾りを排した
静かで美しい、この「神的なもの」の最後を飾るに相応しい響きです。
因みに本CDの原題はラテン語の「numinosum」で「神々しい」というような意味です。
心理学者ユングの自伝「思い出・夢・思想」に出てくる言葉からインスピレーションを受けて
選曲したそうです。