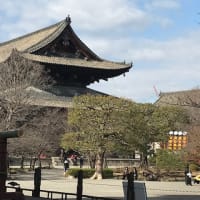霜降り月というが、旧暦の異名 いみょう また異称に ねづき 子の月でもある。
建子月という。天空でくるりと回って見える北斗の観察は面白い。
建す(おざす)の意味 - goo国語辞書https://dictionary.goo.ne.jp › 国語辞書 › 品詞 › 動詞
お‐ざ・す〔を‐〕【▽建す】 の解説
[動サ四]《「尾指す」の意》北斗七星の柄の先が十二支のいずれかの方向を指す。陰暦の1月には寅 (とら) の方向を、2月には卯 (う) の方向をと、順に1年の間に十二支の方向を指す。
「北斗も―・す丑三つの空ものすごく」〈浄・井筒業平〉
https://www.tamarokuto.or.jp/blog/rokuto-report/2020/05/03/northern-sky01/
北の空の星の動き(1)北の大時計
>北斗七星を毎日同じ時刻に観察していると、1年間で同じように一周しているように見えます。例えば一年後の同時刻に北斗七星を探せば、ほぼ同じ位置でみつけることができるのです。
今度は1年間で360度ですから、北極星を中心に、北斗七星が反時計回りに90度(4分の1周)回ったら、3か月(4分の1年)経った、ということになります。つまり、1か月で30度変化するということ。
こちらはさしずめ、「北の大カレンダー」でしょうか。
https://hyogen.info/word/9533260
>建子月【けんしげつ】とは
陰暦11月の異名。子の月(ねのつき)。古代中国では冬至を含む月に、北斗七星の取っ手の先が真下(北の方角)を指すため、この月を十二支の最初である「建子月(けんしげつ)」とした。以降、12月は「建丑月(けんちゅうげつ)」、翌1月は「建寅月(けんいんげつ)」と呼ばれた。「建」は、「建す(おざす)」をあらわし、北斗七星の取っ手の先が十二支のいずれかの方向を指すことを意味する。
・建寅月(けんいんげつ) → 陰暦1月
・建卯月(けんぼうげつ) → 陰暦2月
・建辰月(けんしんげつ) → 陰暦3月
・建巳月(けんしげつ) → 陰暦4月
・建午月(けんごげつ) → 陰暦5月
・建未月(けんびげつ) → 陰暦6月
・建申月(けんしんげつ) → 陰暦7月
・建酉月(けんゆうげつ) → 陰暦8月
・建戌月(けんじゅつげつ) → 陰暦9月
・建亥月(けんがいげつ) → 陰暦10月
・建子月(けんしげつ) → 陰暦11月
・建丑月(けんちゅうげつ) → 陰暦12月