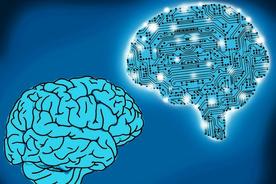
wsj日本版から
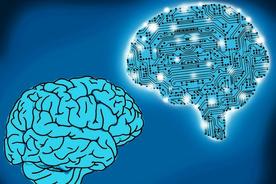
IBMのコンピューター「ディープ・ブルー」が1997年にチェスの世界チャンピオンだったガルリ・カスパロフ氏に勝利したとき、チェスは論理のゲームにすぎない、だからディープ・ブルーの勝利は大きな意味のある成果とも、驚くべきこととも言えない、と識者らは論評した。比喩やだじゃれ、ユーモアなど人間の言語が持つ機微を習得する芸当はコンピューターには到底無理と思われていた。昨年、IBMが生み出した新たなコンピューター「ワトソン」はこうした課題を克服し、米人気クイズ番組「ジョパディ!」で勝利を収めた。人工知能が人間の能力と競い合う可能性についてそろそろ真剣に考える時期なのではないだろうか。
発明家で未来学者のレイ・カーツワイル氏は新著「How to Create a Mind(知性の作り方)」の中でこの意見に賛成している。カーツワイル氏は人間の脳を完全に解明して、そっくりの人工知能を作れる時代は多くの人の予想よりはるかに近いと考えている。カーツワイル氏はこれまで技術の進歩を見事に言い当ててきた。したがって、カーツワイル氏の意見は傾聴に値する。
「人間の脳はあまりにも入り組んでいるため、理論的に理解するのはほぼ不可能」という考え方が流行っている。例えば、マイクロソフトの共同創業者のポール・アレン氏は最近の記事で、IBMのワトソンとカーツワイル氏の両方を批判した。ワトソンの知識は不安定で、特定の領域に限定されており、カーツワイル氏は脳のあらゆる構造が「特定の物事を行うように進化によって精密に形成されてきた」ということを理解していない、というのがアレン氏の主張だ。アレン氏「複雑性というブレーキ」があるため、脳の働きを理解して複製を作ろうとしても、その試みは必然的に制限されると断定している。
カーツワイル氏が新著の中で示した答えには説得力がある。まず第1に、脳は比較的小さく単純な情報量で構成されている。脳のゲノムは2500万バイトだ。脳の複雑性は秩序だった成長と精巧さに由来する。第2に、脳には大量の重複情報が含まれている。特定の基本パターン認識は脳のさまざまな領域でおそらく3億回繰り返されている。第3に、ハーバード大学医学大学院のバン・ウェディーン氏が同僚とともに最近の研究で発見したように、脳の大部分ではマンハッタンの街を走る通りとエレベーターのように、神経線維の束が横に並んでいて、その束がそれぞれ垂直につながっている。
その上、人工知能システムの設計は人間の脳が発達してきた方法と一致している。カーツワイル氏は進化的アルゴリズム(手の込んだ試行錯誤、とでも言おう)を使って、今、私たちが当たり前に思っている音声認識ソフトを自ら開発した。
カーツワイル氏は人間の脳を、認識パターンがどのように発展するかを予想することで機能する機械の集合体と考えており、この点でイノベーターから脳神経科学者に転向したジェフ・ホーキンス氏と一致している(ホーキンス氏は携帯情報端末「パームパイロット」を発明した人物だ)。われわれがある視覚イメージの断片を組み立てるとき、情報は基本的なパターン認識機能から取り入れられ、(神経線維のグリッドを通じて)高次の抽象認識に統合される。一方でまた、情報は抽象認識からパターン認識に下り、視覚イメージに欠けている部分や変化した部分についてパターンを予測することもある。予測がうまくいかないときは「驚き」として認識され、(グリッド状の神経線維を通じて)脳の高次の階層に運ばれ、意識的に分析される。
この構図がおおむね正しければ、脳の複製は不可能ではない。技術者はかつて、回路の幅を5ミクロンにしようとしていたころは、1ミクロンにすることなどできないとばかにされていたが、今では0.022ミクロンを実現した。「人間の脳の構造を調べるプロジェクトは同じように進歩している」のだから、悲観的主義者は正しくない、とカーツワイル氏は言う。
カーツワイル氏はさらに、脳は基本的にリニアな(線形の)組織で、連続して情報を処理していると主張している。だから、われわれは技術の進歩に生じる非線形の流行を把握するのが非常に難しいと感じるのかもしれない。ハードウエアとソフトウエアの両方が急激な変化を遂げるなかで、今後数十年の間に人間の脳がシリコン上に再現されることは絶対にないと言い張るのは、ばかげているし、賢明なことではない。
記者: Matt Ridley
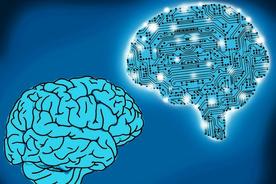
IBMのコンピューター「ディープ・ブルー」が1997年にチェスの世界チャンピオンだったガルリ・カスパロフ氏に勝利したとき、チェスは論理のゲームにすぎない、だからディープ・ブルーの勝利は大きな意味のある成果とも、驚くべきこととも言えない、と識者らは論評した。比喩やだじゃれ、ユーモアなど人間の言語が持つ機微を習得する芸当はコンピューターには到底無理と思われていた。昨年、IBMが生み出した新たなコンピューター「ワトソン」はこうした課題を克服し、米人気クイズ番組「ジョパディ!」で勝利を収めた。人工知能が人間の能力と競い合う可能性についてそろそろ真剣に考える時期なのではないだろうか。
発明家で未来学者のレイ・カーツワイル氏は新著「How to Create a Mind(知性の作り方)」の中でこの意見に賛成している。カーツワイル氏は人間の脳を完全に解明して、そっくりの人工知能を作れる時代は多くの人の予想よりはるかに近いと考えている。カーツワイル氏はこれまで技術の進歩を見事に言い当ててきた。したがって、カーツワイル氏の意見は傾聴に値する。
「人間の脳はあまりにも入り組んでいるため、理論的に理解するのはほぼ不可能」という考え方が流行っている。例えば、マイクロソフトの共同創業者のポール・アレン氏は最近の記事で、IBMのワトソンとカーツワイル氏の両方を批判した。ワトソンの知識は不安定で、特定の領域に限定されており、カーツワイル氏は脳のあらゆる構造が「特定の物事を行うように進化によって精密に形成されてきた」ということを理解していない、というのがアレン氏の主張だ。アレン氏「複雑性というブレーキ」があるため、脳の働きを理解して複製を作ろうとしても、その試みは必然的に制限されると断定している。
カーツワイル氏が新著の中で示した答えには説得力がある。まず第1に、脳は比較的小さく単純な情報量で構成されている。脳のゲノムは2500万バイトだ。脳の複雑性は秩序だった成長と精巧さに由来する。第2に、脳には大量の重複情報が含まれている。特定の基本パターン認識は脳のさまざまな領域でおそらく3億回繰り返されている。第3に、ハーバード大学医学大学院のバン・ウェディーン氏が同僚とともに最近の研究で発見したように、脳の大部分ではマンハッタンの街を走る通りとエレベーターのように、神経線維の束が横に並んでいて、その束がそれぞれ垂直につながっている。
その上、人工知能システムの設計は人間の脳が発達してきた方法と一致している。カーツワイル氏は進化的アルゴリズム(手の込んだ試行錯誤、とでも言おう)を使って、今、私たちが当たり前に思っている音声認識ソフトを自ら開発した。
カーツワイル氏は人間の脳を、認識パターンがどのように発展するかを予想することで機能する機械の集合体と考えており、この点でイノベーターから脳神経科学者に転向したジェフ・ホーキンス氏と一致している(ホーキンス氏は携帯情報端末「パームパイロット」を発明した人物だ)。われわれがある視覚イメージの断片を組み立てるとき、情報は基本的なパターン認識機能から取り入れられ、(神経線維のグリッドを通じて)高次の抽象認識に統合される。一方でまた、情報は抽象認識からパターン認識に下り、視覚イメージに欠けている部分や変化した部分についてパターンを予測することもある。予測がうまくいかないときは「驚き」として認識され、(グリッド状の神経線維を通じて)脳の高次の階層に運ばれ、意識的に分析される。
この構図がおおむね正しければ、脳の複製は不可能ではない。技術者はかつて、回路の幅を5ミクロンにしようとしていたころは、1ミクロンにすることなどできないとばかにされていたが、今では0.022ミクロンを実現した。「人間の脳の構造を調べるプロジェクトは同じように進歩している」のだから、悲観的主義者は正しくない、とカーツワイル氏は言う。
カーツワイル氏はさらに、脳は基本的にリニアな(線形の)組織で、連続して情報を処理していると主張している。だから、われわれは技術の進歩に生じる非線形の流行を把握するのが非常に難しいと感じるのかもしれない。ハードウエアとソフトウエアの両方が急激な変化を遂げるなかで、今後数十年の間に人間の脳がシリコン上に再現されることは絶対にないと言い張るのは、ばかげているし、賢明なことではない。
記者: Matt Ridley




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます