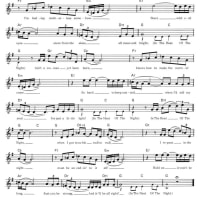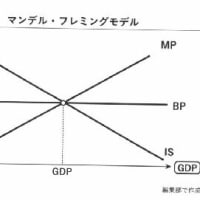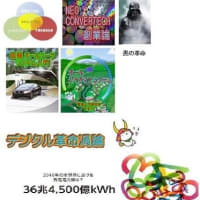【資源王国を実現する構想】
過日、次のように日本を資源王国にする構想の発案をブログ掲載した。そこで今夜はその
構想をもう少し具体的に考察してみたい。
例えば、巻頭のラン藻類などの微生物を表層ディスプレイ技術など利用し、バ
イオリアクター設備に海水を引き込み循環させながら光合成を行い、有用金属
(物質)を吸着→濃縮・回収→バイオマス燃料(バイオプラスチック原料)→
濾過・回収→バイオマス発電→有用金属(物質)回収行うことが可能となれば、
エネルギー・資源枯渇問題を解消でき、併せて地球温暖化ガス排出量を削減で
きることになる。20年後世界一の持続可能社会形成を実現した資源大国はと
問われ時、それは日本!と誰もが答える状況になっているだろう。
『成熟に向かう新弥生時代(2)』
この日のブログでは、理化学研究所の研究グループがラン藻に微生物の遺伝子を導
入し、光合成だけで高効率なバイオプラスチックの生産の研究開発例を取り上げた
が、筑波大・渡辺信教授らのグループが、2012年より耕作放棄地2ヘクタールを活
用した屋外大量培養の実験に着手→つくば市内の耕作放棄地で、実規模レベルでの
開放系運輸燃料生産システムを建設、ボトリオコッカスとオーランチオキトリウム
2種類の藻類を複合した実証実験、つまり、有機物を吸収し、石油系の炭化水素を
作る「オーランチオキトリウム」に代表される藻類バイオマスを活用し、仙台市と
筑波大、東北大が取り組む次世代エネルギーの共同研究。研究施設を下水処理施設
「南蒲生浄化センター」 (宮城野区)に整備。有機物が豊富な下水をサンプルにし
た培養実験も筑波大で始めたというもの。
なお、オーランチオキトリウムは有機物を取り込むことによって増殖するという特
性を持ち、ボトリオコッカスは、低濃度の有機廃水で増殖が促進される。これら
の特性を活かし、下水処理の一次処理水にオーランチオキトリウムを投入、二次処
理水をボトリオコッカスの培養に活用させ、下水処理プロセスへ統合させる研究開
発を行うが、この統合化により、
(1)廃棄物を使用することによるオイル生産コストの抑制
(2)二次処理水(窒素とリンの残渣)をボトリオコッカスの培養に活かすことに
よる水域の富栄養化の防止
(3)オイル採集後の藻類残渣物の動物飼料やメタン発酵への利用の実現
ここでは、オーランチオキトリウムとボトリオコッカスの2種類の藻類を使用して
いるが、細胞表層工学で遺伝子を改変したアーミング酵母や大型藻類(macroalgae)
と微細藻類(microalgae)の海藻類、放線菌など細菌を使って、(1)オイル採集
意外にも、(2)バイオエタノール、(3)バイオプラスチック、(4)水素ガス
などの生物工学変換追加し組み込むことも視野に入れている。さらに、(3)のオ
イル採集後の類残渣物の中の有用物質の回収プロセスを追加することで、いわゆる、
下水処理をエネルギー資源化機能以外の"都市鉱山"機能を加えることを構想してい
る。そして臨海部の下水処理システムに海水を混合の後に有価物質の回収、あるい
は、下水発生するエネルギーを海水資源化システムの動力として利用することも考
えに入れる。なお、この構想をここでは、"ハイブリッド型海水資源化システム"と
仮に呼ぶことにする。その意味では、海洋鉱山と都市鉱山の結合であり、微生物工
学と上下水処理技術と電気化学工学との結合であり、究極の"もったいない工学"で
あり、未来志向型インフラ整備事業となるだけでなく、このシステムあるいは産業
プラットフォーム事業の世界展開が約束されている。
『成熟に向かう新弥生時代(2)』では、マンガン酸化細菌と基質酸化細菌をつか
って、レアメタルをバイオソープション(金属吸着・吸収)適用技術で回収する手
法を考察したが、今夜は、パイロコッカス・フリオサス(Pyrococcus furiosus)由
来のWtpA遺伝子を細胞表層に発現する組換え微生物を利用してタングステンを効率
良く回収することで、タングステンを効率良く回収するトヨタ自動車の「特開2013-
252085|組換え酵母、当該組換え酵母を用いたタングステン回収方法」を考察して
みる(下図参照)。

以上から、実験段階から実用段階への以降には、アーミング酵母の生産コスト(回収コスト)
や生産効率あるいはシステムの堅牢性などが重要なポイントになることが伺える。次に、
リチウムの回収を以下の事例から考察してみる。
日本原子力研究開発機構の星野毅らの研究グループの、イオン伝導体をリチウム分
離膜として用い、リチウム分離過程で電気等の外部エネルギーを消費せず、電気を
発生しながらリチウムを分離する革新的な元素分離技術-核融合炉燃料製造やリチ
ウムイオン電池等の原料のリチウム資源を海水から、逆浸透膜と電気透析の2つの
技術を使って回収する技術(「特開2012-055881 リチウムの回収方法およびリチウ
ムの回収装置」)ついて考察する。この方法は、海水とリチウムを含まない回収溶
液間は、イオン伝導体をリチウム分離膜として用いて隔離するだけでなく、その間
にリチウム濃度差を生じさせることにより、海水中のリチウムが自然に回収溶液へ
選択的に移動する分離原理を発案し、さらにリチウムの移動と同時に発生する電子
を電極により捕獲することで、電気を発生しながらリチウムを回収できるため資源
回収には必ず外部からのエネルギーを必要とするが、リチウム分離過程で電気等の
外部エネルギー消費を要せず、従来の塩湖からのリチウム資源回収技術と比べ、省
スペース、短時間、さらに、電気を新たに発生することで資源回収のゼロ・エミッ
ション化を目指すことができる革新的な技術だという(下図参照)。実験段階での
様々な裏付けデータが揃い、このシステムが実用性を担保できれば、あるいは派生
技術などで飛躍展開できれば、膨大な規模と予測されている蓄電池市場の中核技術
を担うことになると考えられる。
セラミックスは様々な結晶構造で構成されているが中でも、NASICON型、ガーネッ
ト型、ペロブスカイト型等の結晶構造は、イオン伝導性を有することで知られてい
る。ここでは、リチウム(Li)、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)、ゲルマニウム(Ge)
、ケイ素(Si)、リン(P)、酸素(O)を含むNASICON型セラミックスをリチウム分離膜
として使用。

モーグルの上村愛子、脱原発の細川護熙 二人とも残念でしたが、明日に繋がるこ
とを信じていますよ。