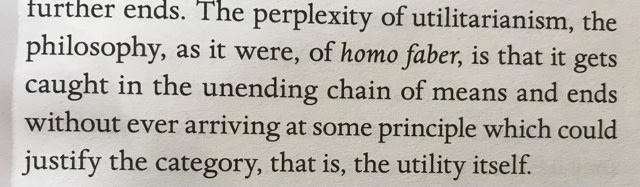誤解がないように断っておけば、必要がなくなれば自由というわけでもないし、自由なら必要事から全く解放されるというわけでもない。この複雑さは、アーレントの記述の揺れ動きからも感じられる。
そしておそらく、アーレントの記述のパラドキシカルな側面は、歴史において必然(必要)と自由が一致するというヘーゲル的なパースペクティヴにおいて極まるだろう。だが、ここでも彼女は気づいているかもしれないが重大な過ちを犯しているように思われる。それは、理性によって“眺められた”歴史なのだ。(かといって、彼女は経験への配慮を怠っているというわけではない)
例えば、私は先に昼と夜の交替という自然的ないし天体的な回転を例に挙げた。(人間の動物としての生死の循環でもいい。そのような感性的な人間も有機体から無機物へと回帰していく)
革命という用語の語源的な意味に、既に天体の回転運動から拝借されたという経緯がある。おそらく、近代以前の人間にとっての天体の回転運動や自然の循環性は、人間の運命や偶然性を司るものだったはずだ。それが、ある歴史的な展望の下でかつての偶然と必然が一致する。(そこには、不可抗力性 irresistibility の概念も付け加わる)
革命は、一度起きてしまえば、それは歴史の必然に変わる。そう言えばいいのだろうか? かといって、理性の眼によって眺められるのは、革命(回転運動)の経験(新しい経験)とは言い難い。それは、起きた“後に”そのような偶然と必然(必要)の一致に変わってしまっているということだろう。
あるいは、(周期的であり循環的な、そして無際限の)自然や天体の運動が歴史化される時に何が生じているのだろうか? 要するに、感性において経験される運命や偶然性と、それらが後に理性によって眺められる歴史的な視座への一致と必然性。
それが、自由を巡る政治的なパラドックスとして彼女の前には現れているということだろう。あるいは、自由がもし最もラディカルな政治的実践に結びつくなら、人間はそれを再び歴史的なパースペクティヴにおいて構成し直すという営みが残されているのかもしれない。
こう述べておくのは適切だろう。ウイルスは変異 permutation は起こすが、革命 revolution は起こさないと。
■コンパッションの力
私はアーレントの“理性の側からの”ルソーの読みについては、間違っていると何度か指摘した。だが、感性の共感 compassion の力を考慮したルソー読解は彼女の天才が示されている。また、その力点の相違に“別の”(あるいは“新しい”)共同性の問題を見取ることはできるかもしれない。
アガンベンの『いと高き貧しさ』は、いわば“神学的な革命の前夜”を物語っているとも読めなくもない。
《理性は人間を利己的にする。それは自然が「不幸な受難者に共鳴するのを」妨げる。》(ibid., p.120)
そして、そのような“理性的共同性”からは追放されることに、アガンベンは新たな政治的な身振りを見取っていた。
つまり、この社会が理性により結託しているなら、それは須く我々を欺く詭弁としてあり、そのような精神は徳性を抹消しようと努めるだろう。そのような社会は、悪徳として栄える以外ない。
《苦悩する能力である情熱 passion と、他人とともに苦悩する同情 compassion が終った地点から、悪徳がはじまった。利己主義は一種の「自然的な」堕落であった。》(ibid., p.121)
こういってよければ、アガンベン、アーレント、ルソー、そしてヴェイユが共鳴するような地平がある。だが、それはこの世界からは隠されているままに留まるだろう。
ここで私がアガンベンの著作を評価したのは、それがアーレントが扱いきれなかったようなキリスト教思想の核心問題——それは、“新しい自由”の重点がキリスト教的共同性の創始によって、vita activa〔活動的生〕からvita contemplativa〔観照的生〕の方へと変転することも含むだろうし、アガンベンの書記論にもその影響が顕著である——を描いているからである。そしてまた、シモーヌ・ヴェイユにおいては必然性の概念が、パラドキシカルな神のヴェールとして既に現れていた。
つまり、自由(それはギリシャのポリスにおいては公的であり、政治的な領域への参加と不可分である)と必然(それはキリスト教的な共同性への扉として、あるいは“神への服従”の印として、公的な領域からは隠されている)は、アーレントとアガンベンを結びつつも切り離すのような、公的領域と私的領域の間にある深淵のパラドックスとしてあることが窺えるだろう。その両方に引き裂かれた魂=心には、パッション〔情熱=受苦〕がある。
そして、キリスト教的政治性(それを“新しい自由”と呼ぶことに我々は異論はない)とはある実行性を保持しながらも、決して公にはならないという性格を持っている。ここでは、それを政治的な“行為のパラドックス”と名指すに留める。
(キリスト教的な“愛の”政治性—それはオイコノミアと統治性の概念へと変形され、“内面の自由”〔記憶〕へと救済-保存される—とは別の、革命が新たな支配関係を必要としてしまうというパラドックスについては、またいずれ別件で取り扱いたく思う。また、ここでいう“内面の自由”は自由意志とは異なる。)
■必要な混乱?
エッセイの冒頭に掲げられた引用は、ポール・ヴァレリーの1932年11月16日の講演からである。
彼はその最初の方で、この混乱が私たちの原動力にもなっていることに注意を促している。そして、そこでのある種の「新しさ」についても、こう述べる。
《そしてそれが我々の原動力にもなっていて、我々自身で創造したこの混乱が、我々にはどこだか解らない方向、また我々が行こうと欲しない方向にいまや我々を導いてゆく。…〔略〕…そしてこの新しさは、我々が生きている時代そのものの新しさから来ている。》(Valéry, op.cit., pp.15-16)
この現在の混乱の状態——奇しくも、このコロナ禍においても私たちはある新しさに遭遇し、生活のあり方までもが改変を迫られている——は、必然的に、それ相応の未来を持ち、その未来を予想することは絶対に不可能であるとも言っている。
おそらくは、我々はそこからは遠くに隔たってはいまい。しかし、ヴァレリーは私たちの知識や能力とによって武装されながら、私たちが組織し設備した世界の迷路的な複雑さを前に「精神の政治学 la politique de l’esprit」を考案することを示そうとする。このヴァレリー的な控えめな身振りこそ、我々をまた精神 esprit の「自由」へと導いていることは、付け加えるまでもない。彼はそれを、形而上学的なものとは異なる《変換する力》として定義し、人間の精神は人間を一種の《冒険》に導き入れていると述べるに至る。
《その冒険というのは、人間がその原始的な生活条件からますます離れて行こうとしている、その努力を言うのであって、あたかも人間という種属は、彼を同じ位置、同じ状態に置こうとする通常の諸本能の他に、それ等とは正反対の、もう一つの全く逆説的な本能を有するかのようなのである。》(ibid., p.33)
我々は、アーレントやルソーの考察から、人間の動物性の側面、つまりは感性的な人間性を見直してきたばかりである。だが、このヴァレリーの述べるところの、“同じ”位置や状態に逆行するような、こういってよければ“別の”本能、つまりは精神は、最初の同一性とは変容しているように思える。それは、感覚的な、そしてリダンダントではあるが受動的な〔パッシヴな〕パッション、またコンパッションの力に裏打ちされている。それは、一つのパッションなのではない。“別の”パッションを必要としているようにも思える。
問題だったのは、“パッションなき”理性の能力だったともいえる。それは、そもそもパッションの語源—pathos, πάθος—にある「耐え忍ぶこと」(忍耐)を欠いているがために軽薄で軽率な能力(“白痴な”欲望=欲求能力)であり、せいぜい《未来に後退りして進んでいく》(ibid., p.65) だけではないだろうか?
★追記:アーレントに即した必要と自由の区別の優れて明晰な要約と問題点は、今出敏彦『ハンナ・アーレント『人間の条件』再考―世界への愛』(2013) の第二章・第一節においても見られる。また、アーレントが据え損なっただろう二つの必然性の区別については、木前利秋『メタ構想力——ヴィーコ・マルクス・アーレント』(2008) の第八章・第一節から第二節において問題提起されている。