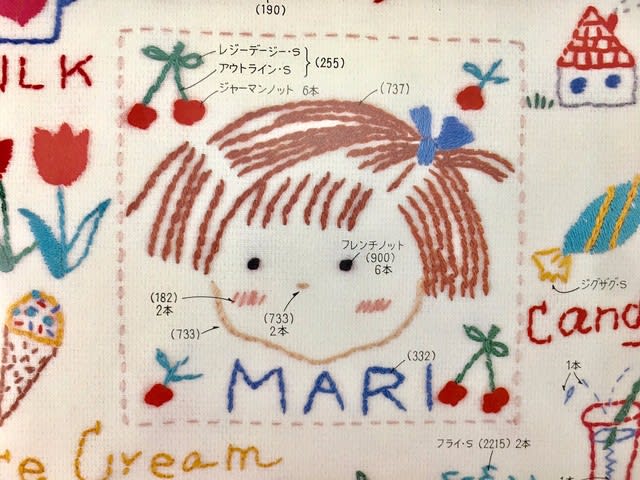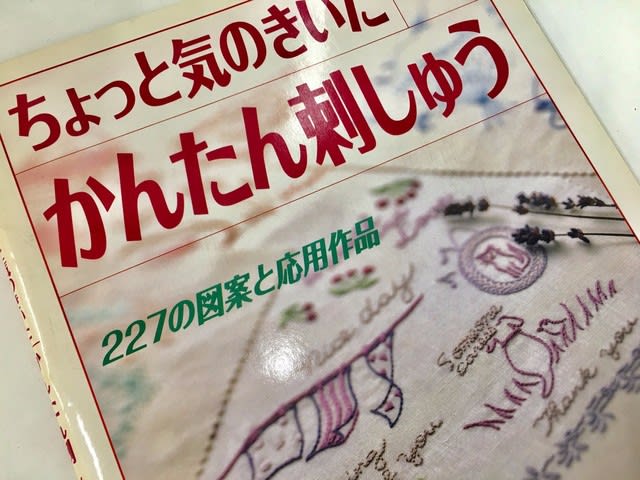今日は本の紹介です。
タイトルは、『異才、発見!―枠を飛び出す子どもたち』(伊藤史織著、岩波新書、2017)。
みなさんは「異才発掘プロジェクトROCKET(Room Of Children with Kokorozashi and Extra-ordinary Talents)」をご存知でしょうか?
これは、東京大学先端科学技術研究センターと日本財団との共同主催で実現した、新たな「学びの場」です。
指導方針に従ってはっきりとした「基準」を設けて教育を行う「学校」。
その決められた枠から、はみ出してしまう子どもたちがいます。学校では「変わった子」「空気の読めない子」「言った通りにできない子」「馴染めない子」などと呼ばれています。
そんな子どもたちの中には、特化した才能を持つ子もたくさんいます。
このプロジェクトは、その「才能」を潰すことなく、どんどん引き伸ばしていこうという取り組みです。
決して、社会に適応させよう、不登校の子どもを学校に戻そうというものではありません。
本書は、筆者がこの取り組みを長期取材しまとめたものです。
学んでいく子どもたちのようす、主催者が目指すものや熱意を伝えながら、「教育」について新しい問いをくれます。
子どもたちは強烈な個性を持っていて、集団を気にせず好き勝手に動き回ります。それを注意する大人はここにはいません。自分のやりたいことを自分のペースでとことんやらせます。
印象的だったのは、好きなことだけを思い切りやらせるのと同時に、自分の力で考えること、自分のすることに責任が伴うということをしっかりと教える大人の姿です。
子ども扱いせず、厳しく教える分、その土台にはスタッフと子どもの絶対的な信頼関係があります。
前半では、「周りと違う子」を育てる筆者の実経験も綴られていて、「親」の心理的な部分が隠さず語られます。
あとがきで、「生きているだけでいいと心から思ってくれる人がいることが、子どもの生きる力の源です」という一文が胸に刺さります。
「才能」というとなんだかすごいもののように聞こえますが、子どものどんなに小さな力も信じてあげられることが大切だと感じました。
簡単なことではありませんが、学校、家庭、社会が少しずつ変わっていけたらと思います。
イオ9月号の書評欄でも紹介されます。
興味がある方はぜひ読んでください。
--------------------------
さて、イオ編集部は明日から1週間、夏休みに入ります。
実は昨日の朝、転んで足の甲を捻挫してしまいました。痛いです。
病院で全治2週間と言われましたが、いやいや、5日で治します(治したいです)。
でないと連休の計画を遂行できません…!!
休みの期間は、日刊イオもお休みします。次回更新は18日です。(S)