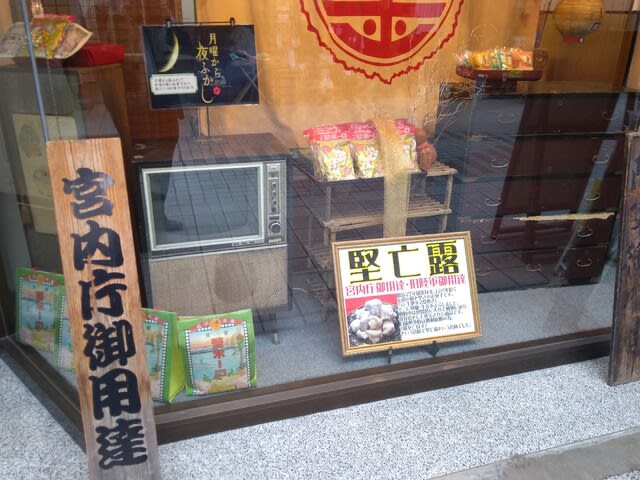今日は、製作した真空管アンプの裏蓋の作成を行いました。裏ブタなので大したことはしていませんが、木枠に固定するためのネジ穴と、足、通気口の作成ぐらいです。

まずネジ穴は、縦横均等に3本ずつ入るようにしています。また、足ですが、今回初めてくり抜いた木の足を作って見ました。製作中の足を写真に示します。

足にしている木は、100均で買ってきた桐の木です。4㎝のホールソーでくり抜いて、ボール盤で回転させながらやすりで磨いていますが、目の細かいサンドペーパーをかけないと表面がザラザラです。
そして出来上がりは、下記のような感じです。

色を塗っていないのでなんだか浮いていますが、ま、とりあえずこれで。この足にさらに丸いフエルトを張り付けようと思います(今日はフエルトがなくて張っていません)。
そして通気口は4㎝のホールソーで対角線上に穴あけしましたが、穴から虫が入らないようにパンチングメタルでふさいでします。部品取りで落札した古いアンプを解体作業中に、たまに、シャーシ内に”Gブリ”の卵があったりします。気持ち悪~いアンプにならないよう気をつけましょう。
そして、シャーシが案外熱くなるので、あまり熱いようだと、ファンをつけるかもわかりませんが、ほこりが入るので私はファンは嫌いです。
シャーシが熱くなる原因は、300Bのカソード抵抗の排熱、電源トランスの熱、ヒータの整流用ブリッジダイオードあたりだと思いますが、それにしてもカソード抵抗の熱が結構大きい。ここは定電流回路などに変更する可能性もありです。まだまだいろいろ触るところがありそうです。
ではまた~。

















 この、のっぺいうどんは、長浜の発祥らしく、とろみのついた汁にほんのりショウガが効いておいしいうどんでした。やっぱり現地で食べてよかった。うどんの中央にある黒い丸いものは大きなシイタケで、かじっても嚙み切れず苦労しましたが、2つに折ってかじると厚みが出て切れやすく、うまく食べることができました。
この、のっぺいうどんは、長浜の発祥らしく、とろみのついた汁にほんのりショウガが効いておいしいうどんでした。やっぱり現地で食べてよかった。うどんの中央にある黒い丸いものは大きなシイタケで、かじっても嚙み切れず苦労しましたが、2つに折ってかじると厚みが出て切れやすく、うまく食べることができました。