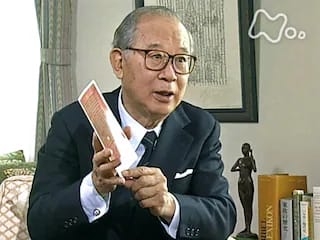先日、NHKからBS放送の受信が可能なテレビをお持ちなら、BS受信料を支払ってほしい旨のレターが届いた。昔は、NHK職員らしき人が受信料の支払いを求めて、家にやってきたこともあったが、最近はとんと見かけていない。当時すこぶる評判が悪く、BSは見ていないと玄関越しに断ったこともあるが、手紙作戦は継続しているようである。
NHK法なるものに基づいて、NHKの受信料を支払うことについては、公共性から理解するし、現に支払っているが、BS放送となると話は別である。公共の放送は、地上デジタルに一本化して実施すべきであり、公共性をBS放送にも求めることは理解できない。民放各局でもBS放送を行っているが、民放のもので十分である。
NHKは、BS放送を見たい人だけにお金を徴収して見せるようにすればいいと思う。現代の放送技術を使って、視聴料を払っていない家庭のテレビにはスクランブルをかけて、見せないようにすればいいだけである。以前は、スクランブルがかかっていたが、なぜか今はかかっていないようである。何か問題でもあったのであろうか?
テレビにBS受信機能が付いているならそれだけの理由で、見てもいないBS放送の受信料を強制的に徴収しようとするのはおかしいと思う。テレビが見られるスマホを持っているだけで、見てもいない人にNHK受信料を支払えという議論といっしょである。我が家では居間のテレビのアンテナコードの接触不良だと思うが、地上波は見られるが、BSについては、受信できませんというレスポンスが表示される。
「NHKから国民を守る党」というような政党がある位だから、受信料について疑問を持っている人もいかに多いかを物語っている。過去にはNHK職員の不祥事も多発しており、上層部の政権との癒着も気になる。政権の意向でアナウンサーを降板させたり、左遷させたり、目に余る人事も少なくない。NHKをやめて民放にトラバーユするアナウンサーも後を絶たない。NHKは、政権の御用メディアになることなく、本来のメディア機能を十分発揮し、公正な放送を実行してほしいものである。問題点がすべてクリアになり、納得できたら支払ってもいいと思うが、現時点では、見てもいない BSの受信料を支払うことには否定的である。