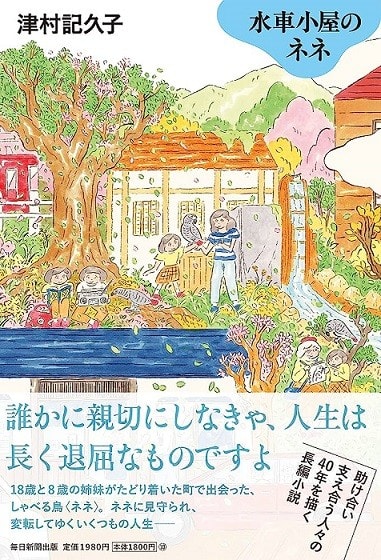春暮康一 早川書房
ワシのごとき古狸SFファンは著者のペンネームを見れば、ふふん、なるほどと思う。ハル・クレメントというSF作家がアメリカにいた。ワシらが若いころの海外ハードSF作家といえば、ぱっと思いつくのは、ジェイムス・ブリッシュかハル・クレメントだった。この春暮康一というペンネームは、そのハル・クレメントからとったとのこと。
ハードSFといってもいろいろあるけど、ジェイムス・ブリッシュは物理系のハードSF。ハル・クレメントは生物系ハードSFであった。クレメントの代表作「重力の使命」はものすごい重力を持つ惑星に住む生物が出てくる。平べったいムカデみたいなやつだが、重力が生物にどういう影響をおよぼすか考察している。そのハル・クレメントにリスペクトする著者の作品集は3篇の中編が収められている。
「主観者」「法治の獣」「方舟は荒野をわたる」いずれも特異な環境に棲息する異様な(人間の観点から見た)生き物たちが登場する。「主観者」は異星の海の発光群体生物。「法治の獣」スペースコロニー「ソードⅡ」の法律は一角獣シエジーが司っているらしい。「方舟は荒野をわたる」惑星オローリンは自転周期と傾斜軸がグラグラ変わる。そんな星にも生き物はいる。
かようなSFはいかに異様な星を設定するか。その星に生きる生物はどんなんだ。それを期待して読者は読むのだが、下手するとこんなんありえん、となるが、この作品集では、なるほどこういう環境ではこうなるか。納得がいくのである。SFを読むよろこびを感じさせてくれた。