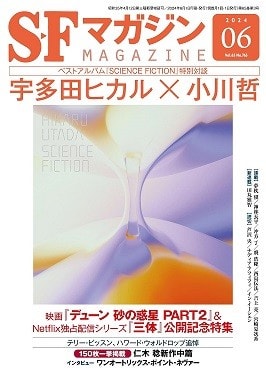昨日は神戸新開地喜楽館に行っとった。喜楽館はでけて6年や。そやから、昨日は喜楽館開館6周年記念特別公演の最終日やった。
神戸新開地喜楽館は2018年7月11日に開館した。ワシもこけら落とし公演に行こうと思ったけど、この時のチケットは30分で完売。さすがのワシも買えなんだわ。ここだけの話やけどな、喜楽館、ほんまは別の名前になる予定やったんや。神戸の新開地に上方落語の定席ができるゆうんで、小屋の名前を公募しとった。ワシは「新開地ええとこ亭」で応募した。自信もっとったんやけどな。
ワシの高校はいまはなき神戸市立湊川高校やった。そやから新開地は地元や。今はそんなことないけど、昔は「ヤ」のおじさんらの巣やった。その新開地に聚楽館ゆう映画館があった。今はパチンコ屋になっとるけど、「ええとこええとこ聚楽館」といわれたもんや。高校の定期試験が終わったらよう聚楽館で映画をみたで。「大脱走」「ワイルドバンチ」「ミクロの決死圏」なんかを観たな。その聚楽館への想いをこめて「新開地ええとこ亭」と名付けたんやけどな。
ま、ワシの思い出話はこのへんで、昨日の話や。
開演前の一席は桂かかおさん。小枝師匠のお弟子さん。前座噺の定番「動物園」をやらはった。オーソドックな「動物園」を無難にやらはったけど、少しは工夫があったもええんちゃうん。
開口一番は月亭秀都さん。高座名から判るように月亭文都さんのお弟子さん。これまた前座噺の定番「時うどん」夏にやる噺やないと思うんやけどな。
二番手は笑福亭鉄瓶さん。「骨つり」をやらはった。オーバーアクションな見ごたえのある「骨つり」やった。鶴瓶一門はうまい噺家さんが多いです。
色もんはラッキー舞さんの太神楽。清楚な女性の芸人さん。定番の傘の上で鞠や枡を廻す芸のあと、出刃包丁を3本使った芸はなかなかスリリングやった。
仲トリは桂雀三郎師匠。「代書屋」や。枝雀一門らしく主人公の名前は松本留五郎。ちゃんと「セーネンガッピ」や「セーネンガッピ、ヲ」「ポン」もあった。やっぱり松本留五郎はおもろいわ。
仲入り後の最初は桂文之助さん。「紙入れ」です。アニキのよめさんと不倫する噺です。
トリ前は先代文枝師匠の最後のお弟子さん。明石出身の桂阿か枝さん。朝霧駅前のしおみ産婦人科で生まれたといってはった。いまはせきじま産婦人科になってますけど、とゆうてはった。グーグルアースで見るとほんまに朝霧駅前に「せきじま産婦人科」があった。
「千早ふる」をやらはった。ところどころの先代文枝師匠の面影をかいま見ることができた。あのねちゃーとした先代文枝師匠の語り口を一番いろこく受け継いでいるのは、先代文枝一門では阿か枝さんやないかとワシは思うな。
さて、トリは笑福亭鶴瓶師匠。まくらでたっぷり、先日亡くなった桂ざこば師匠の思い出噺。ふたりでよう遊んだそうです。あんな落語家はもう出ませんと鶴瓶さんはいってはった。「三年目」をやらはった。鶴瓶さんの落語をなまで見る機会は少ないけど、さすがうまいです。
神戸新開地喜楽館は2018年7月11日に開館した。ワシもこけら落とし公演に行こうと思ったけど、この時のチケットは30分で完売。さすがのワシも買えなんだわ。ここだけの話やけどな、喜楽館、ほんまは別の名前になる予定やったんや。神戸の新開地に上方落語の定席ができるゆうんで、小屋の名前を公募しとった。ワシは「新開地ええとこ亭」で応募した。自信もっとったんやけどな。
ワシの高校はいまはなき神戸市立湊川高校やった。そやから新開地は地元や。今はそんなことないけど、昔は「ヤ」のおじさんらの巣やった。その新開地に聚楽館ゆう映画館があった。今はパチンコ屋になっとるけど、「ええとこええとこ聚楽館」といわれたもんや。高校の定期試験が終わったらよう聚楽館で映画をみたで。「大脱走」「ワイルドバンチ」「ミクロの決死圏」なんかを観たな。その聚楽館への想いをこめて「新開地ええとこ亭」と名付けたんやけどな。
ま、ワシの思い出話はこのへんで、昨日の話や。
開演前の一席は桂かかおさん。小枝師匠のお弟子さん。前座噺の定番「動物園」をやらはった。オーソドックな「動物園」を無難にやらはったけど、少しは工夫があったもええんちゃうん。
開口一番は月亭秀都さん。高座名から判るように月亭文都さんのお弟子さん。これまた前座噺の定番「時うどん」夏にやる噺やないと思うんやけどな。
二番手は笑福亭鉄瓶さん。「骨つり」をやらはった。オーバーアクションな見ごたえのある「骨つり」やった。鶴瓶一門はうまい噺家さんが多いです。
色もんはラッキー舞さんの太神楽。清楚な女性の芸人さん。定番の傘の上で鞠や枡を廻す芸のあと、出刃包丁を3本使った芸はなかなかスリリングやった。
仲トリは桂雀三郎師匠。「代書屋」や。枝雀一門らしく主人公の名前は松本留五郎。ちゃんと「セーネンガッピ」や「セーネンガッピ、ヲ」「ポン」もあった。やっぱり松本留五郎はおもろいわ。
仲入り後の最初は桂文之助さん。「紙入れ」です。アニキのよめさんと不倫する噺です。
トリ前は先代文枝師匠の最後のお弟子さん。明石出身の桂阿か枝さん。朝霧駅前のしおみ産婦人科で生まれたといってはった。いまはせきじま産婦人科になってますけど、とゆうてはった。グーグルアースで見るとほんまに朝霧駅前に「せきじま産婦人科」があった。
「千早ふる」をやらはった。ところどころの先代文枝師匠の面影をかいま見ることができた。あのねちゃーとした先代文枝師匠の語り口を一番いろこく受け継いでいるのは、先代文枝一門では阿か枝さんやないかとワシは思うな。
さて、トリは笑福亭鶴瓶師匠。まくらでたっぷり、先日亡くなった桂ざこば師匠の思い出噺。ふたりでよう遊んだそうです。あんな落語家はもう出ませんと鶴瓶さんはいってはった。「三年目」をやらはった。鶴瓶さんの落語をなまで見る機会は少ないけど、さすがうまいです。