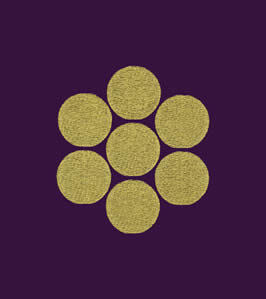☆ハート・ロッカー(2008 アメリカ 131分)
原題 The Hurt Locker
staff 監督/キャスリン・ビグロー 脚本/マーク・ボール 撮影/バリー・アクロイド
美術/カール・ユーリウスソン 音楽/マルコ・ベルトラミ、バック・サンダース
cast ジェレミー・レナー アンソニー・マッキー ガイ・ピアース デヴィッド・モース
☆2004年夏、イラク、バグダッド
少年だった頃、ぼくは兵器にまるで興味がなかった。
友達の中にはめったやたらに戦闘機や戦車や軍艦に詳しいやつがいて、
プラモデルもそういう類いのものばかり作ってた。
ぼくは、だめだった。
なんでだろうとおもうんだけど、いまだに理由はわからない。
戦争に興味のない少年は、おとなになってもなかなか興味が湧かなかった。
それでも長く生きてれば、すこしは戦争や兵器について知識がついてくるものだ。
でも、そんなものは単なる付け焼刃でしかなかった。
IED(即席爆発装置)とかEOD(爆発物処理)とかいう単語も知らなかったし、
イラク戦争において、
アメリカ兵のIEDによる死傷者が凄まじい数に上っているなんてことも知らなかった。
だから、爆発物処理班がどのような活動をしているのか、
この映画を見ながら、ああ、そうなんだ~となんとか理解できたくらいだ。
まったく、自分のことが情けなくなってくるけど、事実なんだから仕方がない。
で、この映画なんだけど、
主題の受け止め方について、なんだか、いろんな意見があるみたいで、
それはつまり、おのおのの観客がおのおのの意見をいわざるを得ないほど、
強烈な映画だったってことなんだろう。
実際、映像は、衝撃的ですらあった。
じりじりした緊迫感もさることながら、爆弾が爆発する瞬間のスローモーションとか、
ぞくっとするほど強烈だったし、美しさすら感じとれてしまった。
実際に戦場に送り込まれている兵士たちに、美しさなんていったら怒られるだろうけど、
それは、演出のちからづよさを証明するものだから、仕方がない。
でも、たしかにリアルなんだけど、ドキュメンタリーを見ているような印象は受けなかった。
全体の構成にしても、いくつかの挿話にしても、むろん会話にしても、計算されたものだ。
で、ジェレミー・レナー演じるところの、
イラク駐留アメリカ軍爆発物処理班B(ブラボー)中隊に途中から配属された、
爆弾処理の熟練ウィリアム・ジェームズ一等軍曹のことなんだけど、
兵士の誰もが精神が崩壊してしまいそうな戦場で、彼は偏執的に職務をこなしてる。
心が病んでしまっているのか、それとも自暴自棄になっているのか、判断はつかない。
ただ、原題から、なんとなく想像することはできる。
原題の「Hurt Locker」というのは、辞書によれば、米軍の俗語で、
「極限まで追い詰められた状態。または棺桶のこと」らしい。
ということは、
戦場という地獄に放り込まれ、異常な緊迫感の中で爆弾を処理している内に、
徐々に心を閉ざし、愛情とか憐憫とかいった物柔らかな感情を失ってしまった主人公が、
アメリカの家族も含めて誰とも打ち解けられない荒々しい日々を送っていたんだけど、
あるとき現地の少年と出会ったことで、少しだけ人間的な感情を取り戻したのも束の間、
その少年までもが殺され、体内に爆弾を埋め込まれるという、
あまりにも惨たらしい目に遭わされたために常軌を失い、かつ、心の底まで蝕まれ、
ひとたびは母国アメリカに帰ったものの、穏やかな生活にはもはや馴染めなくなり、
ふたたび死の崖っぷちに立たされるイラクの地へ戻ってゆかざるを得なくなるんだけど、
主人公にとって、棺桶のような戦場は、実は彼が生を実感できるところで、
つまり、戦争の恐ろしさは、そうした人間を生産してしまうところにあるというのが、
もしかしたら、この映画のいわんとしていることなのかもしれない。
よくわからないのは、
殺されたはずの少年、あるいはその子に酷似した少年が、
主人公の前に現れてDVDを売ろうとするところで、
ジェレミー・レナーは唖然とするのと同時に、少年を拒むような態度に出る場面だ。
これは、
たとえ、その少年が以前の少年であろうがなかろうが、
二度とふたたび子供の死をまのあたりにしたくないという彼個人の防衛本能なのか、
あるいは、自分が新たな少年に接してしまえば、
今度はこの少年が犠牲になる恐れがあるんじゃないかとおもい、
そうした悲劇をふたたび起こさないために配慮して拒んだのか、ということだ。
ぼくは、人の顔がよく憶えられないものだから、
余計にそんな曖昧なことをおもってしまうのかもしれないけど、
ただ、監督のキャスリン・ビグローの意図しているのが、
アメリカに対する反戦の主張なのか、それとも普遍的な意味での戦争反対なのか、
いまのところは、どちらとも判断がつかない。