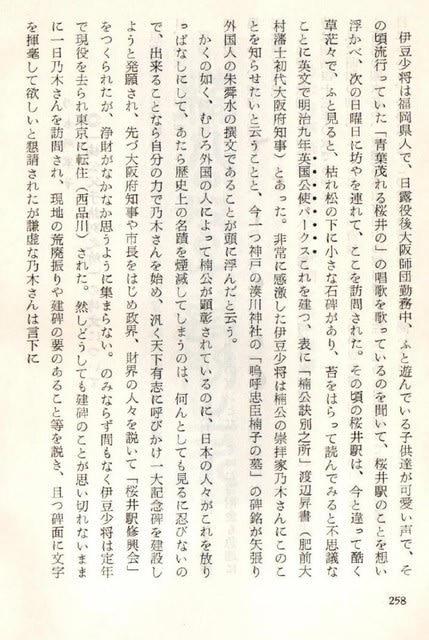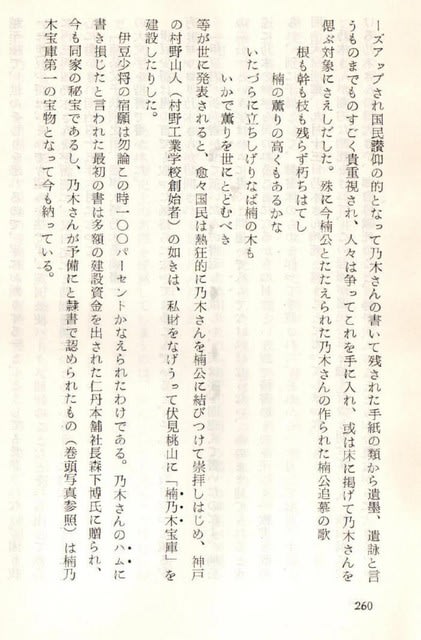今週のNHK朝ドラ「エール」は第13週「スター発掘オーディション!」です。
Gooニュースでは下のリンクのように今週のストーリーを紹介しています。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/crankin/entertainment/crankin-7769103
6月22日(月)放送の 61話ではこんな内容でした。
コロンブスレコードと契約して5年が過ぎ、裕一(窪田正孝)はご当地ソングや
「大阪タイガース」など球団歌を数多く手がけ、安定した作曲家生活を送っていた。
ある日、裕一は廿日市(古田新太)から「コロンブス専属新人歌手募集」の
オーディション合格者のデビュー曲の作曲を依頼される。
裕一は4年前に音楽学校を卒業以来、いまだオペラ歌手としてデビュー
できていない久志(山崎育三郎)に応募を勧める。
掛布元監督が特別出演
4歳になった華ちゃん(田中乃愛)が喫茶店でスイーツを食べており、
傍に音(二階堂ふみ)が色々と世話をしている場面から始まります。
華ちゃんを演じるのは、セントラル所属の子役・田中乃愛(のあ)ちゃん。
なつぞら では、奥原咲太郎・なつの妹、千遥の幼少期を演じていました。
また、大河ドラマ 「麒麟がくる」 では、大火事で両親を失った幼少期の
駒を演じていました。
実話では
古山裕一・音のモデルは古関祐而・金子夫妻
鉄男のモデルは野村 俊夫
久志のモデルは伊藤久男です。
古関祐而、野村俊夫、伊藤久男の3人は福島の三羽烏と言われています。
今日のドラマは実話の昭和11年(1936)を設定
この年に大阪タイガースの歌(六甲おろし)を作曲しています。

上の写真はドラマ(6月22日放送)での福島三羽烏
伊藤久男についてWikipediaより引用紹介します。
伊藤 久男(いとう ひさお)は、日本の歌手
生年:1910年(明治43年)7月7日
没年: 1983年(昭和58年)4月25日
本名は伊藤 四三男(いとう しさお)。福島県本宮市出身。
本名の四三男は生年の明治43年に由来する。元妻は戦前にコロムビアレコード
等で活躍した元芸者歌手・赤坂百太郎(大西ふさ子)。
伊藤は同郷の作曲家・古関裕而の作品を多くレコーディングしている。「露営の歌」「続露営の歌」
「暁に祈る」「海底万里」といった戦時歌謡から、「イヨマンテの夜」「君いとしき人よ」
といった歌謡曲、また、現在でも夏の高校野球全国大会で歌われている「栄冠は君に輝く」
までも伊藤の創唱によるものであった。
NHK紅白歌合戦にも計11回出場している。古関裕而のクラシックの格調は、
美しいテナーの音色で歌う藤山一郎に代表されるが、古関メロディーのドラマティックな
抒情性は伊藤久男のリリックな歌唱によって声価を高めた。
エール 62話 6月23日(火)はつぎのような展開になるようです。
久志(山崎育三郎)がなぜ音楽の道に進むことになったのか、そのきっかけについての物語。
学校ではクールにふるまっている10歳の久志(山口太幹)だったが、
家では父の再婚で新しくやってきた母・玲子(黒川芽以)になじむことができず、葛藤をかかえていた。
担任の藤堂先生(森山直太朗)は、ある日クラスの皆で歌っている時に
久志の歌の才能に気づいて、学芸会でその歌声を披露することをすすめる。
最後に、伊藤久男の歌唱で曲:古関祐而、詞:野村俊夫の福島三羽烏により
昭和15年(1940)にレコード化された「暁に祈る」のyoutube動画を添付。
暁に祈る 伊藤久男