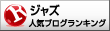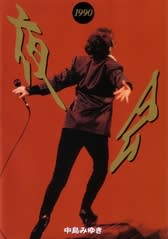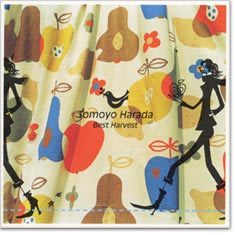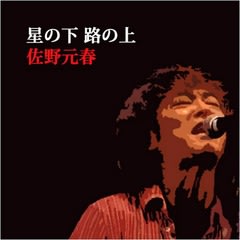昨晩、「NHKアーカイブス」で「ステージ101」の最終回というのを放送してましたね。1974年3月に放映したものだそうです。
アタシャ、残念ながら、この番組はリアルタイムでは見たかどうか分からないし、見たとしても覚えていません。
この頃のアタクシはウラホロという十勝の片田舎に住んで居たんですが、4歳だったので、「ロンパールーム」とか、「はたらくおじさん」とか、そんなもんばっかり見てましたし、両親も、30代半ばだったんで、まぁ、「ステージ101」は、見てなかったであろうと思います。
そんで、見ていなかった筈のこの番組になんで興味がアルのかと言えば、太田裕美さんや谷山浩子サンが出演していた番組として知っているからなんですね。
まぁ、そういうコトで、ハテ、出演しているのかな~、とか思いながら見てたんですが、裕美さんは居らっシャイましたが、浩子サンは分からんかった。(浩子サンもエンドロールには名前が出ていたが・・・)
実は、昨晩は、この放送の途中から見たんで、せいぜい30分しか見てないんですが、国内のポップス(番組オリジナルが中心のようですね)と海外のポップスがバランスよく配されていていた番組だったという事が理解できました。音楽ファンを増やすという事にはかなり貢献した番組だったんじゃないッスか?
まぁ、NHK的に角が丸まったサウンドになってたんで、当時から、ロック原理主義者にはウケが悪かったと思われますけどサ。
あと、先日亡くなった宮川泰先生も、この番組に絡んでたようですね。
番組ともどもポップ・ミュージックの裾野を広げる事に貢献してたんですね~、やっぱり。
あと、田中星児氏がこの番組を起点にして、「うたのお兄さん」になったそうですが、田中星児氏は、ワタクシにとって最初のミュージック・ヒーローだったんで、そういう意味では、アタクシもこの番組の影響を受けたとは言えますワ。
アタシャ、残念ながら、この番組はリアルタイムでは見たかどうか分からないし、見たとしても覚えていません。
この頃のアタクシはウラホロという十勝の片田舎に住んで居たんですが、4歳だったので、「ロンパールーム」とか、「はたらくおじさん」とか、そんなもんばっかり見てましたし、両親も、30代半ばだったんで、まぁ、「ステージ101」は、見てなかったであろうと思います。
そんで、見ていなかった筈のこの番組になんで興味がアルのかと言えば、太田裕美さんや谷山浩子サンが出演していた番組として知っているからなんですね。
まぁ、そういうコトで、ハテ、出演しているのかな~、とか思いながら見てたんですが、裕美さんは居らっシャイましたが、浩子サンは分からんかった。(浩子サンもエンドロールには名前が出ていたが・・・)
実は、昨晩は、この放送の途中から見たんで、せいぜい30分しか見てないんですが、国内のポップス(番組オリジナルが中心のようですね)と海外のポップスがバランスよく配されていていた番組だったという事が理解できました。音楽ファンを増やすという事にはかなり貢献した番組だったんじゃないッスか?
まぁ、NHK的に角が丸まったサウンドになってたんで、当時から、ロック原理主義者にはウケが悪かったと思われますけどサ。
あと、先日亡くなった宮川泰先生も、この番組に絡んでたようですね。
番組ともどもポップ・ミュージックの裾野を広げる事に貢献してたんですね~、やっぱり。
あと、田中星児氏がこの番組を起点にして、「うたのお兄さん」になったそうですが、田中星児氏は、ワタクシにとって最初のミュージック・ヒーローだったんで、そういう意味では、アタクシもこの番組の影響を受けたとは言えますワ。