モダンチョキチョキズ
『ボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説』(1993)
当ブログ三度目の登場のこのアルバム。
やっぱり、どう聴いても、紛れもナイ傑作。
伝説的な一枚。
1曲目「コンガと私」
老婆と化した濱田マリの語りでスタート。「やってますか・・・?」のくだりは何度聴いても笑えるし、このヒトの語りは、それだけで聴かせる力がありますねぇ。途中から、コンガだけを伴奏とした歌になりますが、ボーカルもやはり聴かせます。
2曲目「24時間宇宙一周」
笑いの要素のない曲ですが、こういうポップなセンスも、またモダチョキの魅力の一つ。(笑いの要素がナイと言ってもフツーじゃないですが)
4曲目「ふられ節」
表面的にはアメリカ批判の歌のように聴こえますが、歌詞が掲載されていないし、意味不明な部分や、聞き取り難い部分もあったりして、よう分かりません。どうも実は「倫理」とか「意志」とかそういう難しいコトを歌っているようにも思えるんですが、そんな歌詞が、あっけらかんと、ポップなサウンドに乗っかってます。傑作。
5曲目「初恋の丘」
曲は由紀さおりの「初恋の丘」なんですが、前半は傑作なしゃべり芸。韓国語と日本語のチャンポンなハナモゲラ。爆笑。そして、本編「初恋の丘」へ繋がって行きます。濱田マリのボーカルがまた、とっても良くって、曲自体の美しさがストレートに伝わってくる。いや~、実にいいね~、と思わず聴き入りますが、良く聴くとバックコーラスが韓国語っぽい響きになっている。タダじゃ終わらない。流石だ。
6曲目「続 しとやかな獣(博士のテーマ)」
前田憲男らによるピアノトリオ演奏(マジ、カッコいい)に載せたナレーション。「クロスオーヴァー・イレヴン」のパロディですかね。え、え?ソレで終わるの~ッ!?という感じのオチが見事。
7曲目「ジャングル」
「ここはジャングル、怖いぞ。ここはジャングル、おっかない。」
ただソレだけの曲である。しかもワズカ30秒。
ココまでマンガな音楽をワタシは他に知らない。実に最高だ。
9曲目「主婦になったバーゲン娘(ガンポンギーのテーマ)」
スラッシュ・メタルに乗せて、主婦になったバーゲン娘をコキ下ろす。何度聴いても笑いが止まらん。
10曲目「アルサロ ピンサロ(パヤツのテーマ)」
歌詞はフーゾクにハマったオトコの歌なんですが、サウンドが実に見事なニューヨーク・サルサ。ニューヨーク・サルサを愛するこのワタシが言うのだから間違いナイです。なんで、こんな見事なサウンドが作れるんでしょうか?超カッコいい。
11曲目「野菜あたまRock」
濱田マリのあっけらかんボーカルが炸裂。
フランク・ザッパ的な展開もあるし、しゃべり芸も出るし、まさにモダチョキと言った感じの一曲。「やってますか・・・?」が、また出て来る。爆笑。
12曲目「有馬ポルカ (Besarabia)」
懐かしいメロディを歌わせると濱田マリは実にイイです。
13曲目「あの世へ帰りたい」
聖歌隊による仏教ソング。
そう言えば賛美歌によくあるような気がする「ド→ラ」という持ち上げ系メロディが出て来て、そういう笑わせ方もしてくれる。
14曲目「凍りの梨~ボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説~」
シュギョクの切ない系名曲。結構感動的。
最後に、また老婆になった濱田マリが出て来て、ここまでの14曲が、老婆のお話だった事が分かる。ゲ、鳥肌。
15曲目「喝采」
濱田マリの見事なカウントで始まる「喝采」。あの、ちあきなおみの「喝采」カヴァー。インストです。
コレ、ほんとーッッッに見事なカヴァーです。
ホーン・アレンジが見事。
リハーモナイズと転調のセンスが見事。
これによって、汽車、ではなくゆっくりと空を飛ぶ曲になっている。
最後のあたりの、短いソリ。鳥肌二連発。
16曲目「博多の女」
これも、超傑作。
演歌なメロディ。
強烈なブラス・ロック~ジャズ・ロックなサウンド。
超タイトで超カッコいい演奏。鳥肌三連発。
そして、最高に、くッだらねえ歌詞。
しかも、ネズミ男な声のボーカル。
(モチロン濱田サンも出て来るでよ。)
もはや、傑作中の傑作と言う他ナイ。
17曲目「『くまちゃん』予告編」
「曲」じゃないですね。
しっかし、ダジャレの連発はアホウ過ぎて笑いが止まらん。
ここまで徹底するってやっぱスゲエなぁ。
という、17曲。
凄いパワーです。
何年も続く訳ないです。
続けたら死にますから、続く訳ありません。
そのようにパワーが凝縮された傑作です。
残念ながら廃盤です。
ブックオフでどうぞ。
『ボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説』(1993)
当ブログ三度目の登場のこのアルバム。
やっぱり、どう聴いても、紛れもナイ傑作。
伝説的な一枚。
1曲目「コンガと私」
老婆と化した濱田マリの語りでスタート。「やってますか・・・?」のくだりは何度聴いても笑えるし、このヒトの語りは、それだけで聴かせる力がありますねぇ。途中から、コンガだけを伴奏とした歌になりますが、ボーカルもやはり聴かせます。
2曲目「24時間宇宙一周」
笑いの要素のない曲ですが、こういうポップなセンスも、またモダチョキの魅力の一つ。(笑いの要素がナイと言ってもフツーじゃないですが)
4曲目「ふられ節」
表面的にはアメリカ批判の歌のように聴こえますが、歌詞が掲載されていないし、意味不明な部分や、聞き取り難い部分もあったりして、よう分かりません。どうも実は「倫理」とか「意志」とかそういう難しいコトを歌っているようにも思えるんですが、そんな歌詞が、あっけらかんと、ポップなサウンドに乗っかってます。傑作。
5曲目「初恋の丘」
曲は由紀さおりの「初恋の丘」なんですが、前半は傑作なしゃべり芸。韓国語と日本語のチャンポンなハナモゲラ。爆笑。そして、本編「初恋の丘」へ繋がって行きます。濱田マリのボーカルがまた、とっても良くって、曲自体の美しさがストレートに伝わってくる。いや~、実にいいね~、と思わず聴き入りますが、良く聴くとバックコーラスが韓国語っぽい響きになっている。タダじゃ終わらない。流石だ。
6曲目「続 しとやかな獣(博士のテーマ)」
前田憲男らによるピアノトリオ演奏(マジ、カッコいい)に載せたナレーション。「クロスオーヴァー・イレヴン」のパロディですかね。え、え?ソレで終わるの~ッ!?という感じのオチが見事。
7曲目「ジャングル」
「ここはジャングル、怖いぞ。ここはジャングル、おっかない。」
ただソレだけの曲である。しかもワズカ30秒。
ココまでマンガな音楽をワタシは他に知らない。実に最高だ。
9曲目「主婦になったバーゲン娘(ガンポンギーのテーマ)」
スラッシュ・メタルに乗せて、主婦になったバーゲン娘をコキ下ろす。何度聴いても笑いが止まらん。
10曲目「アルサロ ピンサロ(パヤツのテーマ)」
歌詞はフーゾクにハマったオトコの歌なんですが、サウンドが実に見事なニューヨーク・サルサ。ニューヨーク・サルサを愛するこのワタシが言うのだから間違いナイです。なんで、こんな見事なサウンドが作れるんでしょうか?超カッコいい。
11曲目「野菜あたまRock」
濱田マリのあっけらかんボーカルが炸裂。
フランク・ザッパ的な展開もあるし、しゃべり芸も出るし、まさにモダチョキと言った感じの一曲。「やってますか・・・?」が、また出て来る。爆笑。
12曲目「有馬ポルカ (Besarabia)」
懐かしいメロディを歌わせると濱田マリは実にイイです。
13曲目「あの世へ帰りたい」
聖歌隊による仏教ソング。
そう言えば賛美歌によくあるような気がする「ド→ラ」という持ち上げ系メロディが出て来て、そういう笑わせ方もしてくれる。
14曲目「凍りの梨~ボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説~」
シュギョクの切ない系名曲。結構感動的。
最後に、また老婆になった濱田マリが出て来て、ここまでの14曲が、老婆のお話だった事が分かる。ゲ、鳥肌。
15曲目「喝采」
濱田マリの見事なカウントで始まる「喝采」。あの、ちあきなおみの「喝采」カヴァー。インストです。
コレ、ほんとーッッッに見事なカヴァーです。
ホーン・アレンジが見事。
リハーモナイズと転調のセンスが見事。
これによって、汽車、ではなくゆっくりと空を飛ぶ曲になっている。
最後のあたりの、短いソリ。鳥肌二連発。
16曲目「博多の女」
これも、超傑作。
演歌なメロディ。
強烈なブラス・ロック~ジャズ・ロックなサウンド。
超タイトで超カッコいい演奏。鳥肌三連発。
そして、最高に、くッだらねえ歌詞。
しかも、ネズミ男な声のボーカル。
(モチロン濱田サンも出て来るでよ。)
もはや、傑作中の傑作と言う他ナイ。
17曲目「『くまちゃん』予告編」
「曲」じゃないですね。
しっかし、ダジャレの連発はアホウ過ぎて笑いが止まらん。
ここまで徹底するってやっぱスゲエなぁ。
という、17曲。
凄いパワーです。
何年も続く訳ないです。
続けたら死にますから、続く訳ありません。
そのようにパワーが凝縮された傑作です。
残念ながら廃盤です。
ブックオフでどうぞ。











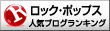





 )
)







 君のテレフォゥン・ナンむバぁ~ア」と歌う最後の「
君のテレフォゥン・ナンむバぁ~ア」と歌う最後の「




