公的情報を隠し、庶民の個人情報を収集して分析、さらに子どもの性格や思想傾向を調べて監視へ 櫻井ジャーナル 2015.05.22
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505220000/
これまでも公的な情報を国民に開示してこなかった日本政府だが、「特定秘密保護法」を成立させて秘密度は一段と高まった。戸籍が充実し、警察が住民に関する情報を集めている日本は監視制度が整備されている国だが、「住民基本台帳」や「マイナンバー制度」の導入でその監視度は一段と高まる。企業が独自に集めている個人情報も膨大で、それを統合して管理するシステムも開発されているはずだ。既に存在しているかもしれない。

庶民を主権者だと考えていない支配層は昔から強力な監視システムを欲しがってきた。監視社会をテーマにした小説『1984』をジョージ・オーウェルは1949年に書いたが、すでにそれは現実になっている。オーウェルはソ連を想定していたらしいが、実際はアメリカが最先端の国だ。

オーウェルが『1984』を出す直前、アメリカでは闇の世界が生まれていた。1948年には心理戦や破壊活動を目的とした極秘機関の「特殊計画局」が創設され、「OPC(政策調整局)」へ名称変更になった。1944年に米英の情報機関が設置したゲリラ戦部隊の「ジェドバラ」を大戦後も存続させようとしたようだ。
OPCは1950年にCIAへ吸収され、「計画局」の核になった。その直後にアレン・ダレスが副長官としてCIAへ乗り込んで来る。1973年に「作戦局」へ名称が変更になるが、活動の一端が議会の調査で明るみに出たことが原因だ。2005年には「NCS(国家秘密局)」に衣替えしている。
破壊活動の延長線上に戦争はあるが、アメリカの支配層はその戦争に反対する人や団体を最も恐れる。FBIは1950年に国民監視プロジェクトの 「COINTELPRO」を、またCIAも同じ目的で1967年にMHケイアスをスタートさせている。彼らにとってアル・カイダ系の戦闘集団、IS、あるいはネオ・ナチは「自由の戦士」だが、平和を愛し、戦争に反対する人びとは「テロリスト」だということ。「愛国者法」でも同じことが言える。

OPCが設立されたころ、アメリカとイギリスは電子的な情報活動の連携を目的として「UKUSA(ユクザ)協定」を締結した。現在もこの協定は生きていて、アメリカの「NSA」とイギリスの「GCHQ」が中心。GCHQが設立されたのは1942年だが、NSAは1952年。NSAの前身である 「AFSA」も1949年で、協定の方が先ということになる。
UKUSAは情報の収集と分析が目的だが、発信する情報を統制する仕組みも同じ頃に始まっている。ジャーナリストのデボラ・デイビスが「モッキンバー ド」と呼ぶ情報操作プロジェクトで、その中心にはアレン・ダレス、フランク・ウィズナーOPC局長、後にCIA長官に就任するリチャード・ヘルムズ、そしてワシントン・ポスト紙の社主だったフィリップ・グラハム。同紙は後にウォーターゲート事件でリチャード・ニクソン大統領を辞任に追い込む。その時の社主、キャサリン・グラハムはフィリップの妻だ。
ウォーターゲート事件はふたりの若手記者、ボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインが中心になって調査していたが、そのうちバーンスタインは 1977年に退社、「CIAとメディア」というレポートをローリング・ストーン誌に書いている。バーンスタインによると、その当時でさえ400名以上の ジャーナリストがCIAのために働き、1950年から66年にかけてニューヨーク・タイムズ紙は10名以上の工作員に架空の肩書きを提供していたという。 こうしたことは別のメディアでも行われていただろう。(Carl Bernstein, “CIA and the Media”, Rolling Stone, October 20, 1977)
しかし、1970年代までは気骨ある記者や編集者がメディアには存在、ある程度は情報を発信していた。そうしたジャーナリストの締め出しが強化されたのは1980年代だ。巨大資本による支配が認められたこともあり、プロパガンダ色が急速に強まった。
同じ頃、日本では手間暇かけた地道な取材で中身のある報道をするより、手抜き取材の方が「コスト・パフォーマンスが良い」という考え方をする経営者が増えた。体制に批判的な雑誌を支えていたのは総会屋だったことも事実で、総会屋の取り締まりで反体制的なメディアは大きなダメージを受けた。
フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング(FAZ)紙の編集者だったウド・ウルフコテは最近のメディアとCIAとの関係を本にしている。彼によると、ドイツだけでなく多くの国のジャーナリストがCIAに買収され、例えば、人びとがロシアに敵意を持つように誘導するプロパガンダを展開しているという。
そうした仕組みを作り挙げるため、アメリカの支配層はドイツの有力な新聞、雑誌、ラジオ、テレビのジャーナリストを顎足つきでアメリカに招待、そうして 築かれた「交友関係」を通じてジャーナリストを洗脳していくらしいが、これは1970年代と同じ。日本にも「鼻薬」を嗅がされたマスコミ社員は少なくないと言われている。
むのたけじは1991年に開かれた「新聞・放送・出版・写真・広告の分野で働く800人の団体」が主催する講演会の冒頭、「ジャーナリズムはとうにくたばった」と発言して疎んじられるようにようになったらしいが、この指摘は事実。(むのたけじ著『希望は絶望のど真ん中に』岩波新書、2011年)

ウルフコテは今年2月にこの問題に関する本を出しているが、その前からメディアに登場し、告発に至った理由を説明していた。ジャーナリストとして過ごした25年の間に教わったことは、嘘をつき、裏切り、人びとに真実を知らせないということで、 ドイツやアメリカのメディアがヨーロッパの人びとをロシアとの戦争へと導き、引き返すことのできない地点にさしかかっていることに危機感を抱いたようだ。 日本の状況はさらに悪い。
こうした告発の前、昨年8月にドイツの経済紙ハンデスブラットの発行人、ガボール・シュタイガートは「西側の間違った道」と題する評論を発表している。ウクライナが不安定化する中、「西側」は戦争熱に浮かされ、政府を率いる人びとは思考を停止して間違った道を歩み始めたと批判しているのだ。
こうしたメディアを使った情報操作のほか、「教育」で洗脳しようとしている。

安倍晋三政権はその点、露骨。多くの人はメディアや教育でコントロールされるが、それでも騙されない人はいるわけで、そうした人びとを探し出すシステムも開発されている。
ACLU(アメリカ市民自由連合)によると、スーパー・コンピュータを使い、膨大な量のデータを分析して「潜在的テロリスト」を見つけ出そうとするシステムの開発も進んでいる。つまり、どのような傾向の本を購入し、借りるのか、どのようなタイプの音楽を聞くのか、どのような絵画を好むのか、どのようなドラマを見るのか、あるいは交友関係はどうなっているのかなどを調べ、性格や思想傾向を分析し、支配層にとって「危険な人物」になりそうな子どもを見つけようというわけだ。

正直でも誠実でもない大人を真似する子どもに「道徳」を教科として教えても偽善を蔓延させるだけ 櫻井ジャーナル 2015.05.20
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505200000/

文部科学省は「道徳」を教科にし、検定教科書を作るのだという。子どもはおとなをデフォルメしてコピーするもので、子どもに問題があるなら、その原因はおとなにある。ところが、そのおとなに反省の色は見えない。そんな状態で「道徳」を教科にしても、「偽善」を教えることになるだけ。「洗脳」とも言える。
平然と嘘をつき、正直でも誠実でもない人物を首相にしている日本。不公正な政策で貧富の差を拡大させ、低所得者は教育を受ける権利さえ奪われている。公正でも公平でもない仕組みを利用して富を独占している強欲な人びとに節度があるとは言えない。

東電福島第一原発の事故で福島県をはじめ広範囲にわたる地域が放射性物質に汚染され、その影響が出ている可能性が高い。かなり深刻な事態だという声も現場から聞こえてくる。それにもかかわらず政府も東電も「安全だ」と叫び、汚染地域に人びとを留まらせてきた。マスコミも口をつぐんでいる。到底、生命を尊重しているとは言えない。
2003年にアメリカのジョージ・W・ブッシュ政権が嘘で始めたイラク侵攻作戦では約100万人が殺されたと推測されているが、その嘘を承知で侵略戦争を支持した政治家、官僚、「専門家」、記者、編集者などは訂正も謝罪もしていない。勿論、戦争犯罪で裁かれてもいない。
アメリカのイラクに対する先制攻撃もネオコン/シオニストが1992年に作成した国防総省のDPG(国防計画指針)草案に基づいている。2000年にPNACが公表した「米国防の再構築」はこの指針がベースで、その執筆者がブッシュ・ジュニア政権に入り、戦略を作り上げていたので、必然的な結果だ。
嘘を容認する人びとは、当然、歴史も直視しない。安倍政権は自分たちの妄想に合わせて歴史の教科書を書き直させようとしている。事実を語る人が現れると 彼らは「自虐」だと罵りながら耳を閉ざす。似たように反応するのがシオニストで、イスラエルが行ってきた破壊と虐殺を批判するユダヤ系の人に対して「自己 憎悪(Self-hating)」だと攻撃、歴史の書き換えにも熱心である。
日本の独善的な歴史教育の流れをさかのぼると、第2次世界大戦の前にあった京都学派と東大朱光会が見えてくる。朱光会が組織されたのは1931年で、当初の会長は春山作樹。のちに平泉澄へ引き継がれた。メンバーだった村尾次郎は後年、東京教育懇話会へ参加して戦後の教科書を攻撃、時野谷滋、鳥巣通明、山口康助のように、文部省入りしたメンバーもいる。
支配層にとって都合の良い物語を人びとの頭に植え付けようとしているのは教育以外にもある。「報道」と呼ばれているものだ。イラクへの軍事侵略だけでな く、中東、北アフリカ、ユーゴスラビア、ウクライナなどでの体制転覆プロジェクト、核戦争の挑発などアメリカの支配層が知られたくない話も伝えない。何しろ、日本の支配層はアメリカの支配層に従属することで自分たちの権力を維持している。

NHK、安保法案の国会審議を中継せず 2015年5月26日22時56分
http://www.asahi.com/articles/ASH5V76YDH5VUCVL02K.html
衆院本会議での安全保障関連法案審議の終盤、空席が目立つ自民党の議席=26日午後4時1分、飯塚晋一撮影
26日に始まった安全保障関連法案の国会審議を、NHKは中継しなかった。この日あったのは衆院本会議での代表質問など。NHK広報局は「必ず中継するのは施政方針演説などの政府演説とそれに関する代表質問というのが原則」と説明する。原則外のものはケース・バイ・ケースで対応しているという。27日の特別委員会は関心が高いので中継するという。
世界で侵略戦争を続ける勢力を抱える米国へ軍事的に従属するための法案成立を安倍政権は目指す 2015.06.01
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201506010000/
言うまでもなく、日本の進む方向はアメリカの戦略次第であり、日本の「エリート」はアメリカの支配層に従うだけである。4月27日に外務大臣の岸田文雄と防衛大臣の中谷元はニューヨークでアメリカのジョン・ケリー国務長官やアシュトン・カーター国防長官と会談して新しい「日米防衛協力指針(ガイドライン)」を発表したが、これもアメリカ側の命令に基づくもの。「安全保障法制」に関する国会の議論は儀式にすぎない。少なくとも安倍晋三政権はそう考えているだろう。
現在、アメリカを動かしている戦略は1992年に作成されたDPG(国防計画指針)の草案がベースで、アメリカを「唯一の超大国」と位置づけ、潜在的ライバル、つまり西ヨーロッパ、東アジア、旧ソ連圏、南西アジアを潰すという方針を示している。
この指針の基本的な考え方は、国防総省のシンクタンクONA(ネット評価室)で室長を務めてきたアンドリュー・マーシャルのもの。それに基づき、リチャード・チェイニー国防長官の下、ポール・ウォルフォウィッツ国防次官、I・ルイス・リビー、ザルメイ・ハリルザドといったネオコン人脈で作成したもので、「ウォルフォウィッツ・ドクトリン」とも呼ばれている。このウォルフォウィッツは1991年にシリア、イラン、イラクを殲滅すると話していたとウェズリー・クラーク元欧州連合軍(現在のNATO作戦連合軍)最高司令官は語っている。
1993年から2001年にかけてのビル・クリントン政権でネオコンは主導権を握ることができなかったが、大統領は個人的なスキャンダルに忙殺され、好戦的な方向へ政策が向かう。キーパーソンはマデリーン・オルブライトだと言えるだろう。
オルブライトは1997年にウォーレン・クリストファーから引き継ぐ形で国務長官に就任した。オルブライトはアフガニスタンで戦争を仕掛けたズビグネフ・ブレジンスキーの教え子で、バラク・オバマ政権で国家安全保障問題担当の大統領補佐官に指名されたスーザン・ライスの師でもある。また、オバマ大統領はブレジンスキーの教え子。
ブレジンスキーは1970年代後半、ジミー・カーター大統領の補佐官だった時、ソ連をアフガニスタンへ誘い込み、そこでイスラム武装勢力と戦わせるという秘密工作を考えた人物。ロシア制圧が目標で、そのカギを握る国がウクライナだと考えていた。この工作ではCIAが戦闘員を育成、支援しているが、その登録リストがアル・カイダと呼ばれ、そのスポンサーがサウジアラビアだ。
クリストファー長官の時代から「人権擁護団体」がユーゴスラビア政府の「人権侵害」を宣伝していたが、これらは間違った、あるいは不公正な情報。アメリカ政府も軍事介入には踏み切らなかった。状況が変わったのは、オルブライトがユーゴスラビア空爆を支持すると表明した1998年だ。1999年3月にNATOはユーゴスラビアを先制攻撃、5月には中国大使館を爆撃した。アメリカ政府は「誤爆」だとしているが、状況から考えて意図的な攻撃だった可能性はきわめて高い。
2000年にネオコン系シンクタンクのPNACは1992年のDPG草稿をベースにして「米国防の再構築」という報告書を公表、その中では東アジアを重要視している。この段階ではウラジミル・プーチンがロシア大統領になったばかりで、アメリカの傀儡だったボリス・エリツィンの路線を引き継ぐ、つまり属国の地位に留まると見られていた。中国も若手エリートを懐柔、洗脳することで傀儡化に成功したとアメリカ支配層は考えていたように見える。
そして2001年、ニューヨークの世界貿易センターとワシントンDCの国防総省本部庁舎(ペンタゴン)が攻撃される。多くの人びとが茫然自失になる中、アメリカ支配層は「アル・カイダ」を「テロリストの象徴」にし、あたかもイラクがアメリカをすぐにでも核攻撃するかのような宣伝を始め、2003年にはイラクを先制攻撃した。1991年にウォルフォウィッツが口にしたとおりの展開だ。
その後、アメリカはアル・カイダ/IS(イラクとレバントのイスラム首長国。ISIS、ISIL、IEIL、ダーイシュとも表記)を使ってリビアやシリアの体制転覆プロジェクトを始めた。リビアは既に成功したが、シリアの場合はロシアがNATOの直接介入を阻止したことで目的は達成できていない。イエメンでもアル・カイダを投入していたが、ここでも思惑通りに進まず、ここにきてサウジアラビアが直接介入、サウジアラビアを装ってイスラエルも攻撃に参加し、中性子爆弾を使用したとも言われている。この推測が正しく、ロシアや中国に対する「警告」のつもりなら、逆効果になるだろう。



昨年2月にネオコン/シオニストはウクライナの合法政権を暴力的に、憲法を無視したプロセスで倒したが、その時に使った武装集団はネオ・ナチ。NATOが連動してロシアと戦争する姿勢を見せてきたが、5月12日にはアメリカのジョン・ケリー国務長官がロシアのソチでウラジミル・プーチン大統領らと会談、ウクライナでの戦闘を終わらせるためにミンスク合意を支持する姿勢を明確にした。流れに変化が見られる。ネオコンの「ヨーダ」とも呼ばれるマーシャルが今年1月、92歳でONA室長を退任したことも戦争を遠ざける要素ではある。
しかし、ロシアの周辺で軍事力を増強している状況に変化はなく、戦争に前向きのフィリップ・ブリードラブは今でもNATO欧州連合軍最高司令官/在欧米空軍司令官の職にあり、今年2月には戦争に消極的なチャック・ヘーゲルから好戦的なアシュトン・カーターに交代、アメリカはミサイル巡洋艦のベラ・ガルフ、ミサイル駆逐艦のロス、トラクストン、フリゲート艦のテイラーなどを黒海に入れ、ロシア領海の間際を航行させるなど挑発している。
東アジアでの軍事的な緊張も高まり、日米に対抗するため、中国はロシアと軍事的な連携を強めている。カーター長官は2011年から13年にかけて国防副長官を務めた人物で、06年にはハーバード大学で朝鮮空爆を主張するなど、好戦的な姿勢を見せてきた。安倍首相を高揚させるタイプの人物だと言えるだろう。
その安倍首相は「安全保障法制」を推進、全世界で侵略戦争を始め、全面核戦争も辞さない姿勢を見せているアメリカの戦いに参加しようとしている。ネオコンと同じように、安倍政権も正気ではない。
おまけ
ラスト・リベンジ

本作は批評家から酷評されている。










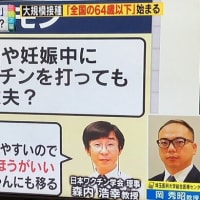
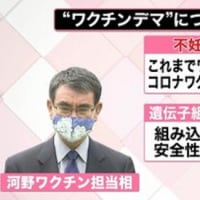

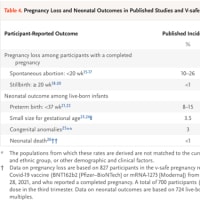
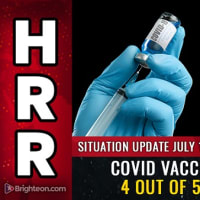



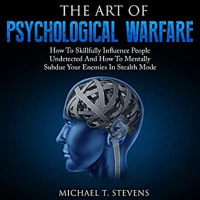

従う奴隷はエルサレム
その他の者はトサツ所送り