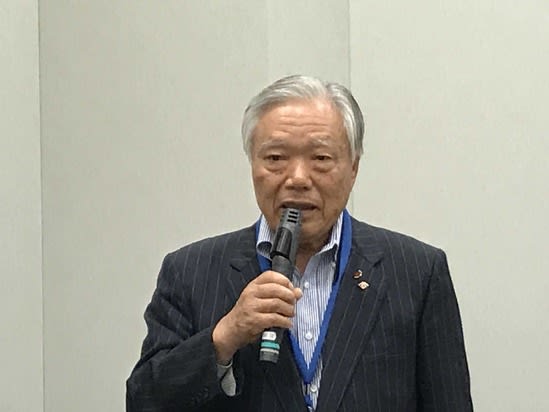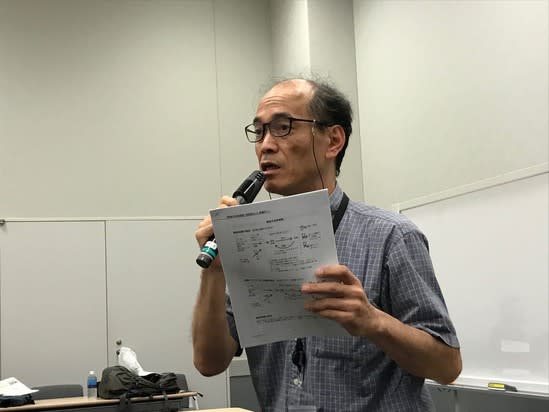痴漢や盗撮、児童買春までも 皇位継承で55万人に「棚ボタ」恩赦、時代遅れの遺物では
前田恒彦 | 元特捜部主任検事 10/22(火) 8:30
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191022-00147838/

(写真:西村尚己/アフロ)
即位礼正殿の儀が行われる10月22日に合わせ、政府の復権令が公布・施行される。皇位継承が国家的慶事であることは確かだが、もはや恩赦は時代遅れの遺物にほかならず、慣例のように行う必要などないはずだ。
恩赦の理由と実施内容
すなわち、恩赦を所管する法務省保護局は、なぜ今回実施するのか、次のように説明している。
「新しい令和の時代を迎え、即位の礼が行われます。この慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から、今般、恩赦を実施することとなりました」
出典:「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00006.html
そのうえで、「国民感情、特に犯罪被害者やその御遺族の心情等に配慮」したとして、次のとおり内容や範囲を絞り込んだ。
(1) 政令恩赦
罰金刑の執行を受け終わり、3年間再び処罰されていない者に対し、刑に処せられたため生じた資格の制限をなくす「復権」を一律に実施
(2) 特別基準恩赦
本人の出願に基づき、犯情や本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等を個別に審査して実施
(a) 病気等で長期間刑の執行が停止され、なお長期にわたり執行困難な者に対する「刑の執行の免除」
(b) 刑を受けたことが社会生活上の障害となっている罰金刑の執行終了者に対する「復権」
有罪の言渡しが確定した者に対して一律にその効力を失わせるといった「大赦(たいしゃ)」や、死刑を無期懲役に変更するといった「減刑」は実施されない。
刑法の規定により、罰金刑の執行を終えたあと、罰金以上の刑に処せられないで5年経過すれば、前科に伴う制裁措置として制限されていた資格が回復する。例えば、選挙違反事件で停止された公民権(選挙権や被選挙権)が復活するといったものだ。
今回の恩赦では、この5年を3年に短縮し、執行終了から3年経過していれば一律に復権させようというわけだ。
とはいえ、対象者は約55万人にも上る。反省の有無や悔悟の程度などを問わないから、まさしく「棚ボタ」だ。
しかも、罪種や言い渡された罰金額に制限はなく、内訳を見ると無免許運転や酒気帯び運転など道路交通法違反が65.2%、人身事故に基づく過失運転致死傷等が17.4%、暴行・傷害が3.3%、窃盗が2.6%となっている。
それ以外の罪名が11.4%に上るが、これには買収など公職選挙法違反に問われた約430人や、脅迫、器物損壊、建造物侵入、名誉毀損、賭博、威力業務妨害、海賊版配信、危険ドラッグ所持、ダフ屋、ストーカー、動物虐待といったさまざまな犯罪のほか、痴漢や盗撮、児童買春、淫行条例違反、児童ポルノ所持なども含まれる。
(1)の政令恩赦では、たとえ被害者のいる犯罪であっても、その意向を確認しないまま一律に復権が認められるわけで、国民感情や被害者らの心情等に配慮したという法務省の説明は苦しい。
合理的理由なし
そもそも、自由を奪い、労働を義務付ける懲役刑と比べると、罰金刑には犯罪者に対する感銘力が乏しい。「金を払って済んだ」と思われやすいし、家族や友人らに用立ててもらったものを納付してもかまわないからだ。
ある程度の資産があれば痛くも痒くもない金額だし、営業的な犯罪者には一種の税金のように見られて軽視されている。
略式起訴により公開法廷での正式裁判や被告人質問を受けず、事件記録の検討だけで罰金額が決められる場合がほとんどだから、裁判官の顔すら見ないで終わってしまう。
前科に伴う資格制限が併存することにより、こうした罰金刑でもある程度の感銘力が維持できているわけだ。
にもかかわらず、しかも恩赦制度そのものに何ら合理的な理由が見いだせない中、罰金刑の執行を受けて3年経過した者を一律に復権させるという政府の「配慮」は理解に苦しむ。ますます罰金刑が軽く見られるだけだ。
効果も疑問
そればかりか、今回の復権にはあまり意味がない。というのも、前科に伴う資格制限は禁錮以上の刑に処せられた場合が中心だからだ。例えば、懲役刑の執行猶予期間中は国家公務員や地方公務員になれないし、パスポートを発給されないこともある。
これに対し、「罰金以上」ということだと資格制限もかなり限られてくる。それも「任意的欠格事由」、すなわち「免許を与えないことがある」といったパターンがほとんどだ。
例えば、医師や歯科医師、薬剤師、看護師・准看護師などの場合、前科の有無を問わず国家試験を受けて合格することまではできるが、罰金刑だと執行終了から5年、禁錮刑や懲役刑だと10年、執行猶予付きだと猶予期間を経過していなければ免許を与えられないこともあり得る。また、すでに与えられている免許を取り消されたり、業務停止処分を受けるといったペナルティの可能性もある。
ただ、あくまで制度上の話であり、いずれも絶対というわけではなく、それこそ罰金止まりであれば犯した罪の内容次第でそうしたペナルティが見送られる場合のほうが多い。しかも、医師などの職業を選んでいないものには何の関係もない資格制限だ。
むしろ、一般の人からすると、交通違反や事故に伴う運転免許の取消しや停止、違反点数の累積がどうなるか気になるところだろう。しかし、これらは罰金刑の有無と無関係に下される行政処分にほかならず、復権の対象ではないから、失った免許が戻ってくるとか、違反点数がゼロになるといったこともない。
先ほどから挙げているように、選挙違反事件だと5年間は公民権が停止されるというのが罰金刑に対する典型的な資格制限と言える。今回の復権で実際に恩典を受けるのは、まさしく彼らということになるだろう。
先例踏襲はやめよ
そもそも、法務省は「慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進する」と言うが、国家的慶事などいつ起こるか分からず、自分が選ばれるかも分からないわけで、そうした不確実な目標に向かって更生の道を邁進するとは考えられない。
同じような犯罪に及んでも、運良く慶時に条件をみたしていれば対象となり、そうでなければ対象外となるわけで、明らかに不公平だ。
もし実施するのであれば、次のようなケースを前提としたうえで、個別の事情に応じ、限定的かつ慎重に適用されるべきだろう。
(i) 有罪が言い渡された当時と比べ、社会情勢や事情、法令が大きく変化した場合の救済策
(ii) 重病の受刑者や重い精神障害の受刑者、えん罪が疑われる受刑者らに対する救済策
少なくとも、恩赦を決定し、犯罪者に慈悲を与えることができる権力者の権威付けや、選挙違反に問われた政権支持者の公民権回復を図るといった政治的思わくに基づいて実施すべきものではない。
安易な先例踏襲はやめるべきだ。(了)
(参考)
拙稿「恩赦と懲戒免除 なぜあるのか」
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20180808-00092269/
前田恒彦 元特捜部主任検事
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。


呪われ史因果応報<本澤二郎の「日本の風景」(3471) 2019-10-19 23:41:59
https://ameblo.jp/honji-789/entry-12537537293.html
<源流は明治維新の天皇絶対主義=人権・自由のはく奪>
安倍晋三内閣は、人々に戦前の秘史を思い出させてくれる。田布施の歴史なのか、因果応報の戦前戦後の日本正史は、ことごとく負の連鎖を裏付けて余りあろう。源流は明治維新の天皇絶対主義にある。人々の人権・自由をはく奪した「近代化」は誤りであった。
今回の台風15号と19号の大自然の怒りとも関係があろう。「大量の放射能汚染物資を保管していた袋が、400ミリ豪雨で河川や海に流れた」と中国のネットで炎上、家族から「中国に帰れ」の呼びかけが飛び交っている。
この大量の放射能ゴミの垂れ流しのような事態は、フクシマ原発の1000個近いタンクの汚染水も、同じく海に流れだしていることを教えているが、当局は報道管制で蓋をかけている。
今も明治が生きている日本であろう。
<帝国憲法・国家神道・教育勅語=侵略・植民地主義=原爆投下>
明治の天皇神格化を実現した三本柱は、大日本帝国憲法・国家神道・教育勅語である。憲法と宗教と教育で人々を鉄の鎖で拘束したもので、そこから必然的に植民地・侵略戦争を可能にした。
日本の学校教育が決して教えない真実である。背後を天皇の官僚と財閥が固め、軍閥に道筋を示した。
朝鮮半島を植民地支配、ついで大陸に傀儡政権まで打ち立て、蛮行を繰り返した。その結果としての原爆投下であった。日本敗戦は、天皇絶対主義の行き着く先だった。これを自業自得という。
<戦後も天皇制存続=財閥・軍閥の復活=54基の原発>
敗戦は、自由と人権を悲願とする国民に、改革への機会と希望を与えるものだった。しかし、国民にその力はなかった。明治以来の天皇絶対主義に、人々の精神は粉々に打ち砕かれてしまっていた。
占領軍任せが、今日に尾を引いてしまった。悲劇による一大改革を推進する好機を逸してしまった。ことほど荒廃した国土と疲弊した国民が、1945年の日本だった。
当時の為政者もまた、自立する中での独立国を目指すという気概がなかった。近代化にそぐわない天皇制を存続させてしまった。まもなく朝鮮戦争で、解体されたはずの財閥が復活した。軍閥もまた、やけぼっくいに火がついてしまった。戦前を支配した天皇の官僚は、温存されてしまった。
国民は非戦の憲法9条を手にしたが、安倍晋三というA級戦犯の孫は、公然と破憲を貫いている。連立を組む公明党も「戦争党」に衣替えして、止めようとしない。
かくして54基もの原発が列島の隅々に建設された。その先に311が待ち構えていた。
<311東電福島原発崩壊=再稼働=放射能まみれ列島=関電疑獄>
311にうろたえた世界の政治指導者は、少なくない。ドイツのメルケル首相は、即座にドイツ原発の廃炉を決め、自然エネルギーに切り替えた。
昨今、各国は原発建設を取りやめている。アメリカも含めて。核をコントールできないし、これほど危険で、高価なエネルギーなどない。核武装に野心をたぎらせる安倍・自公内閣は、こともあろうに再稼働へと進軍、世界を驚かせている。
放射能汚染は、フクシマ原発の周囲30キロ圏や80キロ圏で抑え込まれた、という大嘘を信じる国民は、いまほとんどいない。
人々は、東京湾の魚も危ない、太平洋岸の魚はなおさらだ、と認識している。これもまた、日本政府の隠ぺい対策の成果である。
東京五輪開催にも暗雲が垂れ込めてきている。こうした懸念を払しょくしようとしてか、安倍の別動隊である維新の会が「汚染水を大阪湾に受け入れる」と言い出して、新たな怒りと反発を招いている。
放射能まみれ列島は、千葉県の水源地に投棄された1万トン以上の放射能汚染物資問題も、新たな火種となって、これを強行した俳優崩れの知事・森田健作への罷免の動きを本格化させている。
そして、ついに関電疑獄事件が発覚した。原発の闇が暴かれようとしている。
そこに、世界大不況下の10%消費税という大増税で、消費の著しい落ち込みが、あらゆる企業と会社員、貧困層の生活に襲い掛かっている。国民は、166億円の原始の皇位継承劇にも、スポーツ熱狂報道にも踊る情況ではない。暗い時代の予感がするばかりだ。因果応報に立ちすくんでいる!

2019年10月20日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
https://twitter.com/yuu2_memo/status/1185947600949673984
ウォーカー@yuu2_memo 8:55 - 20 d’oct. de 2019
この図は、興味深いですね。

https://twitter.com/KSN1HybmjjiCMoQ/status/1185591910586445824
けん@KSN1HybmjjiCMoQ 9:21 - 19 d’oct. de 2019
皆さんには、この日本、どのように見えるでしょうか?
私には、戦争で焦土と化した日本に見えます。
地震、豪雨、台風で疲弊した国民の姿に寄り添うことも無く、人権を抑圧し蹂躙する法案作りに余念がない政治。
国民より兵器、暮らしより重税、公平より差別、公正より不正。全ての価値観が歪んでる。
前田恒彦 | 元特捜部主任検事 10/22(火) 8:30
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191022-00147838/

(写真:西村尚己/アフロ)
即位礼正殿の儀が行われる10月22日に合わせ、政府の復権令が公布・施行される。皇位継承が国家的慶事であることは確かだが、もはや恩赦は時代遅れの遺物にほかならず、慣例のように行う必要などないはずだ。
恩赦の理由と実施内容
すなわち、恩赦を所管する法務省保護局は、なぜ今回実施するのか、次のように説明している。
「新しい令和の時代を迎え、即位の礼が行われます。この慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から、今般、恩赦を実施することとなりました」
出典:「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00006.html
そのうえで、「国民感情、特に犯罪被害者やその御遺族の心情等に配慮」したとして、次のとおり内容や範囲を絞り込んだ。
(1) 政令恩赦
罰金刑の執行を受け終わり、3年間再び処罰されていない者に対し、刑に処せられたため生じた資格の制限をなくす「復権」を一律に実施
(2) 特別基準恩赦
本人の出願に基づき、犯情や本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等を個別に審査して実施
(a) 病気等で長期間刑の執行が停止され、なお長期にわたり執行困難な者に対する「刑の執行の免除」
(b) 刑を受けたことが社会生活上の障害となっている罰金刑の執行終了者に対する「復権」
有罪の言渡しが確定した者に対して一律にその効力を失わせるといった「大赦(たいしゃ)」や、死刑を無期懲役に変更するといった「減刑」は実施されない。
刑法の規定により、罰金刑の執行を終えたあと、罰金以上の刑に処せられないで5年経過すれば、前科に伴う制裁措置として制限されていた資格が回復する。例えば、選挙違反事件で停止された公民権(選挙権や被選挙権)が復活するといったものだ。
今回の恩赦では、この5年を3年に短縮し、執行終了から3年経過していれば一律に復権させようというわけだ。
とはいえ、対象者は約55万人にも上る。反省の有無や悔悟の程度などを問わないから、まさしく「棚ボタ」だ。
しかも、罪種や言い渡された罰金額に制限はなく、内訳を見ると無免許運転や酒気帯び運転など道路交通法違反が65.2%、人身事故に基づく過失運転致死傷等が17.4%、暴行・傷害が3.3%、窃盗が2.6%となっている。
それ以外の罪名が11.4%に上るが、これには買収など公職選挙法違反に問われた約430人や、脅迫、器物損壊、建造物侵入、名誉毀損、賭博、威力業務妨害、海賊版配信、危険ドラッグ所持、ダフ屋、ストーカー、動物虐待といったさまざまな犯罪のほか、痴漢や盗撮、児童買春、淫行条例違反、児童ポルノ所持なども含まれる。
(1)の政令恩赦では、たとえ被害者のいる犯罪であっても、その意向を確認しないまま一律に復権が認められるわけで、国民感情や被害者らの心情等に配慮したという法務省の説明は苦しい。
合理的理由なし
そもそも、自由を奪い、労働を義務付ける懲役刑と比べると、罰金刑には犯罪者に対する感銘力が乏しい。「金を払って済んだ」と思われやすいし、家族や友人らに用立ててもらったものを納付してもかまわないからだ。
ある程度の資産があれば痛くも痒くもない金額だし、営業的な犯罪者には一種の税金のように見られて軽視されている。
略式起訴により公開法廷での正式裁判や被告人質問を受けず、事件記録の検討だけで罰金額が決められる場合がほとんどだから、裁判官の顔すら見ないで終わってしまう。
前科に伴う資格制限が併存することにより、こうした罰金刑でもある程度の感銘力が維持できているわけだ。
にもかかわらず、しかも恩赦制度そのものに何ら合理的な理由が見いだせない中、罰金刑の執行を受けて3年経過した者を一律に復権させるという政府の「配慮」は理解に苦しむ。ますます罰金刑が軽く見られるだけだ。
効果も疑問
そればかりか、今回の復権にはあまり意味がない。というのも、前科に伴う資格制限は禁錮以上の刑に処せられた場合が中心だからだ。例えば、懲役刑の執行猶予期間中は国家公務員や地方公務員になれないし、パスポートを発給されないこともある。
これに対し、「罰金以上」ということだと資格制限もかなり限られてくる。それも「任意的欠格事由」、すなわち「免許を与えないことがある」といったパターンがほとんどだ。
例えば、医師や歯科医師、薬剤師、看護師・准看護師などの場合、前科の有無を問わず国家試験を受けて合格することまではできるが、罰金刑だと執行終了から5年、禁錮刑や懲役刑だと10年、執行猶予付きだと猶予期間を経過していなければ免許を与えられないこともあり得る。また、すでに与えられている免許を取り消されたり、業務停止処分を受けるといったペナルティの可能性もある。
ただ、あくまで制度上の話であり、いずれも絶対というわけではなく、それこそ罰金止まりであれば犯した罪の内容次第でそうしたペナルティが見送られる場合のほうが多い。しかも、医師などの職業を選んでいないものには何の関係もない資格制限だ。
むしろ、一般の人からすると、交通違反や事故に伴う運転免許の取消しや停止、違反点数の累積がどうなるか気になるところだろう。しかし、これらは罰金刑の有無と無関係に下される行政処分にほかならず、復権の対象ではないから、失った免許が戻ってくるとか、違反点数がゼロになるといったこともない。
先ほどから挙げているように、選挙違反事件だと5年間は公民権が停止されるというのが罰金刑に対する典型的な資格制限と言える。今回の復権で実際に恩典を受けるのは、まさしく彼らということになるだろう。
先例踏襲はやめよ
そもそも、法務省は「慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進する」と言うが、国家的慶事などいつ起こるか分からず、自分が選ばれるかも分からないわけで、そうした不確実な目標に向かって更生の道を邁進するとは考えられない。
同じような犯罪に及んでも、運良く慶時に条件をみたしていれば対象となり、そうでなければ対象外となるわけで、明らかに不公平だ。
もし実施するのであれば、次のようなケースを前提としたうえで、個別の事情に応じ、限定的かつ慎重に適用されるべきだろう。
(i) 有罪が言い渡された当時と比べ、社会情勢や事情、法令が大きく変化した場合の救済策
(ii) 重病の受刑者や重い精神障害の受刑者、えん罪が疑われる受刑者らに対する救済策
少なくとも、恩赦を決定し、犯罪者に慈悲を与えることができる権力者の権威付けや、選挙違反に問われた政権支持者の公民権回復を図るといった政治的思わくに基づいて実施すべきものではない。
安易な先例踏襲はやめるべきだ。(了)
(参考)
拙稿「恩赦と懲戒免除 なぜあるのか」
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20180808-00092269/
前田恒彦 元特捜部主任検事
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。


呪われ史因果応報<本澤二郎の「日本の風景」(3471) 2019-10-19 23:41:59
https://ameblo.jp/honji-789/entry-12537537293.html
<源流は明治維新の天皇絶対主義=人権・自由のはく奪>
安倍晋三内閣は、人々に戦前の秘史を思い出させてくれる。田布施の歴史なのか、因果応報の戦前戦後の日本正史は、ことごとく負の連鎖を裏付けて余りあろう。源流は明治維新の天皇絶対主義にある。人々の人権・自由をはく奪した「近代化」は誤りであった。
今回の台風15号と19号の大自然の怒りとも関係があろう。「大量の放射能汚染物資を保管していた袋が、400ミリ豪雨で河川や海に流れた」と中国のネットで炎上、家族から「中国に帰れ」の呼びかけが飛び交っている。
この大量の放射能ゴミの垂れ流しのような事態は、フクシマ原発の1000個近いタンクの汚染水も、同じく海に流れだしていることを教えているが、当局は報道管制で蓋をかけている。
今も明治が生きている日本であろう。
<帝国憲法・国家神道・教育勅語=侵略・植民地主義=原爆投下>
明治の天皇神格化を実現した三本柱は、大日本帝国憲法・国家神道・教育勅語である。憲法と宗教と教育で人々を鉄の鎖で拘束したもので、そこから必然的に植民地・侵略戦争を可能にした。
日本の学校教育が決して教えない真実である。背後を天皇の官僚と財閥が固め、軍閥に道筋を示した。
朝鮮半島を植民地支配、ついで大陸に傀儡政権まで打ち立て、蛮行を繰り返した。その結果としての原爆投下であった。日本敗戦は、天皇絶対主義の行き着く先だった。これを自業自得という。
<戦後も天皇制存続=財閥・軍閥の復活=54基の原発>
敗戦は、自由と人権を悲願とする国民に、改革への機会と希望を与えるものだった。しかし、国民にその力はなかった。明治以来の天皇絶対主義に、人々の精神は粉々に打ち砕かれてしまっていた。
占領軍任せが、今日に尾を引いてしまった。悲劇による一大改革を推進する好機を逸してしまった。ことほど荒廃した国土と疲弊した国民が、1945年の日本だった。
当時の為政者もまた、自立する中での独立国を目指すという気概がなかった。近代化にそぐわない天皇制を存続させてしまった。まもなく朝鮮戦争で、解体されたはずの財閥が復活した。軍閥もまた、やけぼっくいに火がついてしまった。戦前を支配した天皇の官僚は、温存されてしまった。
国民は非戦の憲法9条を手にしたが、安倍晋三というA級戦犯の孫は、公然と破憲を貫いている。連立を組む公明党も「戦争党」に衣替えして、止めようとしない。
かくして54基もの原発が列島の隅々に建設された。その先に311が待ち構えていた。
<311東電福島原発崩壊=再稼働=放射能まみれ列島=関電疑獄>
311にうろたえた世界の政治指導者は、少なくない。ドイツのメルケル首相は、即座にドイツ原発の廃炉を決め、自然エネルギーに切り替えた。
昨今、各国は原発建設を取りやめている。アメリカも含めて。核をコントールできないし、これほど危険で、高価なエネルギーなどない。核武装に野心をたぎらせる安倍・自公内閣は、こともあろうに再稼働へと進軍、世界を驚かせている。
放射能汚染は、フクシマ原発の周囲30キロ圏や80キロ圏で抑え込まれた、という大嘘を信じる国民は、いまほとんどいない。
人々は、東京湾の魚も危ない、太平洋岸の魚はなおさらだ、と認識している。これもまた、日本政府の隠ぺい対策の成果である。
東京五輪開催にも暗雲が垂れ込めてきている。こうした懸念を払しょくしようとしてか、安倍の別動隊である維新の会が「汚染水を大阪湾に受け入れる」と言い出して、新たな怒りと反発を招いている。
放射能まみれ列島は、千葉県の水源地に投棄された1万トン以上の放射能汚染物資問題も、新たな火種となって、これを強行した俳優崩れの知事・森田健作への罷免の動きを本格化させている。
そして、ついに関電疑獄事件が発覚した。原発の闇が暴かれようとしている。
そこに、世界大不況下の10%消費税という大増税で、消費の著しい落ち込みが、あらゆる企業と会社員、貧困層の生活に襲い掛かっている。国民は、166億円の原始の皇位継承劇にも、スポーツ熱狂報道にも踊る情況ではない。暗い時代の予感がするばかりだ。因果応報に立ちすくんでいる!

2019年10月20日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
https://twitter.com/yuu2_memo/status/1185947600949673984
ウォーカー@yuu2_memo 8:55 - 20 d’oct. de 2019
この図は、興味深いですね。

https://twitter.com/KSN1HybmjjiCMoQ/status/1185591910586445824
けん@KSN1HybmjjiCMoQ 9:21 - 19 d’oct. de 2019
皆さんには、この日本、どのように見えるでしょうか?
私には、戦争で焦土と化した日本に見えます。
地震、豪雨、台風で疲弊した国民の姿に寄り添うことも無く、人権を抑圧し蹂躙する法案作りに余念がない政治。
国民より兵器、暮らしより重税、公平より差別、公正より不正。全ての価値観が歪んでる。