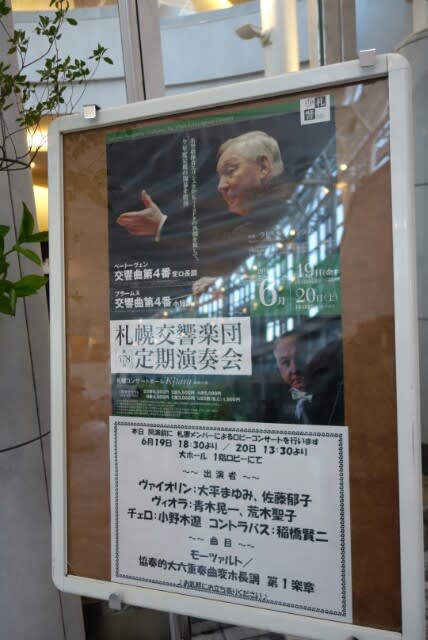愛知祝祭管のBlu-rayディスクを鑑賞しながら、強烈に感動した場面のひとつがこれ。
トロンボーン奏者×3 + テューバ奏者、そしてオーボエ&ファゴット隊の勇姿ももちろんだが、その手前、空中に浮かぶ謎の物体に注目して欲しい。アクロバット飛行中のUFOではない。これこそ2014年10月24日に行われた愛知祝祭管コンサートのすべての音を捉えた三点吊りのワンポイントマイクなのである。
ワーグナー~バッハ~ブルックナーと編成も大きさも異なる3つのプログラムを補助マイクなしのワンポイントで録るというのは、大きな挑戦ではあるが、仕込みと撤収の時間が僅かしかない、という条件から、唯一の選択肢だった。そして、この背水の陣は見事な結果を生み出した。
オーケストラだけの録音でも高い技術とセンスの要求される場面、P席=ステージ後方の高所からのコーラス、パイプオルガン、ステージ前方のヴァイオリン独奏も含めて、すべてを理想に近い録音を成し遂げたエンジニアの小伏和宏氏(ワオンレコード)に、改めて敬意を表したい。

以下、ワオンレコードのホームページに掲載されている録音データとエンジニア小伏和宏氏のコメントを転載する。
CDをお買い求めの方、これから求められる方には、以下をお読み頂くことで、より深く味わいつつ演奏をお楽しみ頂けるはずだ。

タワーレコード オンライン http://tower.jp/item/3776402/ブルックナー:-交響曲第8番(ハース版),-他
かもっくすレーベル OAF-1410
(2015年1月25日リリース) 税別¥2,778
録音日:2014年10月26日
場所:愛知県芸術劇場コンサートホール
Recording, Edit:小伏和宏
Cover design:小伏和宏
《DSD recording》
Microphone:MBHO MBP604/KA100DK
Method:OSS (Buffled stereo)
Pre-amp:Grace Design model 201
Recorder:KORG MR-1000 with Power supply:FSP 150W+Capacitor
Monitor:Grace Design m902B + Sennheiser HD580
《96kHz 24bit PCM editing》
DDC:Weiss Saracon-DSD
Audio-I/O:Weiss AFI1
Monitor:Waon Reference Monitor
■録音のこだわり
事前の下見がかなわなかった上に、仕込に許された時間が1時間しかなく、しかも舞台転換も超短時間、完全撤収も30分(結局伸ばしてもらえましたが…)の予定だったので、舞台上にスポットマイクを置くことが困難で、三点吊りのマイクだけで収録せざるを得ない状況でした。さらにフルオーケストラだけでなく、パイプオルガン、オルガンギャラリーの合唱団もそのマイクセットで収録しなければならなかったのです。音場再現だけを考えれば単一指向性マイクを使ったORTF法が適応できそうですが、この方法は低音が減衰してしまいせっかくのブルックナーのシンフォニーやパイプオルガンの迫力に水を差します。低音までフラットに録るには無指向性のマイクを使わなくてはなりません。舞台配置の関係でマイクから見た音源が左右それぞれ80°つまり左右見開き160°ほどにも広がっていましたので、140°までならリニアな音場再現ができるA-B法ではやや苦しい。マイク四本でPhilips方式も考えましたが、仕込時間が充分にありません。結局悪あがきはやめて、こういう状況での収録も視野に考案されたOSS(Optimal Stereo Signal)法を採用してマイク2本だけで録ることにしました。マイクにはMBHO社製高域補正型の無指向性マイクを、バッフルには不要な櫛形干渉が起きないSchneider Disc(やはりMBHO社製)を使用しました。結果的にこれが大当たりで、音質・音場再現ともに充分満足できる録音が出来たと思います。とても協力的な愛知県芸術劇場の舞台スタッフのおかげもあって、熱のこもった名演をなんとかお届けすることが出来ました。ぜひお楽しみください。