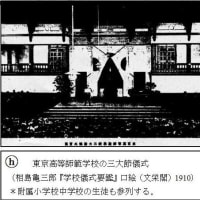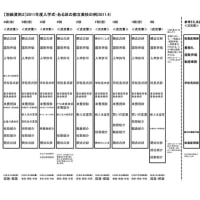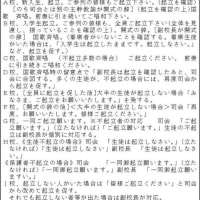◎「セメダイン」という商品名の由来
時枝誠記の言語過程説について紹介している途中だが、いったん、話題を変える。
先月二九日、インターネット・ニュース「ねとらぼ」で、「幻のセメダイン」が発見されたという記事に接した。まず、これを引用してみよう。
戦前に売られていたという幻の接着剤「セメダインB」がTwitter経由でセメダイン社に寄贈され、同社公式アカウントも「実在したんだ!」「鳥肌が立っています…」と驚きのツイートを連投しています。
「セメダインB」戦前に販売されていた接着剤。セメダイン社にも実物は存在せず、資料もほとんど残っていなかったといいます。
ことの起こりは8月下旬、そんな「セメダインB」と同時期に販売されていた初期モデルの「セメダインC」を偶然にも発掘したTwitterユーザーが、同社に現物を寄贈したことで話題を呼びました。それから数日後、ニュースを目にした他の方が今度は「セメダインB」を寄贈。さらにセメダインのもとになったというイギリスの接着剤「メンダイン」まで同社の元に渡りました。
同社公式アカウントはメンダインからつらなるセメダインの歴史をつづっています。メンダインはセメダインの創業当時(1923年)の日本市場を席巻していた接着剤。このメンダインを国産接着剤で「攻め」出そうという気概から、「セメダイン」という名前が決まったのだといいます。
寄贈された「セメダインB」「C」の今後について同社に尋ねたところ「実はまだ決まっていません」とコメント。「貴重な資料ですので、社内で慎重に話し合いを進めています」と述べました。
またTwitter経由で歴史的資料が同社に贈られたことについては、「お二方ともご厚意で寄贈してくださいまして、心から感謝しております」と感謝を述べると同時に、「Twitterのおかげで、こうして社員すら実態を知らなかった資料に触れることができたことに感動しております。また、その感動をTwitterの皆さんと共有できたことに喜びを感じております」とコメントしています。
なお、記事が公開された本日9月29日は「く(9)っつく(29)」で「接着の日」なのだとか。同社のTwitterでは、接着剤にまつわるさまざまな豆知識がいつもより多めに投稿されているようです。
この記事を読んで、むかし古書店で、『セメダイン五十年史』という本を買い求めたことを思い出した。探してみると、すぐに見つかった。奥付には、昭和四八年(一九七三)一一月、セメダイン株式会社発行、「非売品」とあった。
同書は、その一八~二〇ページで、「セメダイン」という商品名の由来を、次のように解説している。
「セメダイン」の由来
輪入品を「攻め」(セメ)出す
まさに徒手空拳の身で、化学接着剤の国産化に挑戦する今村〔善次郎〕青年の心意気は、まことに壮というべきであったが、〝ローマは一日にして成らず〟とか、彼のめざす外国製品を打ち負かすに足る製品は、そう簡単には生まれてこなかった。
くる日も、くる日も、全身「のり」にまみれての研究生活に明け暮れた。一方ではワックスを売り、靴ずみを売り、あるいは夫人の仕立て内職の収入に助けられながら糊口をしのいで、 夫唱婦随の必死の努力が続けられた。
そのころ、性能の優秀と目された輸入品はすべてチューブ詰めであり、これを可能とする「化学のり」の開発が結局最大の眼目であった。しかしチューブ詰め作業については、それまでもワックスを充填してきた経験もあり、善次郎にはそれほど困難とは思えなかったが、強力な接着力を持ち、しかもチューブ詰めにしても容易に固まらない溶液型「のり」の生産は、やはりなかなかに至難なことであった。
悪戦苦闘のすえに、善次郎がまがりなりにも外国製品に太刀打ちのできる製品として、国産接着剤の製造に成功したのは、研究を開始して四年後の大正十二年〔一九二三〕秋のことである。
その年の十一月、彼はこの苦心の製品に「セメダイン」と命名し、谷中初音町〈ヤナカハツネチョウ〉の住居を研究室兼工場兼販売店として、細々ながらも初の国産接着剤の製造販売を開始したのである。すなわち正確には、これが五十年前における当社発祥の真の姿なのである。
なお、発売にあたって商品名とした「セメダイン」は、今日では当社の社名そのものであり、また一般には、いまや接着剤の代名詞のごとくなじみの深いものとなったが、伝えられる命名の由来はおよそ次のようなものである。
そもそも「セメダイン」の語源は、結合材としての「セメント」と、力の単位を現わす「ダイン」とによる造成語で、「強い結合、接着」を意味するというのが通説になっている。しかし一説には、創業当時に市場で隆盛をきわめていたイギリス製の「メンダイン」以下の輸入品を、市場から「攻め」(セメ)出す出すという意味から、外国製品駆逐の闘志を込めて「セメダイン」の命名になったということである。
まさに創業者の心意気のほどを伝えて面白く、また味わい深い命名であったというべきである。
今日、これほどに人口に膾炙【かいしや】した製品名は他に類を見ないほどであるが、われわれはこの事実を誇りに思うと同時に、その製品の知名度にともなう責任の重さを常に心の底に銘記しておくべきである。
なお、今村善次郎の命名になるこの「セメダイン」という名称が、いわゆる商標として正式に登録されたのは、これよりかなり後年、昭和六年〔一九三一〕七月のことである。
次回は、セメダイン株式会社の創業者・今村善次郎(一八九〇~一九七一)について紹介する。