◎これを国語学の入門書と呼びたい(時枝誠記)
根来司著『時枝誠記 言語過程説』(明治書院、一九八五)から、「第二十一 現代の国語学」を紹介している。本日は、その二回目。
二
さてこの『現代の国語学』のはしがきは、次のように書きはじめられる。
《現代の国語学については、嘗て、「国語学史」(昭和十五年、岩波書店刊)の中で、第五期として、その素描を試みたことがある。それとは別に、「国語学原論」(昭和十六年、岩波書店刊)「同続篇」(同三十年、同書店刊)において、私の抱く言語観即ち言語過程説に基づく国語学の別個の体系を組織することを試みて来た。本書は、右の言語過程説の体系を、現代の国語学の中に位置づけるために、第一部において、明治以後の国語学の概観を試み、第二部において、言語過程説に基づく国語学の輪廓を述べようとした。両者は、それぞれ、別個の独立した記述のやうに見られるが、もし、読者が、この両者を合せて、言語過程説の体系が、明治以後の国語学の中で、何故に成立し、どのやうに交渉し、どのやうに位置づけられるかを理解されるならば、それは、正しく著者の本望といふべきである。
もし、これを、各個別々に見るならば、第一部の「近代言語学と国語学」は、「国語学史」の現代の部の史的叙述を、立体的な鳥瞰図に改め、現代国語学の展望をなすものであり、第二部の「言語過程説に基づく国語学」は、過程説理論への入門的記述として、ともに、国語学の初心者への啓蒙を意図しようとするのである。》
時枝博士に従うと、この書は最初国語学概論という書名で、言語過程説の理論によって貫く国語学の体系を記述することを計画したようであるが、それよりも自分の理論が正しく理解されるためにはこれを明治以降の国語学全体の中に位置づけて、それとの連関において理解されることが必要であると考えて、書名も現代の国語学と改め、はしがきに述べたようなことを構想したという。しかし、そのとおりにならなかったことをあとがきに、
《本書の執筆を進めて行くうちに、その「はしがき」に示したやうな方針、即ち本書を、現代国語学の総覧として役立たせるやうに、記述するといふことは、大変な仕事であると同時に、そのことに、どれだけの意味があらうかといふ疑ひの気持ちが起きて来た。最初の方針を実現するには、なほ多くの問題と、学者とその研究業績とに触れなければならないのであるが、それは、短時日で成就出来るとも考へられず、多くの重要事項を省略してしまつたので、入門書として見れば、極めて不完全なものが出来上つてしまった。しかし、その目的のためならば、今日、「日本文学大辞典」(新潮社刊)や「国語学辞典」(東京堂刊)等が、その要望を、十分に満たして呉れるであらう。
最初の方針にも拘はらず、私が、ひそかに意図したものは、それとは、全然、別のものであったやうである。そのことを、稿を進めて行くうちに、次第に自覚するやうになつて、筆は、自ら、その方向を変へて行つた。その方向の一つは、本書によつて、現代の国語学を概説する場合の、一つの方式を試みてみたいといふことであつた。そのためには、一つの学問の体系としての現代の国語学を、それを成立させてゐると考へられる諸要素に分析することである。このことは、学史的に迎ることによつても記述することが出来るのであるが、もつと体系的に、国語学の全機構を解体してみることが必要であると感じた。
次に、考へられたことは、現代の国語学を、冷酷なまでに、そのぎりぎりの線に追ひつめ、その成立の根源をつきとめようとすることである。このやうな仕事は、今までに、誰かによつて、既に試みられてゐなければならない答のことであつたのであるが、それが、なされなかつたのは、今までの国語学の体系が、一つの至上命令のやうに、殆ど疑はれることなく、過ぎて来たためである。もし、読者が、現代の国語学に踏み入つて、そこに、突き破ることも、乗り越えることも出来ない壁を見出し、慄然たる感を抱くであらう時には、恐らく、第二部の言語過程説の理論は、それらの人々に、一つの突破口としての役を果すであらう。第二部は、いはば、現代の国語学から脱出しようとする、私のあがきの記録ででもあるのである。
結局、本書は、最初の方針に反して、読者を、知識の世界よりも、思索の世界へ誘ひ込む書になつてしまつたのである。しかし、私は、これをも、敢へて国語学の入門書と呼びたいのである。》
というふうに述べている。もはや明らかなように時枝博士は日本人がどのように日本語というものを考えたか、日本人に日本語というものがどのように意識されて来たかをさぐる『国語学史』(昭和十五年)から出発して、鎌倉時代以来連綿として継承され、江戸時代に至って学者の手によって大成された言語学説を体系化して、言語過程説を唱え国語学界に大きな波紋を投げかけた。これは言語の本質を言語主体の表現、理解の行為であるとするもので、『国語学原論』(昭和十六年)にはその成立と展開とがまとめられている。この時枝博士の学説はヨーロッパの言語学説との真剣な対決を通じて築かれたものであったので、よく私たちの言語の本質の深奥に触れえたのである。【以下、次回】


















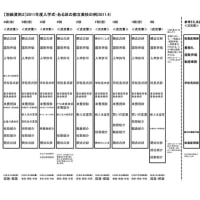
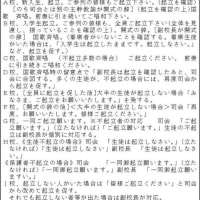








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます