こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。
先週の日曜日に続いて今日も模擬試験ですが雨にならなくて良かったです。夏休みの猛勉強の成果が現れると思います。
小4の算数の教科書にはドイツとカナダの割り算の筆算のやり方が載っていて、国によっていろいろな筆算方法があることが分かります。
さらに、割り算の記号もいくつかあります。日本では「÷」が使われていますが、ドイツでは「:」を使っていて、その他に「/」もあります。下図はドイツのゲッチンゲンで購入したもので、裏は数学者ガウスの肖像で、表には4つの計算式が並べてあって、その一番上にある式は、48-12:3=44 と書いてあり、ドイツの割り算記号が、「:」であることが分かります。

▲ガウスの計算カードにある割り算記号
そこで、どの国でどの記号を使っているのかネットで調べてみたのですが、あまりはっきりしません。日本でお馴染みの「÷」はイギリスのニュートンがよく使ったので広まったということで、イギリス、アメリカで使われているようです。(となると、大英帝国の諸国も「÷」でしょうか)
「:」のほうはドイツの大数学者ライプニッツが使い始めたようで、オランダ、フランスなどヨーロッパ大陸諸国で使われています。ここにもニュートンvsライプニッツの関係があるようです。そして、それらの国々の植民地であったインドネシア(オランダの植民地だった)、ベトナム(フランスの植民地だった)も「:」を使っています。
日本は江戸時代後期からオランダを通してヨーロッパ知識を吸収しましたが、どうして割り算記号がイギリス派になったのでしょうか。不思議なことがあるものです。
先週の日曜日に続いて今日も模擬試験ですが雨にならなくて良かったです。夏休みの猛勉強の成果が現れると思います。
小4の算数の教科書にはドイツとカナダの割り算の筆算のやり方が載っていて、国によっていろいろな筆算方法があることが分かります。
さらに、割り算の記号もいくつかあります。日本では「÷」が使われていますが、ドイツでは「:」を使っていて、その他に「/」もあります。下図はドイツのゲッチンゲンで購入したもので、裏は数学者ガウスの肖像で、表には4つの計算式が並べてあって、その一番上にある式は、48-12:3=44 と書いてあり、ドイツの割り算記号が、「:」であることが分かります。

▲ガウスの計算カードにある割り算記号
そこで、どの国でどの記号を使っているのかネットで調べてみたのですが、あまりはっきりしません。日本でお馴染みの「÷」はイギリスのニュートンがよく使ったので広まったということで、イギリス、アメリカで使われているようです。(となると、大英帝国の諸国も「÷」でしょうか)
「:」のほうはドイツの大数学者ライプニッツが使い始めたようで、オランダ、フランスなどヨーロッパ大陸諸国で使われています。ここにもニュートンvsライプニッツの関係があるようです。そして、それらの国々の植民地であったインドネシア(オランダの植民地だった)、ベトナム(フランスの植民地だった)も「:」を使っています。
日本は江戸時代後期からオランダを通してヨーロッパ知識を吸収しましたが、どうして割り算記号がイギリス派になったのでしょうか。不思議なことがあるものです。










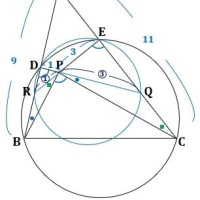
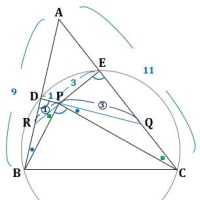
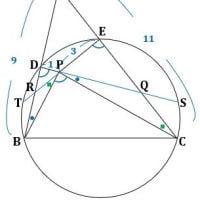
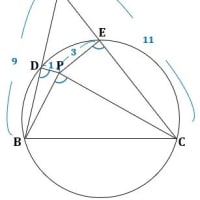



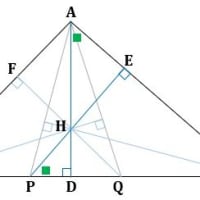
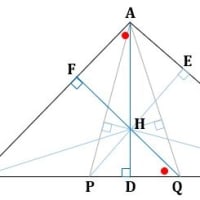
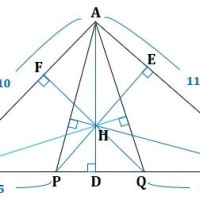
大英帝国は一つ
書くなら、イギリス連邦