こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。
中2の英語教科書に、
These rules protect the islands’ plants and animals.
(これらの規則は(小笠原)諸島の動植物を守っています)
という文があります。
この islands’ は、「島」を意味する island の複数形の 所有格 を表しますが、このような apostrophe(アポストロフィー)(’) を使った 所有格 の 綴り字 について、 オックスフォード実例現代英語用法辞典 に、
● 単数形の名詞+’s
my father’s car (父の車)
● 複数形の名詞+’
my parents’ house (私の両親の家)
● 不規則変化の複数形名詞+’s
the children’s room (子供たちの部屋)
men’s clothes (紳士服)
women’s rights (女性の権利)
an old people’s home (老人ホーム)
と説明しています。
さらに、語尾が -s で終わる単数形の名詞では、 Dickens’s novel(ディケンズの小説)や Mr Lewis’s dog(ルイスさんの犬)のように ’s を付けるほうが一般的であるものの、特に文学・古典上の名前には、 Socrates’ ideas(ソクラテスの考え)のように、単に ’ を付けることもあると記しています。
ちなみに、「英語の歴史から考える英文法の「なぜ」」(朝尾幸次郎著)によると、 アポストロフィー という言葉をはじめて使ったのは シェイクスピア で、『恋の骨折り損』(Love’s Labour’s Lost) にある
You find not the apostraphas, and so miss the accent.
(あなたはアポストロフィーを見落とすので言葉にめりはりがないのです)
を紹介しています。
「英語の歴史から考える英文法の「なぜ」」 は、とても面白く役に立つ本です。興味のある方は、手に取ってみてください。
中2の英語教科書に、
These rules protect the islands’ plants and animals.
(これらの規則は(小笠原)諸島の動植物を守っています)
という文があります。
この islands’ は、「島」を意味する island の複数形の 所有格 を表しますが、このような apostrophe(アポストロフィー)(’) を使った 所有格 の 綴り字 について、 オックスフォード実例現代英語用法辞典 に、
● 単数形の名詞+’s
my father’s car (父の車)
● 複数形の名詞+’
my parents’ house (私の両親の家)
● 不規則変化の複数形名詞+’s
the children’s room (子供たちの部屋)
men’s clothes (紳士服)
women’s rights (女性の権利)
an old people’s home (老人ホーム)
と説明しています。
さらに、語尾が -s で終わる単数形の名詞では、 Dickens’s novel(ディケンズの小説)や Mr Lewis’s dog(ルイスさんの犬)のように ’s を付けるほうが一般的であるものの、特に文学・古典上の名前には、 Socrates’ ideas(ソクラテスの考え)のように、単に ’ を付けることもあると記しています。
ちなみに、「英語の歴史から考える英文法の「なぜ」」(朝尾幸次郎著)によると、 アポストロフィー という言葉をはじめて使ったのは シェイクスピア で、『恋の骨折り損』(Love’s Labour’s Lost) にある
You find not the apostraphas, and so miss the accent.
(あなたはアポストロフィーを見落とすので言葉にめりはりがないのです)
を紹介しています。
「英語の歴史から考える英文法の「なぜ」」 は、とても面白く役に立つ本です。興味のある方は、手に取ってみてください。










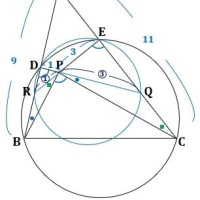
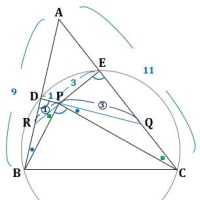
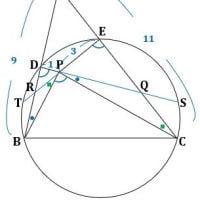
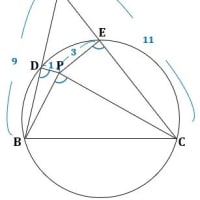



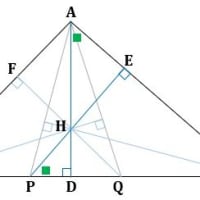
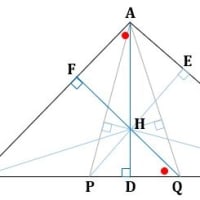
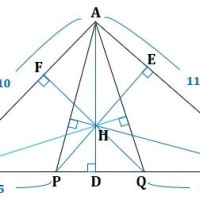

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます