介護報酬から見ると。
4月は診療報酬と介護報酬の同時改定であることはご存知のことと思う。
この介護報酬について知らない事が多過ぎる。
多過ぎると言うより知らなくても良かったと言った方が正解かもしれない。
しかし、今回はそうも言っていられない。
何と言っても、これから増えるのは高齢者であり、高齢者の場合、医療と介護の切り分けが難しいからだ。
少し介護報酬改定の様子も気にして欲しい。
先ず、今回の介護報酬改定で1.2%のアップが決まっている。
内訳は在宅が1%で施設が0.2%の振り分けとなっている。
ここも少し変な話である。
この1.2%は、今年の3月でなくなる「介護職員処遇改善交付金相当分」の1,900億円の補填として当初2%相当のアップが言われていた。
それが1.2%に圧縮されたのは仕方ないが、振り分けとして、在宅が1%で施設が0.2%と差が付くのが納得いかない。
介護従事者の人数割りじゃないのか。
さらに、今回は在宅重視として配分したとある。
それじゃ、「介護職員処遇改善交付金相当分」は関係がなかったって事になる。
そんな議論をしても、世の中は常に都合が良くできている。
その在宅であるが、新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)」と「複合型サービス」の2つのサービスが追加となる。
前者は、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行なうサービスとある。
後者は、従来の小規模多機能施設と訪問介護を複合させたタイプとある。
小規模多機能施設では、デイサービスとショートステイ及び訪問介護が一体となって提供されている。
ここに訪問看護を追加しようと言うものだ。
この2つに共通するのは看護師の存在である。
介護サービスには医療関係者の関与が薄い。
そこに医療関係者として看護師を補う体制の整備だ。
さらに、これに特定看護師制度なども加わると、いよいよ持って在宅の領域から薬剤師が締め出されないかと危惧する。
在宅療養を支えているのは医師でも看護師でもない。
ケアマネジャーや介護事業者でもないと思う。
在宅療養を支えているのは「薬」と「食べ物」である。
真に活用すべきは薬剤師と管理栄養士の存在なくしては成り立たない。
私のセミナーである方から質問があった。
「国は在宅を薦めているが、在宅になると今以上に医療費が膨らむのではないのか」
確かにそう思う。
なぜなら在宅が一番の贅沢のような気がするからだ。
出来る事ならあらゆるサービスを活用してでも自宅で往生したい。
家族が許してくれるなら。
目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!
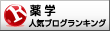
4月は診療報酬と介護報酬の同時改定であることはご存知のことと思う。
この介護報酬について知らない事が多過ぎる。
多過ぎると言うより知らなくても良かったと言った方が正解かもしれない。
しかし、今回はそうも言っていられない。
何と言っても、これから増えるのは高齢者であり、高齢者の場合、医療と介護の切り分けが難しいからだ。
少し介護報酬改定の様子も気にして欲しい。
先ず、今回の介護報酬改定で1.2%のアップが決まっている。
内訳は在宅が1%で施設が0.2%の振り分けとなっている。
ここも少し変な話である。
この1.2%は、今年の3月でなくなる「介護職員処遇改善交付金相当分」の1,900億円の補填として当初2%相当のアップが言われていた。
それが1.2%に圧縮されたのは仕方ないが、振り分けとして、在宅が1%で施設が0.2%と差が付くのが納得いかない。
介護従事者の人数割りじゃないのか。
さらに、今回は在宅重視として配分したとある。
それじゃ、「介護職員処遇改善交付金相当分」は関係がなかったって事になる。
そんな議論をしても、世の中は常に都合が良くできている。
その在宅であるが、新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)」と「複合型サービス」の2つのサービスが追加となる。
前者は、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行なうサービスとある。
後者は、従来の小規模多機能施設と訪問介護を複合させたタイプとある。
小規模多機能施設では、デイサービスとショートステイ及び訪問介護が一体となって提供されている。
ここに訪問看護を追加しようと言うものだ。
この2つに共通するのは看護師の存在である。
介護サービスには医療関係者の関与が薄い。
そこに医療関係者として看護師を補う体制の整備だ。
さらに、これに特定看護師制度なども加わると、いよいよ持って在宅の領域から薬剤師が締め出されないかと危惧する。
在宅療養を支えているのは医師でも看護師でもない。
ケアマネジャーや介護事業者でもないと思う。
在宅療養を支えているのは「薬」と「食べ物」である。
真に活用すべきは薬剤師と管理栄養士の存在なくしては成り立たない。
私のセミナーである方から質問があった。
「国は在宅を薦めているが、在宅になると今以上に医療費が膨らむのではないのか」
確かにそう思う。
なぜなら在宅が一番の贅沢のような気がするからだ。
出来る事ならあらゆるサービスを活用してでも自宅で往生したい。
家族が許してくれるなら。
目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!
















私は在宅を国が薦める一番の目的はやはりコストダウンだと思います。病院では、いつも身の回りの世話をしてくれる人もいますし、ちょっとしたことでも変化があればドクターもしっかり出てきます(訴訟リスクをさげるためですけど)食費も保険が効きます。
在宅だと家族がいれば、彼らが身の回りの世話をせざるえないでしょう。また病院とは違い食費も全額負担になってしまいます。病院みたいに24時間相手してくれる手厚い医療を在宅で実現できているとは思えません。
在宅が進めば、さらにサービス低下によるコストダウンが達成できると厚労省は踏んでいるじゃないんですかね?
厚労省はやさしさ、おもいやりで在宅を薦めているとは到底思えません。
治る治療ならいいのですが、生かす治療なら苦しいです。
私も国が在宅を推進しているのは医療費抑制だと思います。
でも、医療と介護制度を上手に使うと意外にコスト高になると思います。
居宅療養管理指導料だけ見ても医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師と利用できます。
ただ、知られていないので使われていません。
それと有用性についても理解されていません。
いろいろなサービスを考えてみたいですね。
今年も宜しくお願いします。