当社拝殿から伸びる石段の奥に本殿があります。
この本殿を囲む垣の手前に6基、御垣内に1基、
当社境内の中でも比較的に古い燈籠があります。
当社のご由緒は南北朝時代に何度も戦災に遭ったため、
荒廃し衰微したという不幸な歴史があります。
その時代に書物はすべて焼失してしまったため
特に中世は当社にとって「空白」の時代とされてきました。
江戸時代から史料などには…、
延宝もしくは元和年間に林宗甫によって著された
『和州旧跡幽考』に、このように書かれています。
『八咫烏社。菟田の町より一里■、俗に鷹塚村といふ。
一むかしにもやなりけん。社くづれ果て礎のこれり』
また『宇陀郡史料』等には、
『文化13年(1816)、下鴨社(賀茂御祖神社)から
神官が京より参向の際、当社に参って荒廃した社を嘆き、
近郷有志に働きかけて、神社の催行を促した』
…という旨の内容が書かれています。
では、当社は南北朝の争乱で焼失し、
下鴨社から神職が参向するまで、
そのまんまずーっと放置されていたのでしょうか?
それは違います。
何故か。写真をご覧ください。
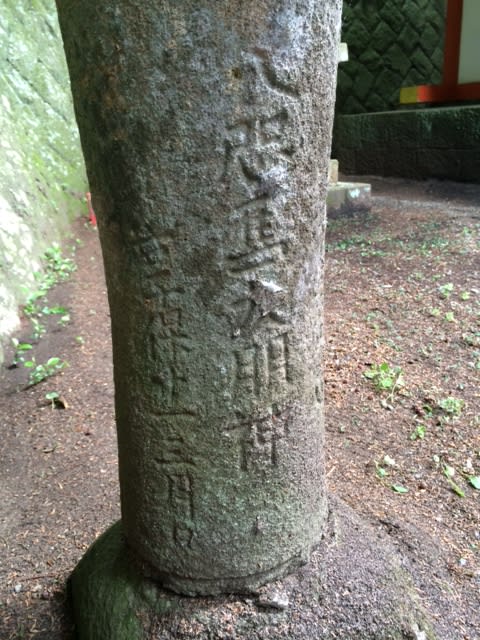
享保の時代の燈籠。
「八咫烏大明神」の文字も確認できます。
この他、宝暦時代の燈籠や
今や苔むして難読な元禄時代の燈籠も。
ちなみに
当社における江戸時代のタイムテーブルをあらわすと…
-----------------------------------
元和(1615-1624)=江戸時代の始まり
…
延宝(1673-1681)『和州旧跡幽考』に著される?
天和(1681-1684)『和州旧跡幽考』に著される?
…
元禄(1688-1704)=燈籠あり
…
享保(1716-1736)=燈籠あり
…
宝暦(1751-1764)=燈籠あり
…
文化(1804-1818)=下鴨社より神官が参向する
文政(1818-1831)=河合家が下鴨社より社守として出向される
…
慶応(1865-1868)=江戸時代の終わり
-----------------------------------
下鴨社から神官がやってくるまでの
時代の折々にも燈籠が奉納されていました。
たしかに戦災によって大きなダメージをうけ
江戸時代の当社は『風前の灯』だったかもしれません。
でも、地域の人々によってお祭りは受け継がれていた。
神さまを崇敬する想いは受け継がれていました。
そのように捉えても良いのではないでしょうか。
(少なくとも僕はそう信じています)
この本殿を囲む垣の手前に6基、御垣内に1基、
当社境内の中でも比較的に古い燈籠があります。
当社のご由緒は南北朝時代に何度も戦災に遭ったため、
荒廃し衰微したという不幸な歴史があります。
その時代に書物はすべて焼失してしまったため
特に中世は当社にとって「空白」の時代とされてきました。
江戸時代から史料などには…、
延宝もしくは元和年間に林宗甫によって著された
『和州旧跡幽考』に、このように書かれています。
『八咫烏社。菟田の町より一里■、俗に鷹塚村といふ。
一むかしにもやなりけん。社くづれ果て礎のこれり』
また『宇陀郡史料』等には、
『文化13年(1816)、下鴨社(賀茂御祖神社)から
神官が京より参向の際、当社に参って荒廃した社を嘆き、
近郷有志に働きかけて、神社の催行を促した』
…という旨の内容が書かれています。
では、当社は南北朝の争乱で焼失し、
下鴨社から神職が参向するまで、
そのまんまずーっと放置されていたのでしょうか?
それは違います。
何故か。写真をご覧ください。
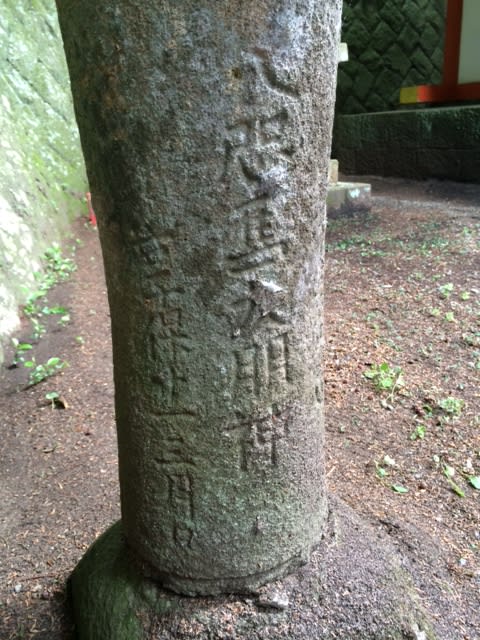
享保の時代の燈籠。
「八咫烏大明神」の文字も確認できます。
この他、宝暦時代の燈籠や
今や苔むして難読な元禄時代の燈籠も。
ちなみに
当社における江戸時代のタイムテーブルをあらわすと…
-----------------------------------
元和(1615-1624)=江戸時代の始まり
…
延宝(1673-1681)『和州旧跡幽考』に著される?
天和(1681-1684)『和州旧跡幽考』に著される?
…
元禄(1688-1704)=燈籠あり
…
享保(1716-1736)=燈籠あり
…
宝暦(1751-1764)=燈籠あり
…
文化(1804-1818)=下鴨社より神官が参向する
文政(1818-1831)=河合家が下鴨社より社守として出向される
…
慶応(1865-1868)=江戸時代の終わり
-----------------------------------
下鴨社から神官がやってくるまでの
時代の折々にも燈籠が奉納されていました。
たしかに戦災によって大きなダメージをうけ
江戸時代の当社は『風前の灯』だったかもしれません。
でも、地域の人々によってお祭りは受け継がれていた。
神さまを崇敬する想いは受け継がれていました。
そのように捉えても良いのではないでしょうか。
(少なくとも僕はそう信じています)









