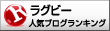東京セブンズから2週間開いてセブンズ三連チャンに突入。本日のYC&ACセブンズを皮切りに来週(4/13)は東日本大学セブンズ、再来週(4/20)は関東大学フットボール連盟のセブンズ・ア・サイド(通称リーグ戦セブンズ)と続く。「花の命は短くて」の如く、僅か1ヶ月でパッと散ってしまう大学生のセブンズだが、この1ヶ月に焦点を絞っているチームもあるので楽しみだ。
とくに今回のYC&ACは1週間前に香港で悲願の「コア15入り達成」に貢献した選手達も出場が予定されているだけに興味のタネは尽きない。ホストチーム(YC&AC)他の社会人に大学生のチームを織り交ぜた構成でサプライズも期待される。果たして、今年はどんなドラマが待っているだろうか。心配された天候も上空を覆っていた雲が晴れて回復してきた。

[予選ラウンド]
●日本大学 0-35 ○タマリバクラブ
○専修大学 28-12 ●YC&AC
●横河武蔵野 15-26 ○慶應義塾大学
●東海大学 5-31 ○PSIコストカッツ
○筑波大学 45-0 ●中央大学
●北海道バーバリアンズ 19-24 ○青山学院大学
●早稲田大学 19-24 ○和歌山県選抜
●明治学院大学 0-39 ○流通経済大学
注目チームはなんと言っても日本代表のジェイミー・ヘンリーを擁するPSI(購買戦略研究所)コストカッツ。ここに驚きの選手達が加わっていた。拓大で大暴れしリコーに入社した横山伸一&健一の横山ブラザーズだ。体型は大学時代と殆ど変わっていないように見えるのが気になるが、緒戦で早くも高いランニング能力を見せつけた。2人は元来セブンズでブレイクしたので完全復活を期待したいところ。でも、やはりこのチームはジェイミーの存在が際立つ。パワフルな東海大を一蹴してしまった。
日大とタマリバの対戦は、日大が福田恒輝や竹山将史を擁するタマリバの老獪さに為す術なく敗れた。そう書きたいところだが、オジサン軍団(失礼ながら)の方が気合が入っていてどうする?というちょっと情けない印象の試合に終わった。その後に登場した専修大学が元気溌溂で自信を持ってプレーしていただけによけいそう感じた。専修がパワーのYC&ACを振り切り見事緒戦突破を果たす。
慶應はセブンズへの取組方針を改めたのか、こちらも元気一杯のプレーで横河武蔵野を圧倒。昨年のリベンジに燃えた中央大はパワーアップした筑波に返り討ちに逢って完敗。北海道バーバリアンズ(トゥキリは出場せず)を破った青山学院はなかなかのタレント軍団といった感じ。和歌山県選抜は来年の和歌山国体に向けて結成されたチームだが、早稲田はチーム熟成度の差が出てよもやの敗戦という結果になってしまった。セブンズの星リリダムにパワフルなジョージとシオネを合谷が操る流経大は明治学院を寄せ付けず難なく緒戦突破を果たす。

[コンソレーション1回戦]
○日本大学 35-17 ●YC&AC
●横河武蔵野 12-33 ○東海大学
○中央大学 22-17 ●北海道バーバリアンズ
○早稲田大学 21-7 ●明治学院大学
去年もそうだったが、緒戦でうまくいかなかったチームはコンソレの1回戦で息を吹き返すことが多い。とくにジャージを替えて登場した日大が「別のチーム」になっていたのが印象的。本日はマイケルはベンチから声援を送る役割だが、かえってチームバランスが良くなった感もある。試合半ばからコンビネーションに冴えが出てきてYC&ACを翻弄し勝利を収めた。東海大は黄金のバックスリーにいい形でボールを渡せば社会人相手でも爆発できる。
中央大もアタックに積極性が出始め北海道バーバリアンズに競り勝った。昨年の本大会で鮮烈なデビューを果たしたスピードスターの住吉藍好のランが冴える。早稲田と明治学院の戦いはスコアからは早稲田が貫禄を見せた形だが、試合内容はほぼ五分。セブンズとしてのチームの熟成度は明治学院の方が上だった。早稲田がどのレベルの選手を出してきたのかは不明だが、東海や筑波に較べると体格差が際立つ(小さい)印象。
[チャンピオンシップ1回戦]
●タマリバクラブ 5-26 ○専修大学
○PSIコストカッツ 21-17 ●慶應義塾大学
○筑波大学 33-7 ●青山学院大学
●和歌山県選抜 0-59 ○流通経済大学
緒戦で元気いっぱいのプレーを見せてYC&ACを破った専修だが、実力はホンモノであることがはっきりした。この大会に向けてしっかり準備をしてきたことでは同じだったはずだが、専修のコンビネーションの方がタマリバを上回った形。準決勝に期待を繋ぐ形で専修がタマリバを圧倒して勝利を収めた。慶應は本当に惜しかった。17-14と勝利を目前にしたところで今やジャパンの看板スターの1人となったPSIのジェイミーの一発に沈む。ジェイミーが自陣でボールを持った段階で前には慶應の選手が5人くらい居たが、すべてタックルを弾かれて70mくらい走られて涙を呑んだ。ただ、PSIは横山ブラザーズという武器はあってもジェイミー頼みの部分が多く流経には苦しいかもという印象を抱かせた。
筑波は専修や(コンソレの)日大のような洗練されたコンビネーションで勝負するチームではないが、プレーの堅実性と身体を張る泥臭さが魅力のチーム。個々の判断がすばらしくそれがチームとして共有されているためディフェンスに綻びが出ないのが強み。才能集団の感がある青山学院を1トライに抑えての圧勝で調子が上がってきた。流経大の看板スターはリリダムだが、誰も止められないジョージ・リサレも凄い。去年よりさらに進化し、既にとてつもない選手になっている。そこに相手ディフェンスを自由自在に切り裂く合谷が居るのだから59-0のスコアも納得。

[コンソレーション準決勝]
○日本大学 26-22 ●東海大学
●中央大学 7-19 ○早稲田大学
加藤HC体制になってから一度も東海大に勝っていない日大だが、コンソレになってから一気にチーム力を上げてきた。専修に刺激されたわけでもないが、接点を作らずにパスを繋ぐコンビネーションで東海大を翻弄する。対する東海大はパワフルな選手が揃っていることが裏目に出る形でちぐはぐ。個人頼みとなってしまい決勝を前にあえなく敗退した。トライの場面をひとつひとつ切り取っていけば惚れ惚れするようなランではあるのだが、ディフェンスになるとあっさり抜かれるシーンが多く反省点がたくさん出た内容だった。
前半の中央大は幸先良く先制して早稲田を圧倒する勢いだった。1人1人が自信を持ってプレーできるようになってきたのが大きい。ひとつ惜しまれるのは、住吉がディフェンスを切り裂いてゴールまであと10数mというところで(ノールックで後ろに)ボールを離したこと。フォロワーが居ればトライになった可能性が高い。ここで勝利がするりと逃げてしまったように思えた。
[チャンピオンシップ準決勝]
○専修大学 24-19 ●PSIコストカッツ
●筑波大学 12-19 ○流通経済大学
コンソレの準決勝あたりから雨が激しくなり、ついに土砂降りの状態に。そんな中でも、専修の磨き抜かれたパスワークが冴え渡る。PSIのメンバーにジェイミーが居なかったことがラッキーだった面はあるにせよ、攻撃の組立ではPSIを上回っていたことは確か。とにかく専修がボールを持つと観ていて楽しい。流石に元セブンズの日本代表監督が率いるチームだけあるが、それだけではなさそう。大雨で身体は冷やされていくが、芯から身体が温まってくるような熱い試合だった。
筑波と流経は双方の日本代表と代表レベルの選手達のマッチアップで見応えのある試合(事実上の決勝戦)になった。リサレやリリダムに対して3人で止めに行っても余らせない筑波のディフェンスが見事。筑波ではどうしても福岡や竹中に注目が集まるが山下など好選手がたくさん居る。専修の洗練したスタイルもいいが、筑波のような泥臭さと個々が精神的な絆で結ばれている乱れない組織も魅力。シンビンが出てしまうなど、最後は流経大の圧倒的なパワーの前に屈した形だが、今年の筑波は去年以上に強くなりそうな予感がする。

[コンソレーション&チャンピオンシップ決勝]
○日本大学 12-5 ●早稲田大学
予選ラウンドでどうなることかと危惧させたことがウソのように自信をつけて決勝に臨んだ日大が早稲田のディフェンスを翻弄して勝利を収めた。日大の(ポイントを作らない)パスラグビーは専修よりも徹底している。丁寧にパスを繋ぎながら相手のディフェンスに綻びが出るのを待ち、一気に勝負を仕掛ける。ここにマイケルが入ったらパワフルなアタックが完成という感じがした。逆に言うと、あえてマイケルを入れないでこの形を作ることがこの大会の目標だったのかも知れない。どうしてもFWのことが気になるが、今年の日大は期待していいかもしれない。早稲田は準備不足だったのかも知れないが、アタック、ディフェンスとも消化不良という印象が残る敗戦となった。
●専修大学 19-62 ○流通経済大学
すっかり雨が上がり晴れ間も見える中での決勝戦。圧倒的な攻撃力を誇る流経大の優位は動かない結果になってしまったが、自陣からの丁寧なアタックでゴールラインまで3つボールを運んだ専修大のアタックも見応えがあった。今からでも遅くはないから、特別枠で専修を東日本大学セブンズに招待できないだろうかと無理は承知で思ってしまう。リーグ戦全体で観ても現時点で流経大の次にセブンズが強いのは専修大と見て間違いない。15人制にしても、入替戦出場枠の争いが激しくなることは間違いなく、また、入替戦も昨年以上に厳しい戦いになるだろう。もちろん、これはリーグ戦Gウォッチャーとしては歓迎すべきこと。ここで掴んだ自信を糧にシーズンを戦い抜けば、悲願達成も現実味を帯びてくるだろう。
◆YC&ACで味わったセブンズの醍醐味
一時激しい雨の降る中で、立ち見での観戦だったわけだが、むしろセブンズの醍醐味を味合わせてもらったような気がした。15人制だとグランドレベル(選手目線)での観戦は、迫力満点である代わりに選手達が重なって全体的な動きが捉えにくい面がある。でも、セブンズだと全体がよく見渡せるので、そういった不満はなくなる。選手達の大きさがわかるだけでなく、スピードの違いもスタンドで観るよりよくわかる。昨シーズンから始めたYC&ACの観戦だが、止められなくなってしまった。この素晴らしい大会を運営している関係者の方々に感謝の言葉を贈りたい。