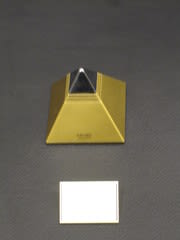中学生になった時、親に買ってもらった腕時計。
ワクワク感と、どこか大人になったような気分で、とてもうれしかったことを覚えています。
買ってもらったのは、SEIKO。
日本を代表する時計メーカーです。
社会人になり、一時期TAGタグホイヤーを着けていましたが、今またSEIKOのクロノグラフを着けています。
アジアの友人から、「なぜ、日本には素晴らしい時計があるのに、スイスメイドなの?」という素朴な質問からでした。
そう、ニッポンには、SEIKOがあるのです。
「セイコーミュージアム」
・開館時間・・・10時~16時
・月曜日休館 祝日・年末年始休館
・入館料 無料

初めて訪れました。
場所は、なんと墨田区の向島。
なんでこんな所に・・・というところにあります。
東京スカイツリーから二駅。
下町の雰囲気がプンプン漂う中に、この博物館はあります。
一階では、親切な女性スタッフが迎えてくれます。
簡単な記帳をして館内へ。
一階・・・ミュージアムショップ 時と時計の進化 スポーツ計時体験コーナー

東京五輪2020でも、SEIKOの文字を見たいものです。

二階・・・セイコー創業の精神 セイコー製品史 日本有数の和時計コレクション
お奨めは、2階。
創業者・服部金太郎さんの服部時計店創業の歴史を写真と解説文で学ぶことが出来ます。
セイコーの原点が分かるとともに、関東大震災、世界大戦など激動する時代を駆け抜けたセイコー社の企業精神、ビジョンを知ることが出来ます。

セイコー社を一言でいうと、「真面目にコツコツ、時計技術のテッペンを目指すジャパニーズカンパニー」。
日本のものつくり企業を代表するメーカーだと思います。
また、手巻き時計、置き時計から、現代のセイコーアストロンに至る歴史は、地味ながらも日本の産業史でもあります。
世界初のクオーツウォッチの実用化、自動発電時計の開発・・・。
特に、機械式時計の頂点をきわめたスプリングドライブは、感動モノです。
MUSEUMは、美術館とも博物館とも訳されますが、セイコーの歴代の時計がこれだけずらっと並ぶと、それはまさに芸術品。
数千円のものから二千万円を超えるドレスウォッチまで、その美術的な価値を観るだけでも心が癒されます。
このミュージアムの2階は、時系列で製品展示をしてあるため、自分の歴史にオーバーラップさせることもあります。
そういえば、目覚まし時計は、ずっとSEIKOでした。
大学時代からピラミッドトークを使い始め、その後キュービックトーク・・・。
そして今は新ピラミッドトークで毎朝起きています。
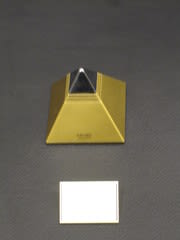
ちょっとピンボケですが・・・。
確か、最初はゴールド色、次にシルバー色のものが発売されました。
今使っている新ピラミッドトークは白色です。
本当に懐かしいなあ~。
日本の家庭には、必ずあった時計たちです。
数字がパタパタと変わっていく時計を見て、思わず昭和の時代を思い出してしまいました。

そういえば、昔、折り畳みのトラベル時計がありましたよね。

時計作りの職人さんのプライド・・・世界のトップを目指そうという技術者魂が、手の上に乗る腕時計サイズに凝縮する。
それは結構迫力ある世界です。
近代日本の歴史とともにあるSEIKOの歴史。
セイコーミュージアムの展示は、よく表現していると思います。
日本の製造業の持つ真面目さ、真摯さを伝える施設であるとも言えます。
時代がデジタル一辺倒になる中、心温まるアナログの世界に癒されます。
が、SEIKO社も、このまま、スマホやタブレット、ウェアラブルなアップルウォッチなどに淘汰されてしまうのでしょうか。
そうなれば、ドレスウォッチや宝飾品としての時計で勝負・・・。
いやいやスウォッチ的な展開で生き残りをかける・・・。
SEIKO社のこれからの経営戦略、マーケティングは大変だと思います。
がんばれ!ニッポンのセイコー!!
セイコーミュージアムは、時計の持つアナログ感、人間の温もり、毎日接する親和性・・・時計というのは文化そのもの、人生そのものであるとも感じることの出来るスペースです。
今後もし出来るのならば、SEIKOを巡る画家、小説家、詩人、文化人などに関連する展示があってもいいかもしれません。
著作権や肖像権の問題もあるのでしょうが、展示の充実のために検討いただければと思います。
一度は訪れたい企業博物館です。