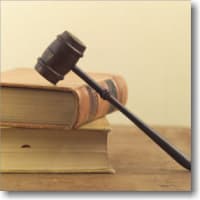おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、整備工場の工場長が現場力を変えるー3の生産性改善でCSを高めよう、です。
工場長として作業現場を見る場合、修理技術の優劣以上に「生産性」をどう高めるかと言う視点が
重要になる。与えられた経営資源で、いかに多くの整備作業をするかだ。
年々歳々工賃目標がアップする中で、メカニックを増やしていては、利益は薄くなってしまう。
これからの作業現場は、メカニックの数を減らしてでも、工賃売上をアップしていくことが
求められている。それを成し遂げるのが「生産性向上」である。
整備工場における生産性の指標には、「稼働率」と「作業効率」の二つがある。
稼働率とは、平たく言えば、お金を稼いでいる割合。計算式は「直接作業時間÷実労働時間(※)×100」。
※拘束時間+残業時間-休憩時間
直接作業時間は、整備作業を行っている時間で、分解、脱着、調整、清掃、計測など実際に作業を行っている
時間に付帯および余裕作業時間を加えた時間。この時間が、基本的に請求時間となりますので、
お金を稼いでいる時間となる。
とはいっても整備作業をしている時間全てが請求できる時間かと言えば、そうはない。
作業している時間が全て請求時間であれば、手の遅いメカや整備経験浅い方が、生産性が高いことになりる。
そこで請求時間を決めるのが「標準作業時間」だ。別名、作業工数とか作業点数などと呼ぶこともある。
この時間が実際かかった時間と比べたのが「作業効率」となる。
計算式は「標準作業時間÷直接作業時間×100」。
実際にかかった直接作業時間が、標準作業時間よりも長ければ生産性は低いことになる。
稼働率を向上させるには「実労働時間」をより長くするか、「間接作業時間」を短くする二つの方策
が考えられる。
間接作業時間の多くを占めるのが「引取・納車」に伴う車両回送時間。
入庫車両のほとんどが引取し、整備が終わったたら届ける必要悪サービス。このパターンを改めること。
ある会社では、このサービスを有料化することにした。地方の田舎町にある工場で、一回の取引で800円とし
た。また、代車の貸し出しは、無料だが工場での引き渡し、引き受けとした。
この結果、半部以上の車両回送回数を減らすことが出来た。
念のためだが、このことで他社に切り替わったお客は全くなかった。
有料化が難しいとなれば、車両回送そのものを効率化すること。
何人で何台回送できたかが車両回送の効率化。例えば、1台のサービスカーに2名で行って、
1台の回送が出来れば、車両回送効率0.5(1台÷2名)となる。
1台のバイクに1名で行って、1台回送できれば車両回送効率は1.0になる。
バイクをタクシーにしたり自転車でもいい。
作業効率は、稼働率と違って社内の努力次第で大いに改善できる。
先ずやるべきことは「工具・部品取置き」と「作業歩行」を減らすことだ。
ある車検整備における作業時間は1時間5分、歩行距離401m、歩行歩数669歩だった。
トルクレンチなどのツールとブレーキフルードは、作業中に取置きをしている。
これは、この工場だけのことではなく、ごく普通に見られる光景だ。
これを、作業前に準備して作業することで歩数、歩行距離は格段に少なくすることが出来る。
作業指示書を貰ったら、即作業に入るのではなく、必要部品、必要工具&テスターなどを取りそろえてから
作業に入る、これを常識にすること。
ある工場で検討しているのが、メカニックごとのハンドツールを無くし、空のキャディを与える。
ハンドツールを共用工具とし、作業指示書を受け取ったメカニックは、ハンドツール置き場に行き、
必要な工具をピックアップ、次に部品庫に行き、必要部品を取り出しキャディに搭載して作業ストールに
行く仕組み。
こうすることによって、取置き回数を減らすことと、作業手順を考えさせることで、作業動線を短くする効果を
狙った改善だ。
生産性の二つの指標は、何のために必要かと言えば「コストダウン」にとって不可欠だからだ。
不景気の中でレバレートの改訂(アップ)は、お客さまからの抵抗が大きく難しいのが現実だ。
しかし、経営的には新しい設備投資も必要だし、定期昇給もやらなければならないなど、
経営費用は間違いなくアップしている。
そのコストを左右する指標が生産性の二大指標なのだ。
稼働率が高まれば売上になる時間を多くすることができ、コストを吸収したことになる。
作業効率は60分の標準作業を40分で行えば、20分のコストを吸収したことになる。
このコストダウンの原点が何かと言えば「5S」。
5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」のこと。
工場長は、生産性の二大指標を統計データとして集計・分析し、その結果に基づいて工場の課題を抽出し
改善活動を行うこと。そして、常に5Sの目を持って工場内外を定期巡視することだ。それがマネジメントである。
株式会社ティオ
お問い合わせ