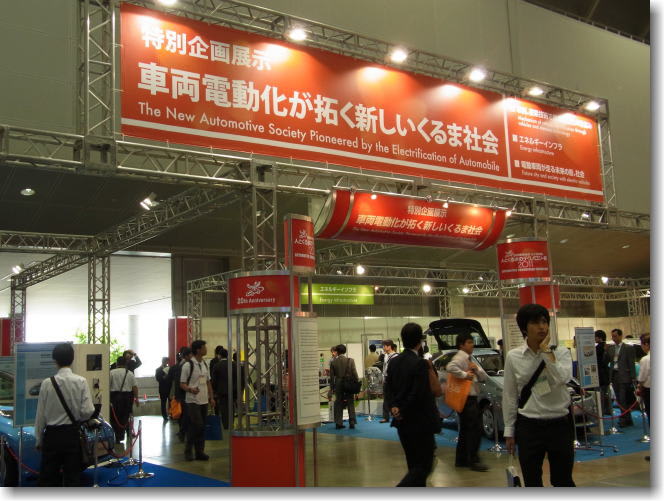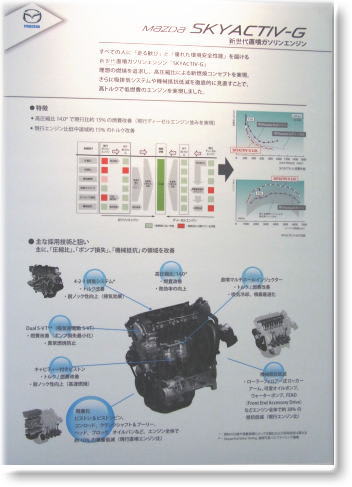おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、22年度整備白書からの報告ー4.整備業の廃業理由、です。
H22年度の整備工場数は、前年比+555工場(0.5%アップ)の91,736工場であった。
業態別では、専業工場が57,182工場で前年と比べて+1,817工場(+3.3%)と、大幅に増えた。
兼業工場は、14,761工場、前年比-1,241工場(-7.9%)と、専業工場の逆で大幅減少となった。
専業工場が大きく増えたのは、未認証工場の認証取得が大きな理由だ。したがって、工場の増加は早晩
止まるだろうし、減っていく曲面を迎えることになるだろう。
ディーラーも前年比で61工場マイナスの16,082工場であった。ディーラーの減少は、事業合理化や
合併などに伴う工場合理化によるものと思う。
自家工場も減っていてマイマス40工場の3,711工場となった。因みに、指定整備工場は29,115工場で、
前年比49工場プラス(+0.2%)となっている。
新規認証工場数は1,909工場(前年比-128工場、-16.0%)で、前職別を見てみると、
次の通りとなっている。
・専業工場 :680工場(前年比-16.0%)
・ディーラー :74工場(同-44.0%)
・自家工場 :35工場(同-27.0%)
・車体整備業 :426工場(同-30.0%)
・ガソリンスタンド :137工場(同+1.0%)
・整備関連事業 :61工場(同-24.0%)
・運輸事業 :70工場(同+79.0%)
・車検代行業 :76工場(同ー24.0%)
・自動車販売業 :127工場(同ー8.0%)
・部品・用品販売業:59工場(同-39.0%)
・その他 :164工場(同+15.0%)
H19年度では2,598工場、H20年度では2,405工場で、増加数が鈍化傾向になっていることがわかる。
認証工場廃業事業数は、1,449工場(前年比-24工場、-17.0%)であった。
理由別に見てみると、次の通りである。
・経営不振 :121工場(前年比-24工場、-17.0%)
・倒産 :58工場(同-6工場、-9.0%)
・工員不足 :38工場(同+3工場、+9.0%)
・事業合理化 :556工場(同+133工場、+31.0%)
・移転・立退き :56工場(同-15工場、-21.0%)
・転業 :18工場(同±0工場、±0%)
・合併 :8工場(同-5工場、-38.0%)
・協業組合参加:1工場(同-8工場、-89.0%)
・後継者難 :147工場(同-35工場、-19.0%)
・自己都合 :345工場(同-68工場、-16.0%)
・取り消し :29工場(同-3工場、-9.0%)
・その他 :71工場(同-23工場、-24.0%)
・不明 :1工場
工員不足を除いて、全て前年比でマイナスであったが、相変わらず「経営不振」「後継者難」「自己都合」が
三桁もあり、気なるところである。
この理由として、景気の低迷などを背景にした、価格競争が激しさを増し、先行き不安による事業継続を
諦める工場がおおいいのではないだろうか。
保有台数が減少しているとはいえ、マーケットはそれなりに潤沢にあり、足りないのはそこから需要を創り
出す企画と行動力ではないだろうか。
例えば、7月24日でアナログ放送からデジタル放送に移行する。これに伴って、テレビの買い替えが
必要だが、家庭用のテレビの買い替えは、補助金などの効果もあり順調に推移しているが、カーテレビは
いかがだろうか。
自社のお客さまの買い替え促進や、チューナー取り付けなどの販売促進を行っているだろうか?はたまた、
管理客の中から未対応客をピックアップして、買い替えやチューナーの必要性をアナウンスしている
だろうか。
販売をアップするチャンスは色々とあるが、それを上手く生かすのは、自分たちである。売上は、待って
いたのでは顕在化しない。能動的に活動してこそ、経営目標が成就するのである。
株式会社ティオ
お問い合わせ