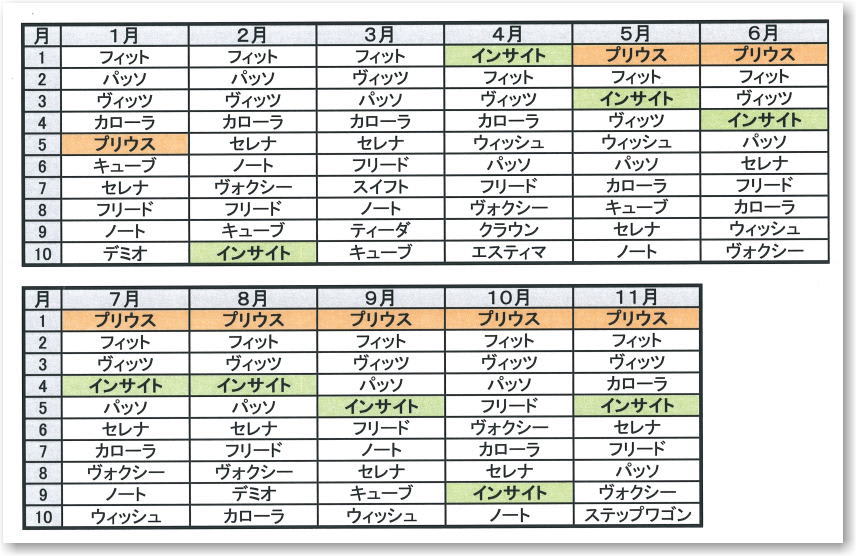今日は、H21年度分解整備業実態調査の緊急レポート(4)格差広がる点検カバー率、です。
整備業界では、毎年のように「定期点検の普及拡大」を、事業のテーマに掲げている。しかし、点検実施率は50%前後で停滞気味である。カーオーナーの意識が希薄なこともあるが、業界全体の取り組みが今一つ盛り上がらいのが気になる。
商用車などの実施率はそれなりに高いものがあるが、個人所有の乗用車となると低調気味である。こうしたこともあって、モータース店の中には、定期点検のお知らせDMを行っていないケースも見受けられる。
管理客だ、などと言っている割には、管理の中身が伴っていない。そんなデータが上記のグラフである。
棒グラフは工場当たりの入庫台数だ。工場規模が違うので、単純比較はできないが、ディーラーでは、平成21年度で549台の入庫がある。モータース店(専業工場+兼業工場)では、たったの37台だ。
これは、1か月の入庫台数ではなく、年間の入庫台数だ。なんと月平均で3台しか入庫がない。さみしい限りである。
車検一台に対しての点検台数を見たのが「点検カバー率」という指標である。折れ線グラフがそれだ。ディーラーでは、2年車検を10台実施すると定期点検は、8.7台実施している。
モータース店は、1.6台だ。作業効率でいえば、30分前後で5千以上点検料になる。レート換算では1万円になる。作業時間終割りにとても率がいいのだ。
なのに、入庫促進は、車検ほどの熱心さはないように感じる。定期点検は、車検とダイレクトに結びついている。だから、今、ディーラーの新車営業マンに「定期点検」の目標が設定されているのだ。
定期点検が他店でに入庫したということは、車検も取られてということになる。結果、自社代替率を悪くすることになり、自分の車販営業の達成率が悪くなりという図式ができているのだ。
定期点検は、顧客囲い込み度のバロメータともいえる。したがって、入庫の結果は、結果として、案内DMとその後のフォローコールは必ず実施することだ。
フォローコールすることで、お客さまとのコミュニケーションも図れ、親しみ度が増すことにつながる。このことだけでも、囲い込み度が高まるのだ。少なくても年に1度ぐらいは、こちらからコンタクトを取ろう。そのきっかけが「定期点検」なのだ。
株式会社ティオ
お問い合わせ