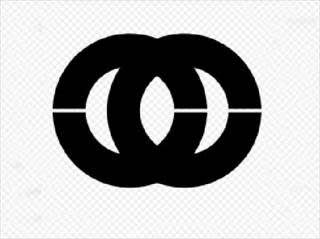山武市(さんむし)は千葉県の東部に位置する市です。2006年3月27日に、山武郡成東町・山武町・蓮沼村・松尾町が合併して誕生しました。東金市、八街市、富里市、山武郡:九十九里町、芝山町、横芝光町に隣接。日本有数の砂浜海岸である九十九里浜のほぼ中央で約8キロメートルにわたって太平洋に面し、地勢は大別して九十九里海岸地帯と、その後背地としての広大な沖積平野及び標高40から50メートルの低位台地からなる丘陵地帯で構成されています。海岸地帯は、砂浜と松林が連なり、成東海岸と蓮沼海岸の遠浅の海が広がり多くの海水浴客が訪れます。平地地帯は、本地域の中央部に広がる肥沃な土壌を持つ九十九里平野で、田園地帯を形成しています。「市の木:杉」「市の花:野菊」「市の鳥:ウグイス」を制定。
キャッチフレーズは「誰もがしあわせを実感できる独立都市 さんむ」

集落排水マンホールには市章と「市の花:野菊」、中央に二羽の「市の鳥:メジロ」、上に「市の木:杉」が描かれています。


2006年10月1日制定の市章は「太陽に映える恵みの大地と太平洋をイメージしました。 山武市の頭文字「山」をモチーフに、未来を拓く新しい風を感じる躍動感に満ちた山武市の姿を表わしています」HPより


上水道関連の蓋は市章付き仕切弁

「山武郡市広域水道企業団章」の消火栓

「大多喜ガス」の社章がついた大きめの角蓋とハンドホール。


「国際石開帝石(国際石油開発帝石株式会社)」のハンドホール

山武市のマスコットキャラクター『SUN(サン)ムシくん』。イチゴ頭のテントウムシ君です。『SUN(サン)=太陽』と『ムシ=テントウムシ』を組み合わせた名前で、イチゴ畑でのかくれんぼが趣味です。

------------------------00----------------------
旧山武郡成東町(なるとうまち)は千葉県の北東部に位置した町です。東金市、山武町、松尾町、九十九里町に隣接。九十九里平野のほぼ中央に位置し、九十九里浜のなかでも有数の広い砂浜をもつ自然あふれる町です。また「野菊の墓」等の作者で知られる『伊藤左千夫』野菊の墓等の作者の出身地でもあり、山武市歴史民俗資料館に隣接した彼の生家が、千葉県指定史跡として今も残されています。

明治22年(1889)、町村制の施行により武射郡成東町、大富村、南郷村、緑海村が成立。
1897年、郡制の施行により、山辺郡・武射郡の区域をもって山武郡が発足。
1954年、山武郡大富村、南郷村を編入。
1955年、山武郡緑海村を編入。
2006年、山武郡山武町・蓮沼村・松尾町と合併。山武市となりました。
独自のマンホール等は無く、町章と自治体名の有る「防火水槽」が唯一の収穫。

昭和35年5月20日制定の町章は「中の形で「N」を示し、それを輪で囲んだたもの」

旧成東町の花であった「野菊」のカラータイル

無印の規格雨水マンホール。旧成東町時代のものなのか、山武市になってからの蓋なのか不明。

撮影日:2019年3月10日