
奈良まほろばソムリエ検定(奈良検定)の「祭りと芸能」対策本を探しているとき、田中眞人さんの『奈良大和路の年中行事』(淡交社刊 215ページ 1800円)という本が目に止まった。版元の紹介文には《奈良県内には、神社仏閣などに仏像や建築などの古代の遺産が多く伝えられていますが、民間にも古い伝統行事が連綿と受け継がれています。本書では、著者がライフワークとして撮り続けてきた奈良の貴重な行事写真を、一挙に紹介。他府県には見られない特色のある行事が奈良には多く、豊かな風土を実感できる一冊です》。
http://www.tankosha.co.jp/cgi-bin/bookdetail.cgi?pc=0000003597-000000
《[本書の特徴]●奈良県内、100ヶ所以上の行事について紹介。●豊富な写真をオールカラーで掲載。詳細な解説付き。●一月から十二月まで開催日順に配置し、歳時記としても見られます。●出版媒体では初紹介となるであろう民俗行事多数》《撮影と同時に綿密な取材をしている著者ならではの奈良行事の集大成。「伝統を継承する奈良の人々の心意気が伝わればと思ってます」(著者)》とある。
※『奈良大和路の年中行事』の目次(PDF形式)
http://www.tankosha.co.jp/prod_img/pdf/0000003597-000000.pdf
奈良の祭りについては、これまで野本暉房さんの『奈良大和の祭り』(東方出版刊 118ページ 2000円)を愛読してきた。1ページに1つの祭りの簡単な説明とハガキ大の写真1点が載った、シンプルで楽しい本だ。
一方『奈良大和路の年中行事』は、解説がとても詳しいので、検定対策本として使える。奈良検定のテキストには写真がほとんど出ていなし、説明もきわめて素っ気ないのでイメージがつかみにくいが、『奈良大和路の年中行事』だと、まるで現地で祭りを見ているような臨場感がある。県下の祭りがきれいに日付順に並んでいるので、とても理解しやすい。奈良の祭り研究の第一人者である鹿谷勲氏(奈良県立民俗博物館学芸課)も、制作に協力されている様子である。
『奈良大和の祭り』の野本暉房さんは、日本生命に勤務されていて、2003年の退職を機に写真に専念されたそうだが、『奈良大和路の年中行事』の田中眞人さんも、会社勤務の傍ら写真を撮って来られた方だ。2002年に退職され、現在は大和郡山市市民交流館の臨時職員を務めながら、ライフワークとして県下の民俗行事などの写真を撮っておられる。
私の知人にも、京都でサラリーマンをしながら小説を書いている鏡清澄さん(筆名)という方がいる。奈良を舞台にした中編小説が2編載った『迦陵頻伽(がりょうびんが)奈良に誓う』(ブイツーソリューション刊 1500円)という本を出版された。奥さんとアイデアを出し合いながら執筆されたとのことで、奈良の名所がたくさん登場し、観光情報小説としても楽しめる本である。
筆者の鏡さんからコメントをいただいたので、以下に紹介する。《『奈良に誓う』は東京の陶器店の若き女性店長あずさが主人公で、あずさの仕事、奈良市西ノ京の旅館の青年後継者である貴一との出会い、二人でめぐる奈良の自然と文化が描かれる。美しい四季折々の情景は心を浄化し、歴史に裏打ちされた文化は人の生き方を深化させていく。『萬世同薫』は貴一が奈良・唐招提寺の開祖である鑑真和上と、和上に関係する人たちから、その精神性の高さを学んでいく話である。なかでも芭蕉が鑑真和上像を拝して詠んだ俳句「若葉して御めの雫ぬぐはばや」の新解釈は、和上と芭蕉の生き方を知れば頷けるものではないだろうか》。
《両編を通じて、素晴らしい場所である奈良と、奈良に育まれる若者の姿が描かれているが、「ところは違っても同じ思いを持つ人がいて、時は変わっても同じように薫る」という言葉は、人間への期待の熱いメッセージである》《この本の魅力は大きく括ると次の三点である。①臨場感あふれる奈良の描写に、多くの読者は奈良へ行きたくなるだろう。②歴史や文学などの事実に接し、知的興奮を覚えるだろう。③奈良の真の価値は、心を見つめ、心を深める点にあることを知るだろう》。
アマゾンでのカスタマーレビューも、好意的だ。《古都奈良の奥深さを理解させるのに、この独特なアプローチはみごとに成功している。奈良に住み、奈良の歴史について長く研究してきた著者による渾身の作である》《奈良に行った読者は、自分を重ねて、まだ行ったことのない読者は奈良への憧れを抱きながら引き込まれていく本である。是非一読を!》《唐招提寺や若草山のお水取りなどを中心に描写が見事に記述されていて、まるでその場にいるような錯覚を感じさせられます》等々。
お3人とも、サラリーマン生活の中で自らのライフワークを発見し、それを着々と実現されている姿は、ご立派である。とても私などマネのできることではないが、奈良を思う気持ちは同じなので、少しでもあやかりたいと思う。
※トップ写真は、私が撮った県指定無形民俗文化財「江包(えっつみ)・大西のお綱祭り」(09.2.11撮影)。『奈良大和路の年中行事』にも『奈良大和の祭り』にも、もっと良い写真が載っているので、ぜひお買い求めいただきたい。
http://www.tankosha.co.jp/cgi-bin/bookdetail.cgi?pc=0000003597-000000
 | 奈良大和路の年中行事田中 眞人淡交社このアイテムの詳細を見る |
《[本書の特徴]●奈良県内、100ヶ所以上の行事について紹介。●豊富な写真をオールカラーで掲載。詳細な解説付き。●一月から十二月まで開催日順に配置し、歳時記としても見られます。●出版媒体では初紹介となるであろう民俗行事多数》《撮影と同時に綿密な取材をしている著者ならではの奈良行事の集大成。「伝統を継承する奈良の人々の心意気が伝わればと思ってます」(著者)》とある。
※『奈良大和路の年中行事』の目次(PDF形式)
http://www.tankosha.co.jp/prod_img/pdf/0000003597-000000.pdf
奈良の祭りについては、これまで野本暉房さんの『奈良大和の祭り』(東方出版刊 118ページ 2000円)を愛読してきた。1ページに1つの祭りの簡単な説明とハガキ大の写真1点が載った、シンプルで楽しい本だ。
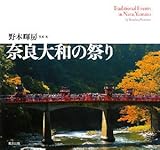 | 奈良大和の祭り野本 暉房東方出版このアイテムの詳細を見る |
一方『奈良大和路の年中行事』は、解説がとても詳しいので、検定対策本として使える。奈良検定のテキストには写真がほとんど出ていなし、説明もきわめて素っ気ないのでイメージがつかみにくいが、『奈良大和路の年中行事』だと、まるで現地で祭りを見ているような臨場感がある。県下の祭りがきれいに日付順に並んでいるので、とても理解しやすい。奈良の祭り研究の第一人者である鹿谷勲氏(奈良県立民俗博物館学芸課)も、制作に協力されている様子である。
『奈良大和の祭り』の野本暉房さんは、日本生命に勤務されていて、2003年の退職を機に写真に専念されたそうだが、『奈良大和路の年中行事』の田中眞人さんも、会社勤務の傍ら写真を撮って来られた方だ。2002年に退職され、現在は大和郡山市市民交流館の臨時職員を務めながら、ライフワークとして県下の民俗行事などの写真を撮っておられる。
私の知人にも、京都でサラリーマンをしながら小説を書いている鏡清澄さん(筆名)という方がいる。奈良を舞台にした中編小説が2編載った『迦陵頻伽(がりょうびんが)奈良に誓う』(ブイツーソリューション刊 1500円)という本を出版された。奥さんとアイデアを出し合いながら執筆されたとのことで、奈良の名所がたくさん登場し、観光情報小説としても楽しめる本である。
 | 迦陵頻伽 奈良に誓う鏡 清澄ブイツーソリューションアイテムの詳細(「なか見!検索」ができる) |
筆者の鏡さんからコメントをいただいたので、以下に紹介する。《『奈良に誓う』は東京の陶器店の若き女性店長あずさが主人公で、あずさの仕事、奈良市西ノ京の旅館の青年後継者である貴一との出会い、二人でめぐる奈良の自然と文化が描かれる。美しい四季折々の情景は心を浄化し、歴史に裏打ちされた文化は人の生き方を深化させていく。『萬世同薫』は貴一が奈良・唐招提寺の開祖である鑑真和上と、和上に関係する人たちから、その精神性の高さを学んでいく話である。なかでも芭蕉が鑑真和上像を拝して詠んだ俳句「若葉して御めの雫ぬぐはばや」の新解釈は、和上と芭蕉の生き方を知れば頷けるものではないだろうか》。
《両編を通じて、素晴らしい場所である奈良と、奈良に育まれる若者の姿が描かれているが、「ところは違っても同じ思いを持つ人がいて、時は変わっても同じように薫る」という言葉は、人間への期待の熱いメッセージである》《この本の魅力は大きく括ると次の三点である。①臨場感あふれる奈良の描写に、多くの読者は奈良へ行きたくなるだろう。②歴史や文学などの事実に接し、知的興奮を覚えるだろう。③奈良の真の価値は、心を見つめ、心を深める点にあることを知るだろう》。
アマゾンでのカスタマーレビューも、好意的だ。《古都奈良の奥深さを理解させるのに、この独特なアプローチはみごとに成功している。奈良に住み、奈良の歴史について長く研究してきた著者による渾身の作である》《奈良に行った読者は、自分を重ねて、まだ行ったことのない読者は奈良への憧れを抱きながら引き込まれていく本である。是非一読を!》《唐招提寺や若草山のお水取りなどを中心に描写が見事に記述されていて、まるでその場にいるような錯覚を感じさせられます》等々。
お3人とも、サラリーマン生活の中で自らのライフワークを発見し、それを着々と実現されている姿は、ご立派である。とても私などマネのできることではないが、奈良を思う気持ちは同じなので、少しでもあやかりたいと思う。
※トップ写真は、私が撮った県指定無形民俗文化財「江包(えっつみ)・大西のお綱祭り」(09.2.11撮影)。『奈良大和路の年中行事』にも『奈良大和の祭り』にも、もっと良い写真が載っているので、ぜひお買い求めいただきたい。


























この本を読んで、一人でも多くの人が奈良へ来て下されば良いなと思っています。
美しい奈良の自然や心に響く年中行事は、人の気持ちを健やかにしてくれるように思います。そして、心の再生を通じて、世の中を少しでも良くしていけないだろうかと思い、『迦陵頻伽 奈良に誓う』と『迦陵頻伽 萬世同薫』を書きました。
奈良が今、世の中や人々に貢献できることは何なのか。奈良を愛する皆さんと考え、行動していきたいです。
奈良検定対策に箸尾を歩いていたら、
偶然「戸立て祭」に出くわしました。
うれしいご縁でした。
奈良にもあんな見事なだんじりがあるんですね。
先日ようやく手に入った「チャレンジ奈良検定」の本を読んでいたら、
奈良県の総県土72%に住む県民は僅か6%とのこと。
東京で奈良県の過疎対策シンポジウムが開催されるとのことで気になっていましたが、
こんな数字になっているとは驚きました。
過疎地域での年中行事、
維持していくことはできるのでしょうか。
大変気になります。
> 奈良が今、世の中や人々に貢献できることは何なのか。
> 奈良を愛する皆さんと考え、行動していきたいです。
もっと早く紹介させていただこうと思っていましたが、今頃になってしまい、失礼しました。鏡さんのご著書には、奈良への愛情がいっぱい詰まっています。一緒に奈良を盛り上げてまいりましょう。
> 風土が感じ取れていいですね。
『奈良大和路の年中行事』には、見たことも聞いたこともないお祭りがたくさん登場します。奈良は祭りの宝庫だったのです。
> 奈良県の総県土72%に住む県民は僅か6%とのこと。
つまり28%の土地(奈良盆地)に県民の94%が住んでいる、ということでしたっけ。
> 過疎地域での年中行事、維持していくことは
> できるのでしょうか。大変気になります。
以前、東吉野村の「小川祭り」を見物に行きました。
http://www.news.janjan.jp/area/0510/0510234170/1.php
すると、なんと知人(ある証券会社の偉いさん)が太鼓台(巨大な御輿)を担いでいるではありませんか。何でも「祭りに備えて帰省した」とのこと。ほとんどの担ぎ手がそういう方だとか。だから祭りは日曜日に開催されています。
過疎の村が知恵を絞って伝統行事を支え続けている姿に、感銘を受けました。
私は以前に金剛寺の御朝拝式でコメントさせていただいたことがあります。
その節は「ならグルグル散歩」のマネジャーと名乗っておりました。
この御朝拝式も誌面で紹介しております。
ほとんどが民俗行事で初公開となると凡そ半分ぐらいでしょうか。
そのためか、本のコードでは旅ジャンルなのですが民俗本として取り扱っているケースが多いようです。
早期定年で辞めた理由のひとつに、私が住んでいる奈良県、大和郡山市で貢献、寄与するものなんなのか思ったことです。
それが民俗行事の記録でした。
やむなく中止される行事が徐々に増えつつありました。
60歳定年を待っていたら行事が消えてしまう。
消える前に記録をしなければと思い立ってのことでした。
奈良県には数多くの知られざる行事があり、それを知ってもらって奈良県を学習してほしい。
その手段に、取材させてもらったものをホームページで公開することしたわけです。
当事は出版する考えすらなかったのですが、編集者が出しましょうの一言で世に出てしまいました。
そのいきさつは11月6日の奈良新聞「なら民俗通信」で紹介されています。
編集の際、鹿谷さんには随分と助言をいただいたおかげで満足できる形になりました。
お二人はもちろんのこと、取材させていたいた方々に感謝、感謝でございます。
民俗博物館での行事写真展では「これだけのものがあったとは全く知らなかった」と多くの方から声がでました。
地域の行事を再発見する大切さを知ったといいます。
後世に記録を残す、これは私自ら与えた課題であり、住む地域への貢献、寄与と考えております。
長々と書き記したことご容赦ください。
> 金剛寺の御朝拝式でコメントさせていただいたことがあります。
おお、本当ですね。「上北山 イズ ミステリー」にコメントをいただいています。このときにリンクを貼らせていただいた御朝拝式の写真が、『奈良大和路の年中行事』に載っているではありませんか!
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/0233529f13849a14bf9e5cf6aab2ac0d
> ほとんどが民俗行事で初公開となると凡そ半分ぐらいでしょうか。
春日祭も春日大社の御田植神事も、全く知りませんでした。奈良市に30年も住んでいるのに。大神神社の繞道祭(にょうどうさい)は、名前しか知りませんでした。
> 60歳定年を待っていたら行事が消えてしまう。
> 消える前に記録をしなければと思い立ってのことでした。
本当に意義のあるお仕事をされましたね。なかなか、そこまで踏み切れるものではありません。
> 民俗博物館での行事写真展では「これだけのものがあった
> とは全く知らなかった」と多くの方から声がでました。
これも素晴らしい活動です。地元の方はさぞお喜びになったことでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/mnjr05gob/e/4a8efa9245a00d84e565e42b518fd572
鹿谷さんが書かれているように、田中さんのご著書は「写真による大和の民俗誌」です。田中さんが撮り尽くせないほどの民俗行事が、県下にはまだたくさんあると思います。『奈良大和路の年中行事』の続編を(少し気が早いですが)期待しています。
奈良のことを広く知って欲しいと思うのと同時に、本来の姿で触れ、深く感じて欲しいなと思います。
私は今までぼんやりとお能を「美しい…」と見てきました。
それも良いのですが。
謡曲の本を読むともっと深く感じることができるようになりました。
その舞台となった場所に足を運んだり歴史的背景を知ることによって、さらに楽しめるようになった気がします。
神社仏閣へ足を運ぶときも、お祭りも、やはり同じことのように、最近は思います。
> ブログへのトラックバックをありがとうございました。
いえ、こちらこそ、当ブログを大きく取り上げていただき、有り難うございました。いただいたお言葉を励みに、頑張って書き続けたいと思います。
http://2010aoniyoshi.at.webry.info/200912/article_5.html
> 舞台となった場所に足を運んだり歴史的背景を知ることによって、
> さらに楽しめるようになった気がします。神社仏閣へ足を運ぶ
> ときも、お祭りも、やはり同じことのように、最近は思います。
全くその通りです。「知れば知るほど、奈良はおもしろい」。お祭りの所作も、一つ一つに意味があって興味は尽きません。奈良にはそんな資源が、いっぱい地下に埋まっています。
埋蔵資源の掘り起こしに、お互いに頑張りましょう。