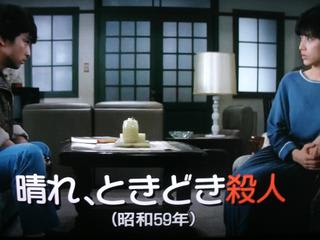原題:『婚期』
監督:吉村公三郎
脚本:水木洋子
撮影:宮川一夫
出演:若尾文子/野添ひとみ/京マチ子/船越英二/三木裕子/高峰三枝子/北林谷栄
1961年/日本
婚期を巡る笑いの「温度差」について
本作は吉村公三郎監督の傑作といっても過言ではないと思うが、例えば、野添ひとみが演じる唐沢鳩子が「もう」24、5歳になろうとしているのだから結婚を考えろと急かされたり、若尾文子が演じる唐沢波子が「既に」29歳の「オールドミス」で婚期を逃しているというような扱いで、今から観るならば明らかに10歳はズレており、それは今観るから面白いと思える視点であり、当時、同世代の女性が笑えたのかどうかはよく分からない。因みに、当時、野添ひとみは23歳で既に川口浩と結婚しており、若尾文子は27歳で未婚である。妻の静を演じている京マチ子が36歳なのは妥当だとしても、驚くべきことにお手伝いの「婆や」を演じる北林谷栄は当時まだ49歳である。さすがに北林は役作りをした上でおそらく60歳代の女性を演じていると思うが、逆にその「婆や」の、唐沢家住人たちの扱い方が酷くて今となっては笑えない。「ハゲネタ」は当時も今も笑えない人は必ずいるだろう。
因みに主人公の唐沢卓夫が寝室で読んでいる本は翻訳されたばかりのベン・ヘクト(Ben Hecht)の『情事の人びと(The Sensualists)』(新庄哲夫訳 1960年)であるが、今は読まれていないようである。