<公表した本、論文など>
2016年に出版された本は以下の3冊です。
「タヌキ学入門--かちかち山から3.11まで 身近な野生動物の意外な素顔」、誠文堂新光社。
これは一般向けにタヌキのことを紹介したもので、生物学の話だけでなく、昔話などにも言及しました。
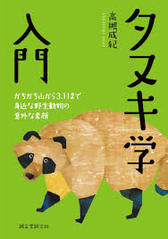
「玉川百科 こども博物誌 動物のくらし」、玉川大学出版部。
これは小学生の低学年を対象にしたもので、哺乳類だけでなく、鳥類、寮生爬虫類、魚類も含み、それぞれの専門家にわかりやすく書いてもらいました。イラストがすばらしく、よいできになりました。

「増補版野生動物管理−理論と技術−」,羽山伸一・三浦慎悟・梶光一・鈴木正嗣,編、文英堂出版,東京。
これは専門書で、このなかにつぎの2つを書きました。
生態系と野生動物のインパクト.:117-142.
食性分析.:295-297.
論文は4編書きました。
足立高行・植原 彰・桑原佳子・高槻成紀.2016.
山梨県乙女高原のテンの食性の季節変化.
哺乳類科学,56: 17-25.
足立高行・桑原佳子・高槻成紀,2017
福岡県朝倉市北部のテンの食性−シカの増加に着目した長期分析.
保全生態学,21: 203-217.
この2つは大分の足立さんがテンの糞を長いあいだ根気強く分析されたもののまとめをお手伝いしたもので、乙女高原のテンの糞は植原さんが採取したものです。福岡のものは11年間におよぶもので、そのあいだにシカが増えて、テンが食べる昆虫や低木の果実などが減ったことがわかりました。
Yamao, K, R. Ishiwaka, M. Murakami and S. Takatsuki. 2016
Seasonal variation in the food habits of the Eurasian harvest mouse (Micromys minutus) from western Tokyo, Japan.(東京西部のカヤネズミの食性の季節変化)
Zoological Science, 33: 611-615.
これは日の出町廃棄物処分場跡地に復活したススキ群落にもどってきたカヤネズミの食性を糞分析で解明したもので、夏の昆虫、冬の種子と季節変化があることが初めてわかりました。またダンゴムシやシデムシなど地表を歩く昆虫などが食べられているという意外なことも初めて明らかになりました。
Morinaga, Y., J. Chuluun and S. Takatsuki. 2016.
Effects of grazing forms on seasonal body weight changes of sheep and goats in north-central Mongolia : a comparison of traditional nomadic grazing and experimental sedentary grazing, (伝統的遊牧と固定飼育によるヒツジとヤギの体重の季節変化の違い:モンゴル北部での事例)
Nature and Peoples, in press
これは伝統的な遊牧で育てた場合と実験的に固定飼育した場合、ヒツジやヤギの体重がどう違うかを比較したもので、固定するとやせることがわかりました。私たちは事情を知らないで「モンゴルは土地面積に対する生産性が低い」と批判する声があるのを、それには意味があるのだということを示したいと思いました。
書評
高槻成紀, 2016.
日本のイヌ- 人のともに生きる 菊水健史・長澤美保・外池亜希子・黒い眞器.
JVM. 69: 197.
高槻成紀,2016.
「女も男もフィールドへ」椎野若菜・的場澄人(編)(2016)古今書院
哺乳類科学, 56: 293-295.
エッセー、解説など
高槻成紀, 2016. いきものばなし10, ニホンジカ. ワンダーフォーゲル,2016.2: 156-157.
高槻成紀, 2016. 唱歌「ふるさと」から里山の変化を考える. 環境会議, 2016春: 40-45.
高槻成紀, 2016. 麻布大学いのちの博物館を語る. 日本農学図書館協議会誌, 181: 7-14.
高槻成紀, 2016. 東京のタヌキ。東京人, 372(2016年7月): 7.
高槻成紀, 2016. 子供たちに動物の息吹を伝えたい.週間読書人,2016.8.5
高槻成紀, 2016. シカ研究者がみた最近の日本の山. 木の目草の芽, 125: 1-4.














