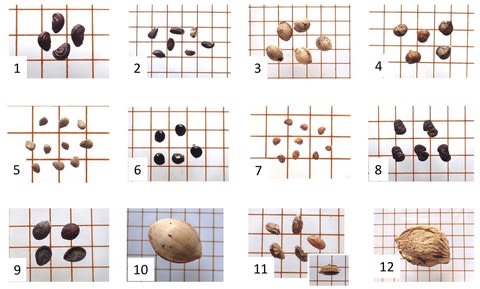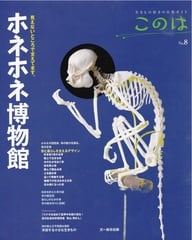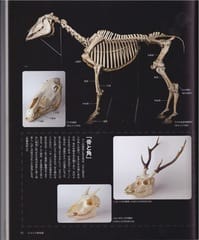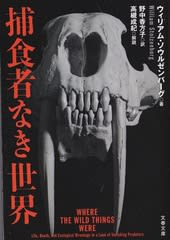2018.5.3
モンゴル北部の森林ステップの草地群落への放牧の影響:放牧と非放牧の比較
高槻成紀・佐藤雅俊・森永由紀
Grassland Science, 64: 157-214.
2002年からモンゴルに通っています。最初はモウコガゼルの調査から始まったのですが、その後家畜と草原の関係を調べるようになって今日に至っています。モンゴル中央の北部はモンゴルとしては比較的降水量があり、山の北斜面には森林があるので「森林ステップ」と呼ばれています。もっと北のロシアに行けばタイガになる、草原と森林の移行帯です。その一つとしてブルガンという場所があり、そこで放牧影響を調べた調査結果が論文になりました。こちら
要旨:モンゴルでは牧畜のあり方が移牧から定着に変化したため、草原が過放牧になり、群落に変化をもたらしている。この調査はモンゴル北部の深林ステップで長い時間家畜を排除した好例を見つけたので、放牧が草原にどのような影響をもたらすかを示そうとした。ブルガン飛行場は1950年代から柵をしてきたので、放牧された場所とされていない場所を比較できる。そこで群落構造、種組成、生育形に着目して柵の内外を比較した。植物量は柵外で40 g/m2であり、柵外(305 g/m2)の7分の1にすぎず、出現種数も半分ほどだった。柵内では草丈は30-40cmあったが、柵外では10cm未満だった。柵内では直立型、分枝型、大型叢生型が多いが、柵外では小型叢生型と匍匐型が優占的だった。柵内では微地形に応じて優占種に違いが見られたが、柵外ではCarex duriusculaというスゲとPotentilla acaulis(キジムシロ属)という匍匐型が優占していた。すなわち放牧影響はもともとある微地形の影響を「マスク」すると言える。この調査は、放牧による群落への影響を生育型を用いることで有効に示せることを示した。

A: 柵内外の比較、B:柵内の様子、C:柵外の様子、D: Potentilla acaulis
Effects of grazing on grassland communities of the forest-steppe of northern Mongolia: a comparison of grazed versus ungrazed places
Seiki Takatsuki, Masatoshi Sato, and Yuki Morinaga
Abstract
Overgrazing of grasslands in the Mongolian steppes resulting from a transition from pastoral to sedentary livestock production has led to significant changes in the plant communities. This study aimed to show how livestock grazing affects steppe vegetation in northern Mongolia by a good example of a long-termed exclusion of grazing. The Bulgan Airport in northern Mongolia has been fenced since the 1950s and thus is suitable to compare grazed and ungrazed plant communities. We studied plots both inside and outside the fence with reference to community structure, species composition, and growth form. Plant biomass for the outside plots averaged (40 g/m2) less than one-seventh of that inside the fence (305 g/m2), and average species number per plot was about half of that inside the fence. Height of plants inside the fence ranged from the ground surface to 30 - 40 cm, whereas most of the plants outside were less than 10 cm tall. Erect, branched, and tall tussock form plants were reduced outside the fence, and short tussock and prostrate form plants became dominant. Microtopography resulted in different dominant plants inside the fence whereas only Carex duriuscula, a sedge, and Potentilla acaulis, a short growing prostrate forb, prevailed outside. That is, grazing as a factor effecting plant communities prevailed and "masked" microtopography outside the fence. It was shown that the use of growth form is effective to evaluate vegetation changes by grazing.
モンゴル北部の森林ステップの草地群落への放牧の影響:放牧と非放牧の比較
高槻成紀・佐藤雅俊・森永由紀
Grassland Science, 64: 157-214.
2002年からモンゴルに通っています。最初はモウコガゼルの調査から始まったのですが、その後家畜と草原の関係を調べるようになって今日に至っています。モンゴル中央の北部はモンゴルとしては比較的降水量があり、山の北斜面には森林があるので「森林ステップ」と呼ばれています。もっと北のロシアに行けばタイガになる、草原と森林の移行帯です。その一つとしてブルガンという場所があり、そこで放牧影響を調べた調査結果が論文になりました。こちら
要旨:モンゴルでは牧畜のあり方が移牧から定着に変化したため、草原が過放牧になり、群落に変化をもたらしている。この調査はモンゴル北部の深林ステップで長い時間家畜を排除した好例を見つけたので、放牧が草原にどのような影響をもたらすかを示そうとした。ブルガン飛行場は1950年代から柵をしてきたので、放牧された場所とされていない場所を比較できる。そこで群落構造、種組成、生育形に着目して柵の内外を比較した。植物量は柵外で40 g/m2であり、柵外(305 g/m2)の7分の1にすぎず、出現種数も半分ほどだった。柵内では草丈は30-40cmあったが、柵外では10cm未満だった。柵内では直立型、分枝型、大型叢生型が多いが、柵外では小型叢生型と匍匐型が優占的だった。柵内では微地形に応じて優占種に違いが見られたが、柵外ではCarex duriusculaというスゲとPotentilla acaulis(キジムシロ属)という匍匐型が優占していた。すなわち放牧影響はもともとある微地形の影響を「マスク」すると言える。この調査は、放牧による群落への影響を生育型を用いることで有効に示せることを示した。

A: 柵内外の比較、B:柵内の様子、C:柵外の様子、D: Potentilla acaulis
Effects of grazing on grassland communities of the forest-steppe of northern Mongolia: a comparison of grazed versus ungrazed places
Seiki Takatsuki, Masatoshi Sato, and Yuki Morinaga
Abstract
Overgrazing of grasslands in the Mongolian steppes resulting from a transition from pastoral to sedentary livestock production has led to significant changes in the plant communities. This study aimed to show how livestock grazing affects steppe vegetation in northern Mongolia by a good example of a long-termed exclusion of grazing. The Bulgan Airport in northern Mongolia has been fenced since the 1950s and thus is suitable to compare grazed and ungrazed plant communities. We studied plots both inside and outside the fence with reference to community structure, species composition, and growth form. Plant biomass for the outside plots averaged (40 g/m2) less than one-seventh of that inside the fence (305 g/m2), and average species number per plot was about half of that inside the fence. Height of plants inside the fence ranged from the ground surface to 30 - 40 cm, whereas most of the plants outside were less than 10 cm tall. Erect, branched, and tall tussock form plants were reduced outside the fence, and short tussock and prostrate form plants became dominant. Microtopography resulted in different dominant plants inside the fence whereas only Carex duriuscula, a sedge, and Potentilla acaulis, a short growing prostrate forb, prevailed outside. That is, grazing as a factor effecting plant communities prevailed and "masked" microtopography outside the fence. It was shown that the use of growth form is effective to evaluate vegetation changes by grazing.