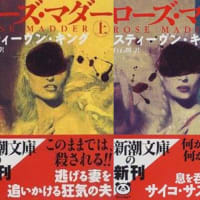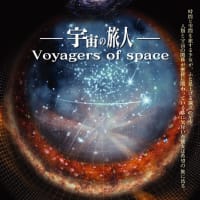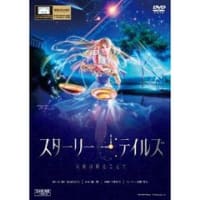※ イオンエンジン燃焼実験の様子
(TOP画像提供:JAXA)
日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時
場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)
講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010
「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」
話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社
宇宙・情報システム事業部)
サブタイトル:
2010年6月13日、深夜。
ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。
一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。
そして小さな輝きだけが残った。
60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…
■故郷への旅支度
故郷を目指す、はやぶさの旅路は続く。
交信が回復したといっても。
僅か1bit/sの、文字通りクモの糸のような。
それも、30分周期に数分のみという。
微かな、微かなはやぶさとの絆。
その、キャリアレベルを上げ下げするだけのチャネルから。
じりじりと、はやぶさの状態を把握し、回復に向けたコマンドを
投入し続ける運用班。
恐らくは、地表衝突による化学燃料ヒドラジンの全流出。
それに伴う、姿勢制御用化学スラスタの無効化によって無制御な
高速スピン状態に陥っていた状況に対しては。
イオンエンジンの中和器から、キセノンガスの直接噴射により対処。
(イオンエンジン本体(イオン源)は、はやぶさの推力軸を通る設計
となっているため、そのジンバル(推射角調整装置)を最大に
振っても、微力なトルクモーメントしか得られない。
一方、中和器は45度の角度を持たせて作られているため、
そこから生ガスを推射することで、結構なトルクを得ることが出来る)
それによって、はやぶさのスピンを安定化、更にそのアンテナを地球に
向けることに成功。
中利得アンテナを使った8bit/s通信(後に、32bit/sまで向上)
が可能となったことや、キセノンガスによる姿勢制御の術を入手した
ことで、はやぶさとの絆はクモの糸からナイロンザイルへと昇格した。
キセノンガスの想定外の使用による帰路の燃料不足の懸念も。
スピン安定の結果、イオンエンジンをトルク源と出来るようになった
ことを受けて、中和器からの直接のキセノンガス噴射制御を行う
必要が低減したために、解消。
(ちなみに、このときのキセノンガスの残量は、約42~44Kgと
推定されていた。
出立時の積載量は66Kgなので、往路で約1/3程を費消したこと
となる。
更に言えば、ヒドラジンの出立時積載量は64Kg。
イトカワ上空決戦終了時にどれくらい残存していたのかは不明だが、
恐らく相当量は残っており、それらが全て流出したことになる)
(註)
この辺りの状況については、「イオンエンジンによる小惑星探査機
「はやぶさ」の帰還運用」JAXAに詳述されている。
(註2)
なお、上記の論文の中では、さらりと書かれてはいるが…。
この時期、イオンエンジンへの火入れは相当に危険だったようである。
何せ、はやぶさ本体の状態がよく分からない中で、高電圧を必要と
するイオンエンジンに点火しようというのであるから…。
この辺りの技術者の葛藤については、「イオンエンジンが起こした奇跡」
NECに詳述されている。
更には、タッチダウン前に発生した二軸(X,Y)のリアクション
ホイール(RW)の故障による姿勢制御手段のロストに対しては、
本来は外乱要因である太陽風を利用した姿勢制御を導入することで、
三軸の姿勢制御術を実現。
Z軸のみは、健在なRWによる制御が可能であったが、X軸とY軸は
他の軸に力が加わったことによるトルクを応用した組み合わせ制御+
太陽風とという離れ業で姿勢制御を実現することとなった。
実に、イカロスに先んじること3年前。
はやぶさは、太陽風を姿勢制御補助動力とした宇宙帆船として、
蘇っていた訳である。
勿論、開発当初にこうした運用が想定されていた訳では全く無い。
そして。
機体内に漏れ出して、残留していたヒドラジン。
可燃性のガスをそのままには出来ないために、極低温から慎重に機体を
ベーキング(暖めること)することで、ガスを蒸発させる。
更に。
やはり、ヒドラジンの流出により、低温障害から全放電してしまった
バッテリーについては。
このままでは、太陽電池パドルに太陽が当たっているときに直接作り
出される電力しか利用できないため、地球帰還のためのイオンエンジン
の噴射はおろか、サンプル採取後のカプセルの容器密閉すら出来て
いない状態だったために。
製造メーカーである古川電気の発案により補充電回路からのバイパス
給電と充電を実現。
(これも、爆発のリスクと隣り合わせの慎重な作業だった)
…と。
降りかかる、あらゆる災厄に対して。
一つひとつ、消しこみをかけていくJAXAをはじめとしたはやぶさを
支え続ける人々。
それらの一連の作業は。
2007年4月まで、足掛け1年以上も費やして慎重に積み重ねられて
いった。
その結果。
はやぶさは、不死鳥の如く甦った訳であるが。
その1年半近いタイムロスは、地球とイトカワ、両者の自転の影響により
当初予定していた地球帰還軌道にはやぶさを投入することが不可能となった
ことを示唆していた。
こうして。
ようやく出立の準備が整った、はやぶさ。
その、地球帰還を2010年6月に再設定した、新たな旅路が始まること
となった。
時に、西暦2007年4月25日。14時30分のことである。
■技術者の矜持
氏の講演では、この次にはやぶさを襲った最大のピンチについての
エピソードが開陳された。
講演中でも、
「文字にすることはできないので…」
と仰られていたので、少しぼかしながらもその貴重なエピソードを
紹介することとしたい。
※ 但し、先日NECのHPに、当事者の方によるほぼ詳細な話が
UPされていたので、ここでも開示度をググッと向上することに。
2009年11月9日。
地球に向けて、順調な旅路を続けていたはやぶさにとって、またもや
大きな試練が襲った。
イオンエンジンの完全停止、である。
この頃、はやぶさは、その四基搭載したイオンエンジンのうち、
老朽化から推力が低下したCを何とか駆動して飛行していた。
機動計算上、更に推力UPを図る必要が生じて、Dに火を入れた
ところ、異常停止。
他のA,Bも起動不能。
このままでは、地球帰還が更に3年延びる瀬戸際にはやぶさは
立たされてしまった。
その際の、各エンジンの状況について以下に総括してみる。
A:出立当初より不調が確認され、予備としての意味もあって
運用を停止中。
稼働時間は、10時間。
B:イトカワ近傍(といっても、1万キロ以上は離れていた訳
であるが)にて再起動確認を行った際に、中和器の劣化に
よる電圧異常が発見されたため、停止中。
稼働時間は、9500時間。
C:復路でも使用していたが、途中でやはり中和器の劣化が
確認されたため、温存策として出力を抑えて運用中。
稼動時間は、8000時間以上。
(Cのみ、この時点での稼動時間データが確認できず。
どなたかご存知であれば、教えてください)
D:今回、推力UPポイントに到達したことを受けて、温存
していたDに火を入れたものの、ご他聞に漏れず中和器
の電圧異常上昇が発生し、ブレーカーにより緊急停止。
その値は閾値を完全に超えており、Dの中和器が事実上
昇天したことを意味していた。
稼動時間は15000時間!の頑張り屋さんだった…。
ここから、あの伝説のA×Bのクロス運用が始まるのだが、
氏の紹介していただいたエピソードは、それに関するもので
ある。
(この稿、続く)
(TOP画像提供:JAXA)
日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時
場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)
講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010
「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」
話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社
宇宙・情報システム事業部)
サブタイトル:
2010年6月13日、深夜。
ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。
一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。
そして小さな輝きだけが残った。
60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…
■故郷への旅支度
故郷を目指す、はやぶさの旅路は続く。
交信が回復したといっても。
僅か1bit/sの、文字通りクモの糸のような。
それも、30分周期に数分のみという。
微かな、微かなはやぶさとの絆。
その、キャリアレベルを上げ下げするだけのチャネルから。
じりじりと、はやぶさの状態を把握し、回復に向けたコマンドを
投入し続ける運用班。
恐らくは、地表衝突による化学燃料ヒドラジンの全流出。
それに伴う、姿勢制御用化学スラスタの無効化によって無制御な
高速スピン状態に陥っていた状況に対しては。
イオンエンジンの中和器から、キセノンガスの直接噴射により対処。
(イオンエンジン本体(イオン源)は、はやぶさの推力軸を通る設計
となっているため、そのジンバル(推射角調整装置)を最大に
振っても、微力なトルクモーメントしか得られない。
一方、中和器は45度の角度を持たせて作られているため、
そこから生ガスを推射することで、結構なトルクを得ることが出来る)
それによって、はやぶさのスピンを安定化、更にそのアンテナを地球に
向けることに成功。
中利得アンテナを使った8bit/s通信(後に、32bit/sまで向上)
が可能となったことや、キセノンガスによる姿勢制御の術を入手した
ことで、はやぶさとの絆はクモの糸からナイロンザイルへと昇格した。
キセノンガスの想定外の使用による帰路の燃料不足の懸念も。
スピン安定の結果、イオンエンジンをトルク源と出来るようになった
ことを受けて、中和器からの直接のキセノンガス噴射制御を行う
必要が低減したために、解消。
(ちなみに、このときのキセノンガスの残量は、約42~44Kgと
推定されていた。
出立時の積載量は66Kgなので、往路で約1/3程を費消したこと
となる。
更に言えば、ヒドラジンの出立時積載量は64Kg。
イトカワ上空決戦終了時にどれくらい残存していたのかは不明だが、
恐らく相当量は残っており、それらが全て流出したことになる)
(註)
この辺りの状況については、「イオンエンジンによる小惑星探査機
「はやぶさ」の帰還運用」JAXAに詳述されている。
(註2)
なお、上記の論文の中では、さらりと書かれてはいるが…。
この時期、イオンエンジンへの火入れは相当に危険だったようである。
何せ、はやぶさ本体の状態がよく分からない中で、高電圧を必要と
するイオンエンジンに点火しようというのであるから…。
この辺りの技術者の葛藤については、「イオンエンジンが起こした奇跡」
NECに詳述されている。
更には、タッチダウン前に発生した二軸(X,Y)のリアクション
ホイール(RW)の故障による姿勢制御手段のロストに対しては、
本来は外乱要因である太陽風を利用した姿勢制御を導入することで、
三軸の姿勢制御術を実現。
Z軸のみは、健在なRWによる制御が可能であったが、X軸とY軸は
他の軸に力が加わったことによるトルクを応用した組み合わせ制御+
太陽風とという離れ業で姿勢制御を実現することとなった。
実に、イカロスに先んじること3年前。
はやぶさは、太陽風を姿勢制御補助動力とした宇宙帆船として、
蘇っていた訳である。
勿論、開発当初にこうした運用が想定されていた訳では全く無い。
そして。
機体内に漏れ出して、残留していたヒドラジン。
可燃性のガスをそのままには出来ないために、極低温から慎重に機体を
ベーキング(暖めること)することで、ガスを蒸発させる。
更に。
やはり、ヒドラジンの流出により、低温障害から全放電してしまった
バッテリーについては。
このままでは、太陽電池パドルに太陽が当たっているときに直接作り
出される電力しか利用できないため、地球帰還のためのイオンエンジン
の噴射はおろか、サンプル採取後のカプセルの容器密閉すら出来て
いない状態だったために。
製造メーカーである古川電気の発案により補充電回路からのバイパス
給電と充電を実現。
(これも、爆発のリスクと隣り合わせの慎重な作業だった)
…と。
降りかかる、あらゆる災厄に対して。
一つひとつ、消しこみをかけていくJAXAをはじめとしたはやぶさを
支え続ける人々。
それらの一連の作業は。
2007年4月まで、足掛け1年以上も費やして慎重に積み重ねられて
いった。
その結果。
はやぶさは、不死鳥の如く甦った訳であるが。
その1年半近いタイムロスは、地球とイトカワ、両者の自転の影響により
当初予定していた地球帰還軌道にはやぶさを投入することが不可能となった
ことを示唆していた。
こうして。
ようやく出立の準備が整った、はやぶさ。
その、地球帰還を2010年6月に再設定した、新たな旅路が始まること
となった。
時に、西暦2007年4月25日。14時30分のことである。
■技術者の矜持
氏の講演では、この次にはやぶさを襲った最大のピンチについての
エピソードが開陳された。
講演中でも、
「文字にすることはできないので…」
と仰られていたので、少しぼかしながらもその貴重なエピソードを
紹介することとしたい。
※ 但し、先日NECのHPに、当事者の方によるほぼ詳細な話が
UPされていたので、ここでも開示度をググッと向上することに。
2009年11月9日。
地球に向けて、順調な旅路を続けていたはやぶさにとって、またもや
大きな試練が襲った。
イオンエンジンの完全停止、である。
この頃、はやぶさは、その四基搭載したイオンエンジンのうち、
老朽化から推力が低下したCを何とか駆動して飛行していた。
機動計算上、更に推力UPを図る必要が生じて、Dに火を入れた
ところ、異常停止。
他のA,Bも起動不能。
このままでは、地球帰還が更に3年延びる瀬戸際にはやぶさは
立たされてしまった。
その際の、各エンジンの状況について以下に総括してみる。
A:出立当初より不調が確認され、予備としての意味もあって
運用を停止中。
稼働時間は、10時間。
B:イトカワ近傍(といっても、1万キロ以上は離れていた訳
であるが)にて再起動確認を行った際に、中和器の劣化に
よる電圧異常が発見されたため、停止中。
稼働時間は、9500時間。
C:復路でも使用していたが、途中でやはり中和器の劣化が
確認されたため、温存策として出力を抑えて運用中。
稼動時間は、8000時間以上。
(Cのみ、この時点での稼動時間データが確認できず。
どなたかご存知であれば、教えてください)
D:今回、推力UPポイントに到達したことを受けて、温存
していたDに火を入れたものの、ご他聞に漏れず中和器
の電圧異常上昇が発生し、ブレーカーにより緊急停止。
その値は閾値を完全に超えており、Dの中和器が事実上
昇天したことを意味していた。
稼動時間は15000時間!の頑張り屋さんだった…。
ここから、あの伝説のA×Bのクロス運用が始まるのだが、
氏の紹介していただいたエピソードは、それに関するもので
ある。
(この稿、続く)
 | 天文マニア養成マニュアル |
| クリエーター情報なし | |
| 恒星社厚生閣 |