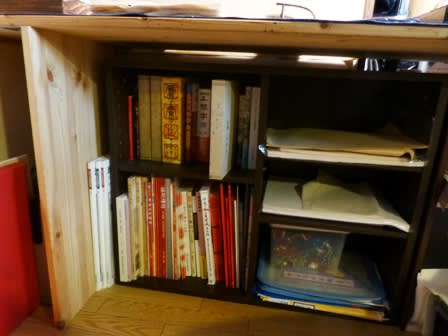釣り鐘墨
釣り鐘墨?
聞き慣れない言葉です。

自分で言うのは何ですが、写真がきれいでしょ!
キャノンEOS7Dでマクロレンズ60mmで撮りました。
今日の画像はこれ一枚です。
釣り鐘墨とは拓本取りに使用する墨で、底の部分を使います。
と先生が言っていました。
拓本取りには湿拓と乾拓がありますが、ほとんどはこの釣り鐘墨を使った乾拓のようです。
乾拓は石碑に紙を当てて、紙の上から摺る方法です。
湿拓は石碑に墨を塗りますので、所有者にお願いしたり準備から始まって2時間くらいかかるようです。
どちらも、画箋紙が必要ですが、特にビニールひもを持って行くと良いようです。
石碑に画箋紙を当てるのですが、上下部分をビニールひもなどで固定すると、風に飛ばされることなく摺ることができるとのことです。
墨友会の研修会で、松本美術館で開催された上条信山展に伺いましたが、この時に乾拓の試しコーナーがあり体験しました。
紙がずれたりで、乾拓も結構難しかったですね。
今回は釣り鐘墨をご紹介いたしました。
写真だけを褒めていただければ幸いです。
萬 鶴