
★ショパン:ピアノ・ソナタ第2番・第3番
(演奏:マウリツィオ・ポリーニ)
1.ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 《葬送行進曲》
2.ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 作品58
(1984年録音)
昨晩久しぶりにオンタイムで投稿しようと思って、このディスクの記事を書き送信ボタンを押したら消えた・・・。
ワードで下書き推敲してコピペするといういつもの手順を怠るとこれだ。。。
ショックの余り不貞寝して・・・ショックでなくても寝る時間ではあったが・・・気を取り直してなんとかもう一度打ち込気力を奮い起こしました。
しかし、あの打ち込んだ記事はどこへ消えてしまったのだろう・・・ともういちど言ってみる。(^^;)
まさしく諸行無常ですな。
ならいいけど、徹底的に一部大乗仏教的虚無主義に陥った記事になりそうでやだな。
行く川の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず・・・
さて、このディスクはほぼ新譜としてオンタイムで手に入れました。
当時はまだクラシックを聴き始めたばかりで、それまでに耳にしていたショパンのピアノ・ソナタといえば、変ロ短調ソナタがアルゲリッチとポゴレリチ、ロ短調ソナタがアルゲリッチのみという状況でありました。
1987年版だったかのクラシック・ディスク一覧の特選記事をみて、チェックしていた中にあったこの盤も「聴きたいな」という感じで手に入れたと思うのですが、当代最高のピアニストはアシュケナージとポリーニでそれぞれの持ち味を遺憾なく発揮したディスクを活発に発表している・・・という雰囲気だったと思います。
ちょうどシンディ・ローパー派とマドンナ派に分かれてたように・・・というと語弊がありますでしょうか?(^^;)
そして私のポリーニ初体験は、数ある特選盤の中からシューベルトの後期ピアノ・ソナタ集とこのショパンのピアノ・ソナタ集を選んで手に入れて聴いたのがはじめですね。
ことショパンの変ロ短調ソナタに関して言えば、それまでに聴いていたのが霊感をダダ漏れのように垂れ流すアルゲリッチと、インスピレーションをそのままオトにしたようなポゴレリチだったので、「なんと地味な音楽なんだろう」と感じましたですね。
かっちりまとまっているんだけど、どこが面白い聴かせどころなんだろうかわからない・・・って。(^^;)
そのころはガイドの文献の評が頼りで、アシュケナージは穏健で万人向きの演奏であり、ポリーニはそれに対して硬派の本物志向の聴き手にこそ良さがわかるピアニストというイメージができあがっていました。
当時から第一人者との呼び声高かったふたりでありますが、ご本人同志の関係にかかわらずそれぞれの陣営からすると正と邪、他方の音楽をいいと認めることは踏み絵を踏むことにほかなりませんでしたね。
それこそこれまでの経験を経て、私は今なら両方いいとはっきり言えるんですけどね。
もちろん、いずれにも首をかしげたくなるところもありますが・・・。
で、「本物志向」を志向していた私は、ポリーニ派にならなきゃいけないような気がしたんで、アシュケナージを聴くことが大幅に遅れました。(^^;)
アシュケナージを認められるようになるまではエラく時間がかかったんですが、考えてみればポリーニのよさに気づくまでも結構時間がかかったような・・・。(^^;)
たしかに喧伝されていたポリーニの美質、「完璧な打鍵による磨き抜かれた音」というのは当時の私にもわかったんですが、クラシック音楽というより“変ロ短調ソナタ”そのものを聴き慣れていなかったことからアルゲリッチの奔放な演奏や、ポゴレリチの悪魔のいたずらのような演奏のほうがピンと来ていたのは間違いありません。
今回ポリーニによるこの2曲のソナタを聴いて、ピアニストは曲の構造を明らかにしつつ完全な音の世界を再構築することにこそ主眼を持っているのであって、曲の感傷にあるいは雰囲気に耽溺することを徹底的に忌避しているんだなということを感じました。
テクニックも音色も彼の持っている技術のすべてはまさにその目的に適ったモノであるとも感得しました。
その際に、近年の演奏で気になったアクセントやシンコペーションのキツさ、唐突さはありませんし、それがポリーニだと感じていればこそ近年の演奏の変化に驚いた・・・そういうことであるようです。
でも、以前感づかなかったことを気づく私がいる・・・。
ポリーニも変化していますが、私自身も変化している。
ディスクの中の音は変化していないはずなのに、それを感じる私の感覚は変化しているということです。
諸行無常だの、行く川の流れ・・・だの、同じことをしているようでいて感じ方はその時々に違う、20年という年月を経れば事ほど左様にこれほど違う。
1年でもこれの20分の1、もっと細かく切っても・・・今日と明日でもいくばくかは違うことになるはずです。
では、以前聴いたことから得た「知識」というのは何なんだろう・・・感覚からきているこれらの経験知は、もしかしたら「邪念」以外の何者でもないかもしれません。
先に述べたアシュケナージを聞くのが大幅に遅れたなどという件も、予断であり邪見の極みであるといわざるをえませんよね。
それを「ご縁」などと言ったりすることもあるようですが、結果的には誤った判断をしていたと思います。
話が大きくなってしまいましたが、結局は「いい音楽」にめぐり合うのかどうかではなく、今いま聴いている音楽をどのように聴き、そこで音の現象をどのように認識するかという問題だけ、昨日わたしが「捌きかた」といったことにも通じるのだと思いますが、そこにいかに集中するか・・・それしかないと思うようになりました。
ポリーニのショパンは全部、他にも多くのディスクを持ち、聴いて思うのは、これほどまでにテクニックばかりが喧伝され精神がたたえられているために、期待感が高まりすぎているんじゃないかということです。
何を聴くのかをハッキリさせて臨まないと、その「現象」の認識レベルでの捉えられ方の差が大きくなってしまう典型タイプのピアニストだと思います。
ある意味では、やはり玄人受けするピアニストという評価が正しいということになるのでしょうか?
このころのポリーニが「めちゃくちゃうまいけど、よさがわからない」という方、ポリーニだと思わずに聴かれることをお勧めしたいです。
「(あれだけすごいと騒がれている)ポリーニの、この演奏のどこがいいんだろう?」と思っている人もポリーニじゃないと思えば、「なんて凄い演奏なんだ」と思われると思いますよ。
今いま、目の前で鳴っている音響だけで音楽を味わえば・・・ね。(^^;)
(演奏:マウリツィオ・ポリーニ)
1.ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 《葬送行進曲》
2.ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 作品58
(1984年録音)
昨晩久しぶりにオンタイムで投稿しようと思って、このディスクの記事を書き送信ボタンを押したら消えた・・・。
ワードで下書き推敲してコピペするといういつもの手順を怠るとこれだ。。。
ショックの余り不貞寝して・・・ショックでなくても寝る時間ではあったが・・・気を取り直してなんとかもう一度打ち込気力を奮い起こしました。
しかし、あの打ち込んだ記事はどこへ消えてしまったのだろう・・・ともういちど言ってみる。(^^;)
まさしく諸行無常ですな。
ならいいけど、徹底的に一部大乗仏教的虚無主義に陥った記事になりそうでやだな。
行く川の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず・・・
さて、このディスクはほぼ新譜としてオンタイムで手に入れました。
当時はまだクラシックを聴き始めたばかりで、それまでに耳にしていたショパンのピアノ・ソナタといえば、変ロ短調ソナタがアルゲリッチとポゴレリチ、ロ短調ソナタがアルゲリッチのみという状況でありました。
1987年版だったかのクラシック・ディスク一覧の特選記事をみて、チェックしていた中にあったこの盤も「聴きたいな」という感じで手に入れたと思うのですが、当代最高のピアニストはアシュケナージとポリーニでそれぞれの持ち味を遺憾なく発揮したディスクを活発に発表している・・・という雰囲気だったと思います。
ちょうどシンディ・ローパー派とマドンナ派に分かれてたように・・・というと語弊がありますでしょうか?(^^;)
そして私のポリーニ初体験は、数ある特選盤の中からシューベルトの後期ピアノ・ソナタ集とこのショパンのピアノ・ソナタ集を選んで手に入れて聴いたのがはじめですね。
ことショパンの変ロ短調ソナタに関して言えば、それまでに聴いていたのが霊感をダダ漏れのように垂れ流すアルゲリッチと、インスピレーションをそのままオトにしたようなポゴレリチだったので、「なんと地味な音楽なんだろう」と感じましたですね。
かっちりまとまっているんだけど、どこが面白い聴かせどころなんだろうかわからない・・・って。(^^;)
そのころはガイドの文献の評が頼りで、アシュケナージは穏健で万人向きの演奏であり、ポリーニはそれに対して硬派の本物志向の聴き手にこそ良さがわかるピアニストというイメージができあがっていました。
当時から第一人者との呼び声高かったふたりでありますが、ご本人同志の関係にかかわらずそれぞれの陣営からすると正と邪、他方の音楽をいいと認めることは踏み絵を踏むことにほかなりませんでしたね。
それこそこれまでの経験を経て、私は今なら両方いいとはっきり言えるんですけどね。
もちろん、いずれにも首をかしげたくなるところもありますが・・・。
で、「本物志向」を志向していた私は、ポリーニ派にならなきゃいけないような気がしたんで、アシュケナージを聴くことが大幅に遅れました。(^^;)
アシュケナージを認められるようになるまではエラく時間がかかったんですが、考えてみればポリーニのよさに気づくまでも結構時間がかかったような・・・。(^^;)
たしかに喧伝されていたポリーニの美質、「完璧な打鍵による磨き抜かれた音」というのは当時の私にもわかったんですが、クラシック音楽というより“変ロ短調ソナタ”そのものを聴き慣れていなかったことからアルゲリッチの奔放な演奏や、ポゴレリチの悪魔のいたずらのような演奏のほうがピンと来ていたのは間違いありません。
今回ポリーニによるこの2曲のソナタを聴いて、ピアニストは曲の構造を明らかにしつつ完全な音の世界を再構築することにこそ主眼を持っているのであって、曲の感傷にあるいは雰囲気に耽溺することを徹底的に忌避しているんだなということを感じました。
テクニックも音色も彼の持っている技術のすべてはまさにその目的に適ったモノであるとも感得しました。
その際に、近年の演奏で気になったアクセントやシンコペーションのキツさ、唐突さはありませんし、それがポリーニだと感じていればこそ近年の演奏の変化に驚いた・・・そういうことであるようです。
でも、以前感づかなかったことを気づく私がいる・・・。
ポリーニも変化していますが、私自身も変化している。
ディスクの中の音は変化していないはずなのに、それを感じる私の感覚は変化しているということです。
諸行無常だの、行く川の流れ・・・だの、同じことをしているようでいて感じ方はその時々に違う、20年という年月を経れば事ほど左様にこれほど違う。
1年でもこれの20分の1、もっと細かく切っても・・・今日と明日でもいくばくかは違うことになるはずです。
では、以前聴いたことから得た「知識」というのは何なんだろう・・・感覚からきているこれらの経験知は、もしかしたら「邪念」以外の何者でもないかもしれません。
先に述べたアシュケナージを聞くのが大幅に遅れたなどという件も、予断であり邪見の極みであるといわざるをえませんよね。
それを「ご縁」などと言ったりすることもあるようですが、結果的には誤った判断をしていたと思います。
話が大きくなってしまいましたが、結局は「いい音楽」にめぐり合うのかどうかではなく、今いま聴いている音楽をどのように聴き、そこで音の現象をどのように認識するかという問題だけ、昨日わたしが「捌きかた」といったことにも通じるのだと思いますが、そこにいかに集中するか・・・それしかないと思うようになりました。
ポリーニのショパンは全部、他にも多くのディスクを持ち、聴いて思うのは、これほどまでにテクニックばかりが喧伝され精神がたたえられているために、期待感が高まりすぎているんじゃないかということです。
何を聴くのかをハッキリさせて臨まないと、その「現象」の認識レベルでの捉えられ方の差が大きくなってしまう典型タイプのピアニストだと思います。
ある意味では、やはり玄人受けするピアニストという評価が正しいということになるのでしょうか?
このころのポリーニが「めちゃくちゃうまいけど、よさがわからない」という方、ポリーニだと思わずに聴かれることをお勧めしたいです。
「(あれだけすごいと騒がれている)ポリーニの、この演奏のどこがいいんだろう?」と思っている人もポリーニじゃないと思えば、「なんて凄い演奏なんだ」と思われると思いますよ。
今いま、目の前で鳴っている音響だけで音楽を味わえば・・・ね。(^^;)











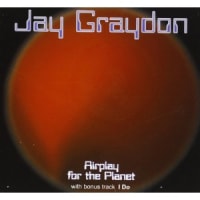
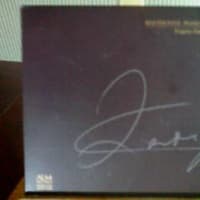
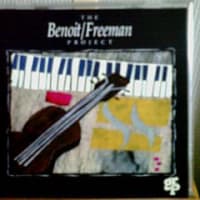
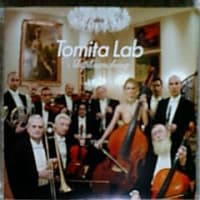
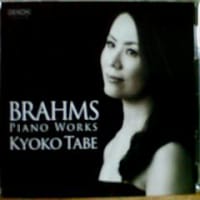

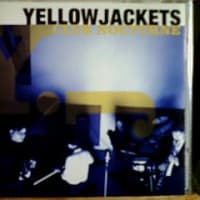


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます