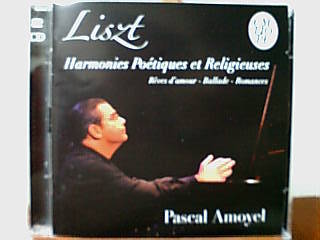★革命のエチュード ~プレイズ・ショパン
(演奏:ジャン=マルク・ルイサダ)
1.ワルツ 第1番 変ホ長調 作品18 「華麗なる大円舞曲」
2.マズルカ 第12番 変イ長調 作品17-3
3.マズルカ 第13番 イ短調 作品17-4
4.マズルカ 第15番 ハ短調 作品24-2
5.幻想曲 ヘ短調 作品49
6.ノクターン 第8番 変二長調 作品27-2
7.スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
8.プレリュード 変イ長調 作品28-17
9.プレリュード ト短調 作品28-22
10.バラード 第3番 変イ長調 作品47
11.ノクターン 第17番 ロ長調 作品62-1
12.エチュード ハ短調 作品10-12 「革命」
13.プレリュード イ長調 作品28-7
(1999年録音)
いや、この演奏はアブナイ。
ジャン=マルク・ルイサダ・・・
彼こそは、私にとってシチュエーションを変えて聴くたびに印象が異なるという鬼門の演奏家なのであります。
機会は違えどもおんなじCDを媒体として聴いているわけで、鳴っている音が同じであるからには、その演奏の心証が違うということは、当然に受け手の私の受止め方の軸がぶれているとしかいいようがありません・・・
そんな自分の拠り所のなさを思い知らされるという意味では、とっても悔しいピアニストといえましょう。
彼のディスクはショパコンで入賞後にDGから出たショパンのワルツ集ではじめて触れました。
当時手許にあったショパンのワルツ集のディスクは、ディーナ・ヨッフェのそれ・・・とっても素直で屈託のない演奏・・・ぐらいだったと思いますから、ルイサダ盤は一聴して演奏上の工夫を念入りに凝らしている解釈が顕著だと感じました。
その工夫・・・
彼の音楽は美しいピアノの音色も含めて彼自身の工夫の積み重ねの賜物であり、天啓が閃いたとか、音楽の神が降臨したといったものとは無縁に思えます。
あくまでも私の感じ方ではですが・・・。
最初は多少イビツに聴こえたとしても、一生懸命さというか人智の及ぶ範囲で持てる力を尽くしてパフォーマンスをしている態度ははっきりしており好感して聴いていたのですが、いつしかその工夫は「確信犯で行っている操作」、つまりは『罠』であると感じるようになっていきました。
そう思い込んでしまうと・・・工夫はあざとさを思わせるようになっていき、不幸なスパイラルに陥ってしまうようになっていってしまったのでした。
しかるにその後・・・
いろんな楽曲で「ルイサダ」の印がついたと知った演奏を小耳に挟むと、言葉は悪いですが先の工夫の成果が、ヤクザの鉄砲玉が精一杯のタンカを切っているような印象を生んでしまって、私にはどんどん馴染めなくなっていったものです。
この盤の演奏にせよとっても丁寧に奏されていると思うには思うのですが、例えば最後のマズルカ(前奏曲第7番)の終止前の和音に普段聴きなれない音が強調されているたった1音それだけで・・・楽譜に異稿があるかもしれないのに・・・「やりやがったな、このやろう!」という気にさせられます。
もちろん引っかかるところはその都度いろいろ・・・
普段であれば、これらを意に介せず風流と聞き流せるのに、ルイサダ印だとどうにも許せない気持ちになるのが自分でも不思議なのですが。。。
ただ、それが・・・
ルイサダ印がついていることを知らずに聴くと、彼の演奏にはどうしても耳を吸い寄せられるような現象が起きてしまうのです。
チョッと聞きには、美麗な音色、そして例の「工夫」が「おいでおいで」をしている。
どうしても言葉が悪くなりますが、他のピアニストとは明らかに違う『誘拐犯』のような手練主管であります。。。
ところで、ピアニストの中には他にも、ザラフィアンツやアファナシエフなどこれも強烈に楽曲を自分流に解釈する輩がおりますが、彼らは自分のためあるいは楽譜に忠実に尽くすためにそのように振舞っているように聴こえます。
その結果、自分の演奏や世界観に陶酔するという現象を素直に聴き取ることができるのですが、憎たらしいことに、ルイサダは誠心誠意を尽くしていながらも「効果を狙っている」ように聴こえてしまい極めて自然な世界に浸っているように見えながら「醒めた目」「薬(麻薬?)の効き具合を観察しているような目」を感じてしまうのです。
そして・・・
先の演奏者不明の奏楽を種明かしされ、果たしてルイサダの演奏とわかると「なぁ~んだ」と思ったり、ちょっとなりとも耳を奪われたことを恥じ入る・・・とまではいいませんが、気の迷いだったと思うか、どうせ長く聴いていたら鼻について飽きると見切ってしまう、そんな「予断」を抱くことが多い気がします。
もちろん、音楽を聴く際に「予断」は禁物。。。
それならば・・・
先入観を完全に排除してルイサダの音楽に向かい合った場合に、どんな真価を見出すのか・・・?
心のコップを空にするよう努めて何度もトライしたのですが、コイツの演奏はそのたびに『怪人20面相』のように違う表情を示すので本当に悔しいのです。
ルイサダのCDのオビにはえてして「ピアノの詩人」と謳われており、かねがねどうも印象が違うと思ってきました。
しかし、よくよく考えていくと「推敲に推敲を重ねて、極めて自然に響く、あるいは聴こえるように自らの解釈の力、演奏の力の及ぶ範囲を尽くして練り上げられている産物」がディスクに収められているのであり、その点「詩人」と言われればそりゃそうだと首肯しなければならない、これまた口惜しい奏楽を提供する演奏家であるわけです。
そんなに悔しいなら聴かなきゃそれまでなのですが、どうもそれも潔くないような気がする。
ここまで書いてきたことだけで、すでに二十分に潔くないのは重々わかっているのですが、切るに忍びない気持ちはあります。
当のルイサダさんはきっと極めて真面目で努力家でいらっしゃると思います。
そして私の態度にも・・・
「何をそんなに躊躇することがあるのですか?素直に私の音楽に耳をかたむけてくだされば・・・」ぐらいのことを願われるのだと思うのですが、その素直に耳を傾けることがどうしてもできないので困ってしまっているのですから・・・。
彼の流儀はともかく、演奏の仕上がりの品質の高さには敬服をします。
ジャケットのセンス(とくにBMGに移ってから)にはかねがね疑問を持っているのですが・・・これらはオトには全然関係ないし・・・。
男性的な演奏を展開しながら、女流にも通じる濃やかさを演出することもできる・・・。
普通ならば、何の文句もない賞賛の嵐となるはずなのに・・・
署名がルイサダとしてあると・・・
何故だろう?
ごめんなさい。(^^;)
(演奏:ジャン=マルク・ルイサダ)
1.ワルツ 第1番 変ホ長調 作品18 「華麗なる大円舞曲」
2.マズルカ 第12番 変イ長調 作品17-3
3.マズルカ 第13番 イ短調 作品17-4
4.マズルカ 第15番 ハ短調 作品24-2
5.幻想曲 ヘ短調 作品49
6.ノクターン 第8番 変二長調 作品27-2
7.スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
8.プレリュード 変イ長調 作品28-17
9.プレリュード ト短調 作品28-22
10.バラード 第3番 変イ長調 作品47
11.ノクターン 第17番 ロ長調 作品62-1
12.エチュード ハ短調 作品10-12 「革命」
13.プレリュード イ長調 作品28-7
(1999年録音)
いや、この演奏はアブナイ。
ジャン=マルク・ルイサダ・・・
彼こそは、私にとってシチュエーションを変えて聴くたびに印象が異なるという鬼門の演奏家なのであります。
機会は違えどもおんなじCDを媒体として聴いているわけで、鳴っている音が同じであるからには、その演奏の心証が違うということは、当然に受け手の私の受止め方の軸がぶれているとしかいいようがありません・・・
そんな自分の拠り所のなさを思い知らされるという意味では、とっても悔しいピアニストといえましょう。
彼のディスクはショパコンで入賞後にDGから出たショパンのワルツ集ではじめて触れました。
当時手許にあったショパンのワルツ集のディスクは、ディーナ・ヨッフェのそれ・・・とっても素直で屈託のない演奏・・・ぐらいだったと思いますから、ルイサダ盤は一聴して演奏上の工夫を念入りに凝らしている解釈が顕著だと感じました。
その工夫・・・
彼の音楽は美しいピアノの音色も含めて彼自身の工夫の積み重ねの賜物であり、天啓が閃いたとか、音楽の神が降臨したといったものとは無縁に思えます。
あくまでも私の感じ方ではですが・・・。
最初は多少イビツに聴こえたとしても、一生懸命さというか人智の及ぶ範囲で持てる力を尽くしてパフォーマンスをしている態度ははっきりしており好感して聴いていたのですが、いつしかその工夫は「確信犯で行っている操作」、つまりは『罠』であると感じるようになっていきました。
そう思い込んでしまうと・・・工夫はあざとさを思わせるようになっていき、不幸なスパイラルに陥ってしまうようになっていってしまったのでした。
しかるにその後・・・
いろんな楽曲で「ルイサダ」の印がついたと知った演奏を小耳に挟むと、言葉は悪いですが先の工夫の成果が、ヤクザの鉄砲玉が精一杯のタンカを切っているような印象を生んでしまって、私にはどんどん馴染めなくなっていったものです。
この盤の演奏にせよとっても丁寧に奏されていると思うには思うのですが、例えば最後のマズルカ(前奏曲第7番)の終止前の和音に普段聴きなれない音が強調されているたった1音それだけで・・・楽譜に異稿があるかもしれないのに・・・「やりやがったな、このやろう!」という気にさせられます。
もちろん引っかかるところはその都度いろいろ・・・
普段であれば、これらを意に介せず風流と聞き流せるのに、ルイサダ印だとどうにも許せない気持ちになるのが自分でも不思議なのですが。。。
ただ、それが・・・
ルイサダ印がついていることを知らずに聴くと、彼の演奏にはどうしても耳を吸い寄せられるような現象が起きてしまうのです。
チョッと聞きには、美麗な音色、そして例の「工夫」が「おいでおいで」をしている。
どうしても言葉が悪くなりますが、他のピアニストとは明らかに違う『誘拐犯』のような手練主管であります。。。
ところで、ピアニストの中には他にも、ザラフィアンツやアファナシエフなどこれも強烈に楽曲を自分流に解釈する輩がおりますが、彼らは自分のためあるいは楽譜に忠実に尽くすためにそのように振舞っているように聴こえます。
その結果、自分の演奏や世界観に陶酔するという現象を素直に聴き取ることができるのですが、憎たらしいことに、ルイサダは誠心誠意を尽くしていながらも「効果を狙っている」ように聴こえてしまい極めて自然な世界に浸っているように見えながら「醒めた目」「薬(麻薬?)の効き具合を観察しているような目」を感じてしまうのです。
そして・・・
先の演奏者不明の奏楽を種明かしされ、果たしてルイサダの演奏とわかると「なぁ~んだ」と思ったり、ちょっとなりとも耳を奪われたことを恥じ入る・・・とまではいいませんが、気の迷いだったと思うか、どうせ長く聴いていたら鼻について飽きると見切ってしまう、そんな「予断」を抱くことが多い気がします。
もちろん、音楽を聴く際に「予断」は禁物。。。
それならば・・・
先入観を完全に排除してルイサダの音楽に向かい合った場合に、どんな真価を見出すのか・・・?
心のコップを空にするよう努めて何度もトライしたのですが、コイツの演奏はそのたびに『怪人20面相』のように違う表情を示すので本当に悔しいのです。
ルイサダのCDのオビにはえてして「ピアノの詩人」と謳われており、かねがねどうも印象が違うと思ってきました。
しかし、よくよく考えていくと「推敲に推敲を重ねて、極めて自然に響く、あるいは聴こえるように自らの解釈の力、演奏の力の及ぶ範囲を尽くして練り上げられている産物」がディスクに収められているのであり、その点「詩人」と言われればそりゃそうだと首肯しなければならない、これまた口惜しい奏楽を提供する演奏家であるわけです。
そんなに悔しいなら聴かなきゃそれまでなのですが、どうもそれも潔くないような気がする。
ここまで書いてきたことだけで、すでに二十分に潔くないのは重々わかっているのですが、切るに忍びない気持ちはあります。
当のルイサダさんはきっと極めて真面目で努力家でいらっしゃると思います。
そして私の態度にも・・・
「何をそんなに躊躇することがあるのですか?素直に私の音楽に耳をかたむけてくだされば・・・」ぐらいのことを願われるのだと思うのですが、その素直に耳を傾けることがどうしてもできないので困ってしまっているのですから・・・。
彼の流儀はともかく、演奏の仕上がりの品質の高さには敬服をします。
ジャケットのセンス(とくにBMGに移ってから)にはかねがね疑問を持っているのですが・・・これらはオトには全然関係ないし・・・。
男性的な演奏を展開しながら、女流にも通じる濃やかさを演出することもできる・・・。
普通ならば、何の文句もない賞賛の嵐となるはずなのに・・・
署名がルイサダとしてあると・・・
何故だろう?
ごめんなさい。(^^;)