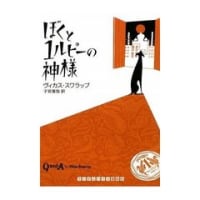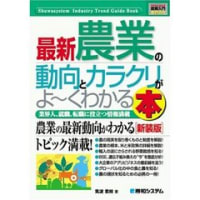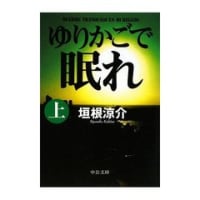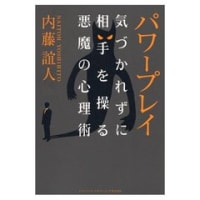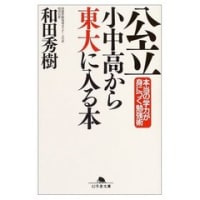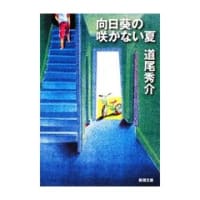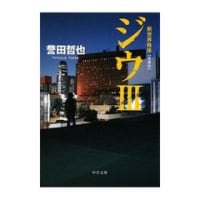同じペットボトル飲料が、スーパーでは88円で売っているが、店の前の自動販売機では150円で売っているということがある。どうして、同じものなのに価格が違うのか?
携帯電話の料金設定は、なぜ多様で複雑なのか?
こういった、我々が日常接する「価格」というものを通じて、やさしく経済のメカニズムを解説してくれています。
「差別価格」という概念は新鮮でした。高く買う客には高く、安くないと買わない客には安い価格で売る。他に手段のない者には高い値段でうる。何となく「そうなんだろうなあ」と考えていたものを明確に解き明かしてくれています。
売る側(企業)は、利益を最大限にしようと考え・工夫して価格設定している。だからこそ、携帯電話の利用料に複雑怪奇は料金設定ができている。複雑さに屈服する利用者は価格差別の餌食になるとさえ著者は言っています。
もう一つ、価格を考える際に重要なのが「取引コスト」という概念。例えば、スーパーで88円で売っているペットボトルのお茶が、コンビニで150円で売っている場合があるが、これは「冷やす」や「すぐにほしいお茶が見つかり時間が節約できる」といったサービスも買っていることになるから。これが「取引コスト」というもの。
この取引コストを販売側と購入側のどちらがどれだけ負担するかで、価格が変動することとなる。
自分の生活の”満足度”を上げるには、こういった価格の仕組みを大まかにでも理解することが、一つの有力な手段になるのだと思います。
携帯電話の料金設定は、なぜ多様で複雑なのか?
こういった、我々が日常接する「価格」というものを通じて、やさしく経済のメカニズムを解説してくれています。
「差別価格」という概念は新鮮でした。高く買う客には高く、安くないと買わない客には安い価格で売る。他に手段のない者には高い値段でうる。何となく「そうなんだろうなあ」と考えていたものを明確に解き明かしてくれています。
売る側(企業)は、利益を最大限にしようと考え・工夫して価格設定している。だからこそ、携帯電話の利用料に複雑怪奇は料金設定ができている。複雑さに屈服する利用者は価格差別の餌食になるとさえ著者は言っています。
もう一つ、価格を考える際に重要なのが「取引コスト」という概念。例えば、スーパーで88円で売っているペットボトルのお茶が、コンビニで150円で売っている場合があるが、これは「冷やす」や「すぐにほしいお茶が見つかり時間が節約できる」といったサービスも買っていることになるから。これが「取引コスト」というもの。
この取引コストを販売側と購入側のどちらがどれだけ負担するかで、価格が変動することとなる。
自分の生活の”満足度”を上げるには、こういった価格の仕組みを大まかにでも理解することが、一つの有力な手段になるのだと思います。