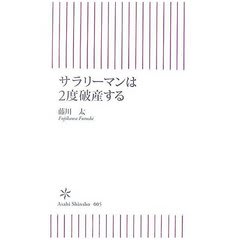「そのプレーの意図は?」と訊かれたとき、監督の目を見て答えを探ろうとする日本人。一方、世界の強国では子どもでさえ自分の考えを明確に説明し、クリエイティブなプレーをしている。
日本サッカーに足りないのは自己決定力であり、その基盤となる論理力と言語力なのだ。
本書は、公認指導者ライセンスや、エリート養成機関・JFAアカデミー福島のカリキュラムで始まった「ディベート」「言語技術」といった画期的トレーニングの理論とメソッドを紹介する。
自分の考えを表現すること。ディベート技術の必要性。サッカーに限らず、日本の初等・中等教育での必要性がたびたび取り上げられます。
そんな中、サッカーの指導者がすでにその必要性を認識し、既に指導に取り入れていることに驚きました。
サッカー界は、既に小学生頃からユースチームなどで指導が行われたりしていて、子供から大人までトータルの指導システムが出来上がっているようです。ここまで、日本のサッカー界を作り上げてこられたのは、早くから海外の指導方法を勉強したりして、Jリーグが盛りがる前から、50年・100年先を見越してシステムを作ろうとしてきた方々の努力のおかげのような気がします。
サッカーに限らず、教育者・指導者たる者は、常に勉強し、新しい指導方法を身に着けることが求められているのです。それが、次世代を担う者を大きくし、結果としてその次の世代にも発展していく道筋ができるのでは。
教育者・指導者には「情熱」が必要なのです。
日本サッカーに足りないのは自己決定力であり、その基盤となる論理力と言語力なのだ。
本書は、公認指導者ライセンスや、エリート養成機関・JFAアカデミー福島のカリキュラムで始まった「ディベート」「言語技術」といった画期的トレーニングの理論とメソッドを紹介する。
自分の考えを表現すること。ディベート技術の必要性。サッカーに限らず、日本の初等・中等教育での必要性がたびたび取り上げられます。
そんな中、サッカーの指導者がすでにその必要性を認識し、既に指導に取り入れていることに驚きました。
サッカー界は、既に小学生頃からユースチームなどで指導が行われたりしていて、子供から大人までトータルの指導システムが出来上がっているようです。ここまで、日本のサッカー界を作り上げてこられたのは、早くから海外の指導方法を勉強したりして、Jリーグが盛りがる前から、50年・100年先を見越してシステムを作ろうとしてきた方々の努力のおかげのような気がします。
サッカーに限らず、教育者・指導者たる者は、常に勉強し、新しい指導方法を身に着けることが求められているのです。それが、次世代を担う者を大きくし、結果としてその次の世代にも発展していく道筋ができるのでは。
教育者・指導者には「情熱」が必要なのです。