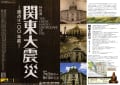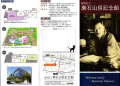久しぶりに花火を間近で見ることが出来た。花火の打ちあがる方向とは反対側には、本日の月齢10の月。一昨日が上弦の月(半月)であった。西の空は厚く黒い雲が遠望でき、強い雨が降っていそうであったが、見ていた場所は雲が切れ、雨の心配はなかった。夕陽が映えた遠くの入道雲が美しかったが、スマホのカメラでは小さく映っただけ。
スマホで、固定もせずに花火を何枚も写したが、これ以上に鮮明なのはなかった。
花火、はやりもあるし、新しいものもあり、年々の進化を見極めるのも楽しいというが、素人目にはただ珍しい、目新しいと思うだけ。作成する職人の苦労はなかなかわからない。
花火は近くで見て、大きな音が少し遅れてドンと響く距離で見るのは迫力がある。一方で音はかすかで、地平線近くにしか見えない遠花火もまた風情があるものである。要するに何処から見てもうれしい。
私の頭の中では、夏の終わりに見ることにこだわりがある。最近では冬の花火大会もあるらしい。それもおもしろいのかもしれないが、なかなか頭の中で受け入れられない。何事も柔軟に受け入れたいのはやまやまである。一度見る機会があれば美しい、と思うのかもしれない。そんな機会があるだろうか。
花火大会を見に行くときも、帰りも電車はかなり混んだ。帰りのほうが少し難儀であった。