本日は「湘南幻想美術館」(太田治子)から8編に目をとおした。
目をとおした中で、一番惹かれた作品はどれか、と言われたらちょっと困ってしまう。
あえて云えばルネ・マグリットの「王様の美術館」であろうか。このマグリットの作品は、人物の形に層状の雲と手前から黒い森が切り取られている。夜空なのだろうか、青い空が現実離れしている。そして中央に建物が寂しげに立っている。表題からするとこれが美術館らしい。人物の顔は左右対称だが、人物の形に切り取られた風景は左右対称から少しずれ、背景の建物のバルコニーは丸い石が、左右対称を破戒している。左右対称からの微妙なズレが、不安定な現実を表象しているかのようである。太田治子の紡ぐ物語も過去の危うい非日常を生きる祖父の思い出であり、この絵の不安定な雰囲気を反映していると感じた。
夕方近くになってから横浜駅近くのいつもの喫茶店まで出かけて、一服。「湘南幻想美術館」(太田治子)を読んだ。本日は10編をのんびりと読んだ。

印象に残った絵画作品は、ギュスターヴ・クールベ《海岸の竜巻〈エトルタ〉》(1870年)と、佐伯祐三《窓のある建物:パリ風景》(1925年)の2作品。
これらの作品につけられたストーリーは少々私の持つ絵に対する印象とはかなり違う。もっともではどんなストーリーを想像したのか、と問われると硬い頭の私には答えようがない。
著者である太田治子は、クールべの作品に、一見誠実さを装いながら女を口先で騙そうという男の話を配した。佐伯祐三の作品には、すぐにばれる嘘をついて女を騙す軽薄な男を配した。
クールベの作品からは、自然の威力に対するに人間の観察力を対峙しようとする意志の力。佐伯祐三の作品からは都会の片隅の崩れそうな建物の向こうにうらぶれた庶民の生活。これを私は感じている。そんな物語を匂わすものを想像している。
感じ方はいろいろなものがあることは前提である。反撥も含めていろいろな想像力を駆り立ててくれるこの書物に感謝している。



本日「幻想美術館」を読み終えた。少しペースが早すぎたかもしれない。各作品ごとにもう少し自分なりの想像力を働かせて物語を紡いでみてから、著者の物語に目をとおしたほうが、楽しかったかもしれない。私には少々甘く切ない物語になりすぎている、という感想も無きにしも非ず。それでもいい刺激を与えてもらったと感謝である。
全体51作品のうち、7作品は私も以前に感銘を受けたり、楽しいと思った作品である。この外に佐伯祐三の《モラン風景》(1928)や、ベルト・モリゾの《ベランダにて》(1884)などは以前に見たかもしれないが、残念ながら特に記憶に残っていなかった。
またどこかで見たものの違和感を抱いていた作品もある。今回あらためて自分の想像力の貧困に気づいた作品もあった。
少なくとも作品を掲載した7作品については、あらためて自分なりの想像力を試してみたいと思った作品である。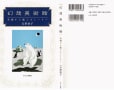
読み始めた「魔女狩りのヨーロッパ史」は目をとおさず、「幻想美術館」(太田治子)から6編ほど読んだ。家に籠っている時は短くて完結する文章のほうがいい。
昨日読んだ中で印象に残ったのは、アンリ・マティスの《肘掛椅子の女性》(1933-34)を取り上げた一編。
私はこの作品、というかマティスの作品は色彩の妙味ばかりに目を取られて、作品から物語を紡ぐということがまったく出来ていなかった。そしてマティスの作品はどちらかというと「苦手」であった。
太田治子は母と娘の物語を紡いでいる。「白地に青い花柄のワンピース姿の女性は、肘掛椅子にふんぞり返っていた。思い切り吊り上がった眼は、暗く光っているように思われた。」と記している。
私はこれまでマティスの描く人物から表情を読み取ったことがなかった。表情は消されるようにぼかされている作品が多く、人物はあくまでも点景として、あるいは服装による色彩の配置の一環でしかないと感じていた。この作品でも女性の顔にはうすらと影のようなものが塗られて表情が読み取りにくい。これを私はマティスがあえて表情を消すように描いたものだと勝手に考えていた。この作品から上記のようにふんぞり返り、吊り上がった目、を見つける鑑賞はできなかった。まして太田治子のように母と娘が見つめる相互の意識に踏み込むことはできなかった。
これを気にマティスの作品の見方を変えてみることにした。少しは年齢と共にますますギスギスとしてきた想像力、感受性にいい刺激になるかもしれない。
昨日竹橋にある東京国立近代美術館から帰る途中、川崎駅で下車し、「川崎浮世絵ギャラリー」を訪れた。ギャラリーでは「浮世絵に見る異国」展を開催していた。
東京駅から国立近代美術館までの往復を歩き、美術館の中でも1時間以上時間を掛けて巡ったので、かなり疲れていた。しかし夕食まで時間もあり、ふたりとも足がだるいのを我慢して、浮世絵、幕末から明治初期の錦絵・横浜絵を楽しんできた。
「異国」を描いた作品も見ることが出来たが、来るたびに展示されていることの多い「唐土廿四考」の12作品が、妻も私も印象に残った。現代の私たちには到底信じられなく、そのあまりに惨い「孝行」なるものになかば呆れながら解説を読んだ。
真冬に親の所望する筍を取りに行ったという「孟宗」に触発されて、ちょうど筍が出始めた時期でもあり、家の近くのスーパーで筍を購入してみた。
しかしここまで規範として取り上げる「親孝行」とは何なのだろうか。逆に年老いた家族の面倒を見ることもできないきびしい中国という地域の当時の社会の現実が反映していたのではないか、などと想像したりもした。
「狂画水滸伝豪傑一百八人十番続」は、武芸のパロディともいえ、「武士道」なるものへの茶化しともいえる強さを感じた。同時に「唐土廿四考」など笑い飛ばしかねないしたたかさも感じた。
本日は東京国立近代美術館へ「中平卓馬 火 氾濫」展に行ってきた。あまり混雑はしていないと思っていたが、入場券売り場は20人ほど並んでいた。しかし会場は広く、じっくりと見ることが出来た。
美術館のホームページには次のような解説がある。
《見どころ》
[これまで未公開の作品を多数展示]
近年その存在が確認された《街路あるいはテロルの痕跡》の1977 年のヴィンテージ・プリントを初展示。昏倒によって中平のキャリアが中断する前の、最後のまとまった作品発表となった雑誌掲載作13 点です。2021 年に東京国立近代美術館が本作を収蔵して以来、今回が初めての展示となります。また1976 年にマルセイユで発表されて以来、展示されることのなかった《デカラージュ》など、未公開の作品を多数展示します。
[カラー写真の重要作を一挙に展示]
1974 年に東京国立近代美術館で開催した「15 人の写真家」展の出品作《氾濫》をちょうど半世紀ぶりに同じ会場で再展示します。カラー写真48 点組で構成される幅約6 メートルの大作で、中平のキャリア転換期における重要作です。
また、中平存命中最後の重要な個展「キリカエ」(2011 年)に展示されたカラーの大判プリント64 点を展示します。
[雑誌から読み解く中平の試み]
『アサヒグラフ』や『朝日ジャーナル』など、キャリア前半の1960 年代から1970 年代前半にかけて発表された作品の掲載誌を多数展示。当時、雑誌は社会にイメージを流通させる手段として重要な役割を担っていました。写真がどのように流通するかについて常に意識的だった中平が、同時代の社会に対して、写真を用いて何を試みようとしていたのか、その実態を紹介します。
[展覧会構成・主な展示作品]
本展は初期から晩年にいたる中平卓馬の仕事を、5つの章でたどります。とくに2~4章では、1977 年に不慮の昏倒と記憶喪失により中断した中平の仕事が、どこへ向かおうとしていたのか、そこにいたる70 年代の展開を詳しくひもときます。
《中平卓馬プロフィール》
1938年東京生まれ。1963年東京外国語大学スペイン科卒業、月刊誌『現代の眼』編集部に勤務。誌面の企画を通じて写真に関心を持ち、1965年に同誌を離れ写真家、批評家として活動を始める。
1966年には森山大道と共同事務所を開設、1968年に多木浩二、高梨豊、岡田隆彦を同人として季刊誌『PROVOKE』を創刊(森山は2号より参加、3号で終刊)。「アレ・ブレ・ボケ」と評された、既成の写真美学を否定する過激な写真表現が注目され、精力的に展開された執筆活動とともに、実作と理論の両面において当時の写真界に特異な存在感を示した。
1973年に上梓した評論集『なぜ、植物図鑑か』では、一転してそれまでの姿勢を自ら批判、「植物図鑑」というキーワードをかかげて、「事物が事物であることを明確化することだけで成立する」方法を目指すことを宣言。翌年、東京国立近代美術館で開催された「15人の写真家」展には48点のカラー写真からなる大作《氾濫》を発表するなど、新たな方向性を模索する。そのさなか、1977 年に急性アルコール中毒で倒れ、記憶の一部を失い活動を中断。療養の後、写真家として再起し、『新たなる凝視』(1983)、『Adieu à X』(1989)などの写真集を刊行。 2010年代始めまで活動を続けた。2015年逝去。
1973年、自己批判を機に、それまでのプリントやネガの大半を焼却したとされていたが、2000 年代初頭、残されていたネガが発見され、それをきっかけとして2003年には横浜美術館で大規模な個展「中平卓馬:原点復帰-横浜」が開催された。
中平卓馬の作品と人となり、主張は「犬の記憶」「犬の記憶終章」(森山大道)をとおして、また2003年横浜美術館での個展、さらに同時代性もあり、馴染みのある写真家である。同時に時々作品が見たくなることもある。そのたびに気に入った作品を見つけたり、再発見したりする。真似したい作品もある。
「時代」と「反乱」ということを手放しては鑑賞できない。モノクロもカラーも惹かれる。しかし「ヴィンテージ・プリント」などという紹介が果たして中平卓馬にふさわしいとは思えないのだが・・・・。時代もずいぶん変わったものである。
ヴラマンクの三越で開催されていた「没後30年・フランス野獣派の旗手 ブラマンク展」の図録を見ていたら、この作品《林檎の木と燕麦の畑》(1943年)という風景画が目に付いた。
確かに見た記憶がある。1943年というのはヴラマンクが47歳頃の作品である。展覧会で見た当時の印象も思い出した。中央の嵐がやってくる前の不安な雲か、嵐の過ぎ去った後の雲間から差す陽射しを受けた雲か、どちらなのか不明であるが印象に残った。
しかし題名を見ると、雲の下の燕麦と手前の木に作者は着目していたことになる。
構図的に見ると、木の横に延びた幹の葉、雲、燕麦、手前の土に映る斜めの太陽光線の束、この強い横の線に対して右端の林檎の木の垂直な太い幹、実に単純である。しかし太陽光線の輝きと暗部が交互に重なって複雑である。またこの林檎の木の曲がり具合が実にいい。
今回は畑の麦の細い垂直な線の連続もまた見どころに思えた。広々とした空間を演出している。もうひとつ雲は実にさまざまな形態をしているのも目に付いた。低い群雲、黒い雨雲、高層の雲等嵐に搔き乱された大気の様相を表している。
念入りな構想力を感じた。
読書の気力があまり湧いてこないので、本棚から2冊のモーリス・ド・ヴラマンク(1876-1958)の図録を2冊引っ張り出してきた。ひとつは1989年に日本橋三越で開催された「没後30年・フランス野獣派の旗手 ブラマンク展」と、1997年にBunkamuraザ・ミュージアムで開催された「生誕120年記念 ヴラマンク展」の図録である。
「花瓶の花」(1939-40年)は前者に展示され、「花」(1940年)は後者に展示されていた。
激しい嵐の風景画を描くブラマンクが、静物画、しかも花瓶の花を描くのかと驚いたものだが、激しいタッチの花々が花瓶からあふれ出るように描かれている。大変印象的な作品を両展覧会で堪能した。
特に黄色の細い花弁とつややかな黒い花瓶が印象的な「花」を私は気に入っている。白い花弁に呼応するように多分室内の光の乱反射を描いたと思われる白い光線の短い煌めきも線香花火のように忘れられない。
この外の花瓶と花を描いた作品が多数展示されていた。硬質で陶器の表面のつややかな花瓶をねっとりとした質感に描き、対称的にそれまでの画家が柔らかく描こうとした花を勢いのある強い筆致で描いた転換が私の目に新鮮に映った。粗い勢いのある筆致と言ったが、決してぞんざいではなく、花の形や色彩は良く計算された描き方でもある。
しかしこの激しい生の横溢に圧倒されるような花と花瓶は、狭く密閉された日本の家屋には合わない。少なくとも我が家の壁に掛けたら、圧倒されて居住者である私は縮こまってしまいかねない。
2冊の図録はだいぶぼろぼろになってきた。
夕食は久しぶりに娘を交えて。娘が帰宅後は、静かにモーツアルトの「ホルン協奏曲」の第1番から第4番、ならびに同梱の「ホルンとオーケストラのためのロンドK.371」を聴いている。ホルンはペーター・ダム、ネヴィル・マリナー指揮でアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ、1988年の録音。
何となく疲れた時や、静かな時間が欲しいときはこの曲はいい。
明日は朝9時前には家を出て、組合の会館へ。3月の退職者会幹事会。午前中は役員会等、昼からは作成した退職者会ニュースと、ブロックニュースの発送日、午後からは幹事会等、15時からは講演会。夕方まで目いっぱいの予定である。いつものとおり、きわめて慌ただしい一日である。
金色堂は過去に現地で3度見た。中を見たのは2回。最初は学生の時に一人で訪れたが、外から金色堂を眺めただけだったと思う。その後2回訪れたときに中も見ることが出来た。しかしあまり近くからは見ることはできなかったのと、手前の欄干や密集して配置されているので、台座などをじっくりと見ることはできなかった。
今回、中央の須弥壇の11体が展示されている。ガラスケースにおさめられているが、ここまで近くから見ることが出来て、ありがたかった。
増長天立像と持国天立像は金箔に顔が覆われているにもかかわらず、優美さや豪華さというよりも力を感じた。私がいつも天部の像に抱く違和感をあまり感じなかった。私はいつも彼等の膝が伸びきって、そのために腰をぐっと落としみなぎる力をため込んだ力強さが抜けていくように見えてしまう。いつの時代でも、誰の作でもこの感想は変わったことがない。
この像も膝が伸びきってはいるが、しかし軽やかな飛翔をしているように見え、違和感が薄らいだ。足で踏みつけている悪鬼が雲の形にも見えるのが不思議である。雲の形をしていることで、飛翔しているように見えるのだと思う。今回の展示では良い体験が出来た。
安田登の「『おくのほそ道』謎解きの旅」を先日読み終えたばかりであるが、そこにこんな記述があった。
「ヨーロッパの日本ブームを作ったのはマルコ・ポーロの「東方見聞録」。・・・黄金の島、ジパングを作ったのは、中尊寺金色堂などの黄金文化を謳歌した平泉ではなかったかと言われています。この平泉こそ奥州藤原氏の都であり、繁栄の証なのです。」(第6章「鎮魂の旅」)
あらためて平泉という場所について考えさせられた。
東博の「本阿弥光悦の大宇宙」展では、次の5点が気に入った。
まずは、やはり目玉展示の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」(重要文化財)、「花卉鳥下絵新古今集和歌巻」、「松山花卉摺下絵新古今集和歌巻」。
解説には「松山花卉摺下絵新古今集和歌巻」は、料紙の継ぎ目裏には「紙師宗二」の印があるとのこと。「鶴下絵・・・」と比べて「筆の打ち込みが柔らかく全体的にたおやか」と記されている。
料紙の選択もまた光悦の美意識に沿ったものであるのだろうが、私はこの巻頭の山と梅、藤、芒様の「雌日芝(めひしば)」がとても気に入った。筆の肥痩のリズムと和歌の句の上下、そして料紙の文様の上下のリズムが実に心地良いと思った。
出来れば描かれた歌を知りたいものである。多分、歌の内容と料紙の文様にも対応関係はあるのだろう。

次に茶碗のコーナーでは特に「黒楽茶碗 銘時雨」と「赤楽茶碗 銘乙御前」(共に重要文化財)が気に入った。黒楽茶碗は照明によって釉薬の色合いが変化して見える用だ。展示ではあまりに強い照明なので、白く浮き上がる口縁の部分が黒く沈んでしまったのかもしれない。
「時雨」「乙御前」ともに手に取って、自然光下の家屋の中で見たかった。また緑色の抹茶の色が底に映えるのを見たいと思ったが、到底適えられない願望である。
明日の午前中はオンラインの美術鑑賞講座「初めての日本美術史」(講師:中村宏美氏)の第2回目で「平安時代後期の美術」。資料を打ち出し終わったばかり。
午後以降は特に予定は入っていない。
本日の横浜の最高気温は昨日よりも10℃以上低くなり、13.9℃。しかしこの気温は昨晩の日付が替わった直後の気温。日中は8℃台で終止していた。ということは日中は16℃も低かったことになる。
それでも天気予報に従って身構えたよりは寒くはなかった。明日はもう少し下がるらしい。日中は5℃から7℃くらいで推移するようだ。本日よりも、北風が少し強く雨の時間も長いかもしれないという。
講座が終わってから、出かけるかどうか、決めたい。

































