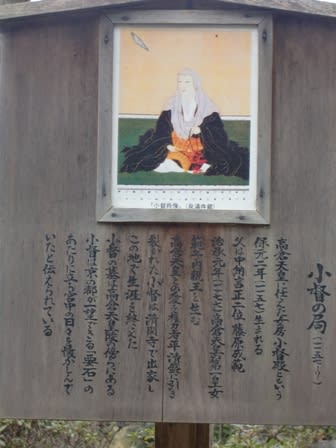香港から帰省中のcmeliaさんと、妹さんNoriさん、
下の妹さんCieさんとNoriさんのご主人の車で
千葉県の佐倉散策に連れて行っていただきました。


旧堀田邸
堀田正倫(まさとも)の邸宅で明治23年竣工、正倫は最後の佐倉藩主でした。
明治時代になると華族として東京に住んでいましたが、佐倉で国の基となる
農業と教育の発展に尽くそうとしました。


佐倉の邸宅の周辺に農事試験場を明治30年に作り

学問の奨学会も作りました、往時の堀田邸は農事試験上の敷地など含めると
約3万坪の広さだったそうです。 桜の庭に出てみました。

庭園は下総台地を借景にしていて、市民の憩いの場となっています

ソメイヨシノが満開でした

現在は3分の1ほどの広さだそうです

次に訪れたのは「旧佐倉順天堂」
蘭医 佐藤泰然が天保14年(1843)に開いた欄医学の塾
佐倉順天堂。



医療器具や書籍等が展示されています



明治時代の医学界をリードする人材を数多く輩出すると同時に
最先端の医療が施されていた。
佐倉は城下町、武士の住む町と商人の住む町に分けられていました。
城の周りに広く配されていた武家屋敷も見ることができます。

旧河原家住宅
道路に接する部分を正面とし、門を設け、土塁と生垣を築き
その奥に玄関や庭を設けていました。


武家屋敷の規模や様式は、居住する藩士の身分の象徴でもあります

こちら河原家は大屋敷だそうです


当主の書斎でしょうか 台所の隣の部屋、女性の部屋でしょう


住宅の裏に希少種の椿が植えられていました

花は黒紅色、珍しい色の椿でした
屋敷の裏側に菜園等を設け、屋敷の境には境界木が植えられ
背後の斜面は竹やぶなどになっていました。
江戸後期の建築で、佐倉藩士が暮らしていた3棟が公開されて
います、それぞれの石高に応じた暮らしぶりの違いが見られます。