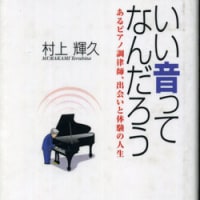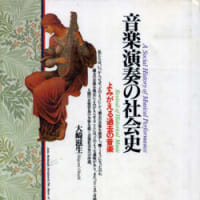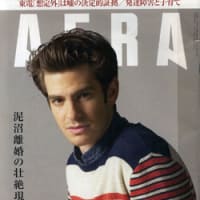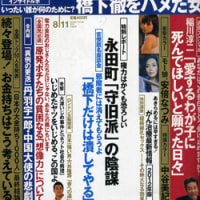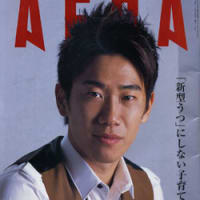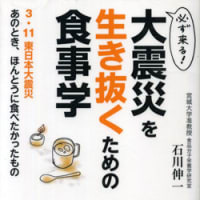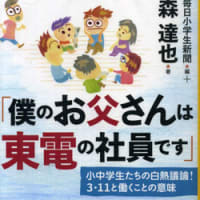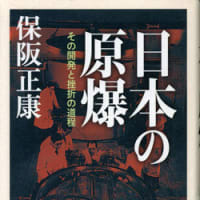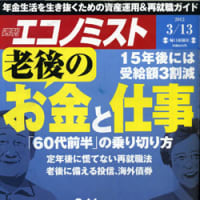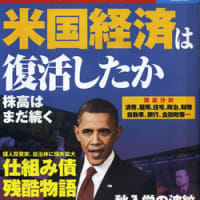『青い光が見えたから
〔16歳のフィンランド留学記〕』
高橋絵里香・著/講談社2007年
ムーミンの国に憧れて、ひとりで留学した高校生の話。フィンランドは民主的な国に思えました。

ムーミンについて書かれておられます。下「」引用。
「子どものための本にありがちな、登場人物は「みんなお互い仲良し」という社会もなく、登場人物を「悪者」や「良い人」にはっきり区別することもない。そういう意味では、ムーミントロールたちが森の妖精であるにもかかわらず、限りなく私たちの現実に近い、人間くさい世界が描かれていた。」
親切な人たちに出会ったようです。下「」引用。
「ライヤさんは、貸してくれていたCDラジカセと電気スタンドを、もう使わないからと言って、私にゆずってくれた。必要最低限のものしか持っていなかった私には、とてもありがたいプレゼントだった。」
ジョンさんの生活を思い出した。
フィンランドの野球。下「」引用。
「音楽と同様に、フィンランド語力が壁にならない体育の授業で、初めてフィンランド式野球というものをやってみることなった。日本の野球とちがうのは、キャッチャーがいなくて、ピッチャーがバッターのすぐとなりでボールを真上に投げるというところだが、ピッチャーの手がバットで打たれそうになったり、危ない眼にもあったりする。」
ボクらのタイベンを思い出すなあー。だいぶ違うけど……。自分たちで楽しめるように変えた……。
日本語ってかっこいいねというサンニ。
トレーナーに日本語が書かれてあるという。
それは「いのしし」、知って笑っていたという。
試験は0点だったのに成績は10段階の5だったという。
読書感想発表や授業態度とをあわせて評価してくれたという。
先生と呼ばれるよりも、名前で呼ばれる方が生徒に慕われているという。下「」引用。
「中学生の頃、「生徒が自分に敬語を使わなくなつた」と嘆いている先生がいたことを思い出していた。だがそれは、生徒にナメらていたわけではなく、生徒が先生を近い存在だと感じていたからだったのだろう、とヴァルプの話をきいて思った。」
敬語というのは、やはり封建的なもののように思えてなりません。
尊敬しているかどうかは形ではなく、ハートで知ってもらいたいものですね。
「美化語」なんて、醜いものさえ、美しくすることがいいことみたいで、ボクはイヤですね。
あやまらなくていい、何をそんなにこわがっているの?
そうヴァルプは言ったという。
--ストレス社会、日本! とボクは思いました。
宗教教育もあったという。下「」引用。
「多くの人がキリスト教、その多くがルター派を信仰しているフィンランドでは、学校でも「宗教」は必修の科目だ。だが当然、別の宗教を信仰している人もいれば、無宗教の人も少数ながらいて、その人たちのためには「倫理学」という別の教科が用意されていた。」
高校を卒業して、フィンランドのオウル大学の自然科学学科にて、生物学と地質学を学んでいるという。
すばらしいね!
 index
index


〔16歳のフィンランド留学記〕』
高橋絵里香・著/講談社2007年
ムーミンの国に憧れて、ひとりで留学した高校生の話。フィンランドは民主的な国に思えました。

ムーミンについて書かれておられます。下「」引用。
「子どものための本にありがちな、登場人物は「みんなお互い仲良し」という社会もなく、登場人物を「悪者」や「良い人」にはっきり区別することもない。そういう意味では、ムーミントロールたちが森の妖精であるにもかかわらず、限りなく私たちの現実に近い、人間くさい世界が描かれていた。」
親切な人たちに出会ったようです。下「」引用。
「ライヤさんは、貸してくれていたCDラジカセと電気スタンドを、もう使わないからと言って、私にゆずってくれた。必要最低限のものしか持っていなかった私には、とてもありがたいプレゼントだった。」
ジョンさんの生活を思い出した。
フィンランドの野球。下「」引用。
「音楽と同様に、フィンランド語力が壁にならない体育の授業で、初めてフィンランド式野球というものをやってみることなった。日本の野球とちがうのは、キャッチャーがいなくて、ピッチャーがバッターのすぐとなりでボールを真上に投げるというところだが、ピッチャーの手がバットで打たれそうになったり、危ない眼にもあったりする。」
ボクらのタイベンを思い出すなあー。だいぶ違うけど……。自分たちで楽しめるように変えた……。
日本語ってかっこいいねというサンニ。
トレーナーに日本語が書かれてあるという。
それは「いのしし」、知って笑っていたという。
試験は0点だったのに成績は10段階の5だったという。
読書感想発表や授業態度とをあわせて評価してくれたという。
先生と呼ばれるよりも、名前で呼ばれる方が生徒に慕われているという。下「」引用。
「中学生の頃、「生徒が自分に敬語を使わなくなつた」と嘆いている先生がいたことを思い出していた。だがそれは、生徒にナメらていたわけではなく、生徒が先生を近い存在だと感じていたからだったのだろう、とヴァルプの話をきいて思った。」
敬語というのは、やはり封建的なもののように思えてなりません。
尊敬しているかどうかは形ではなく、ハートで知ってもらいたいものですね。
「美化語」なんて、醜いものさえ、美しくすることがいいことみたいで、ボクはイヤですね。
あやまらなくていい、何をそんなにこわがっているの?
そうヴァルプは言ったという。
--ストレス社会、日本! とボクは思いました。
宗教教育もあったという。下「」引用。
「多くの人がキリスト教、その多くがルター派を信仰しているフィンランドでは、学校でも「宗教」は必修の科目だ。だが当然、別の宗教を信仰している人もいれば、無宗教の人も少数ながらいて、その人たちのためには「倫理学」という別の教科が用意されていた。」
高校を卒業して、フィンランドのオウル大学の自然科学学科にて、生物学と地質学を学んでいるという。
すばらしいね!
 index
index